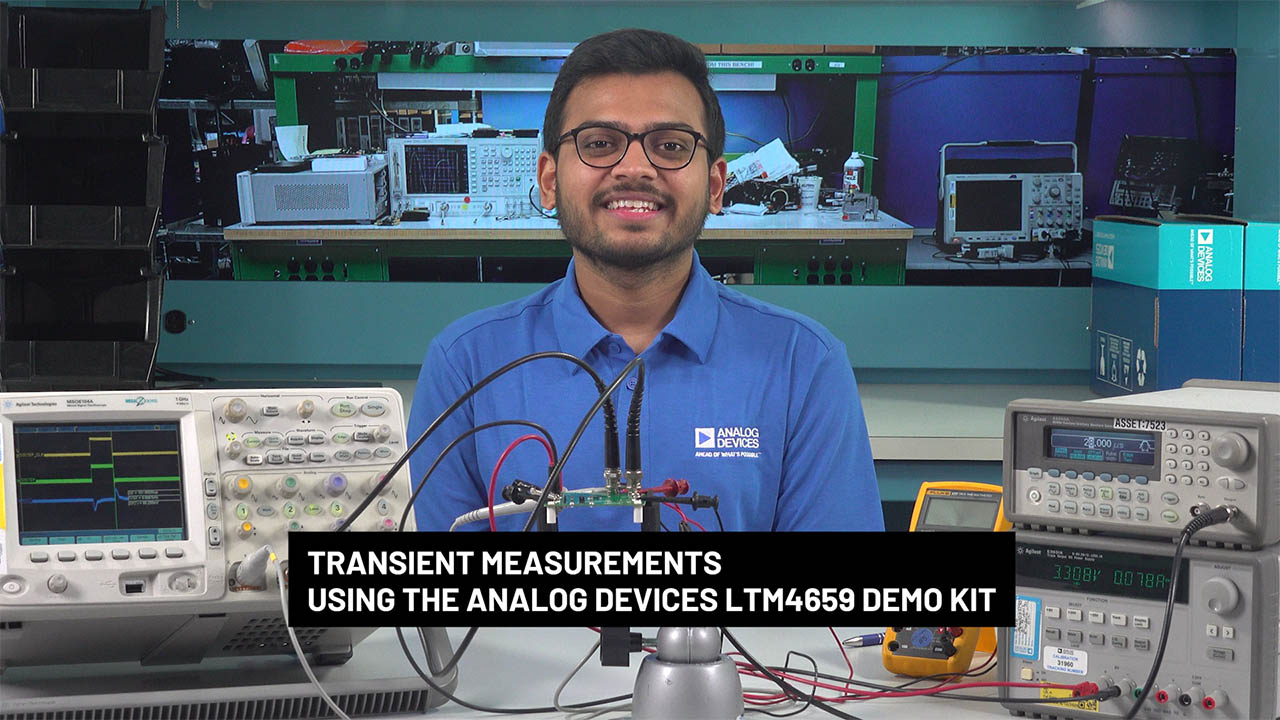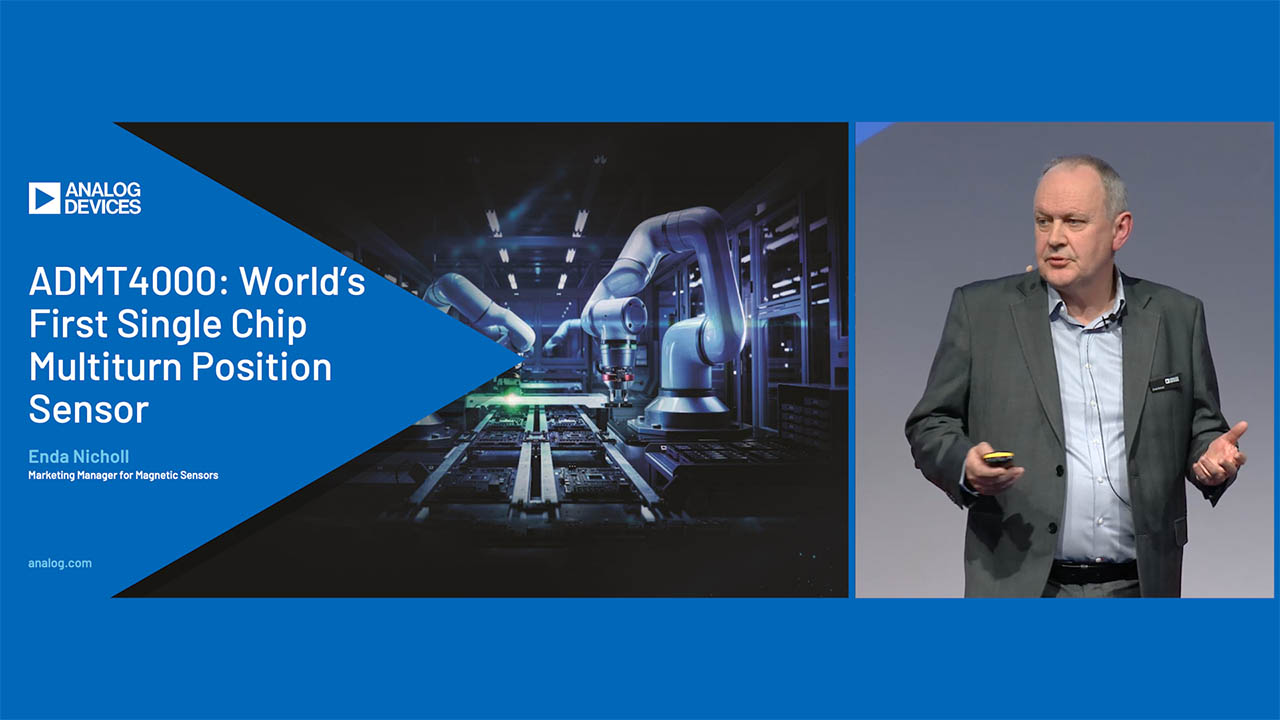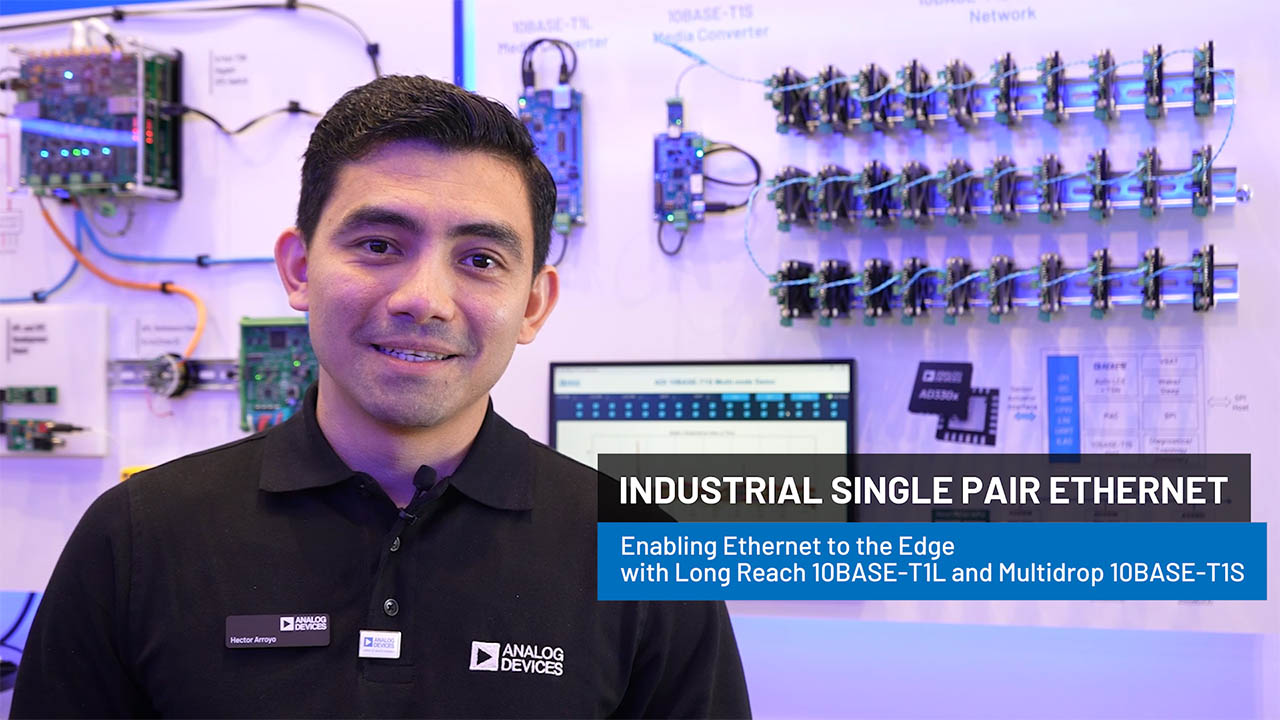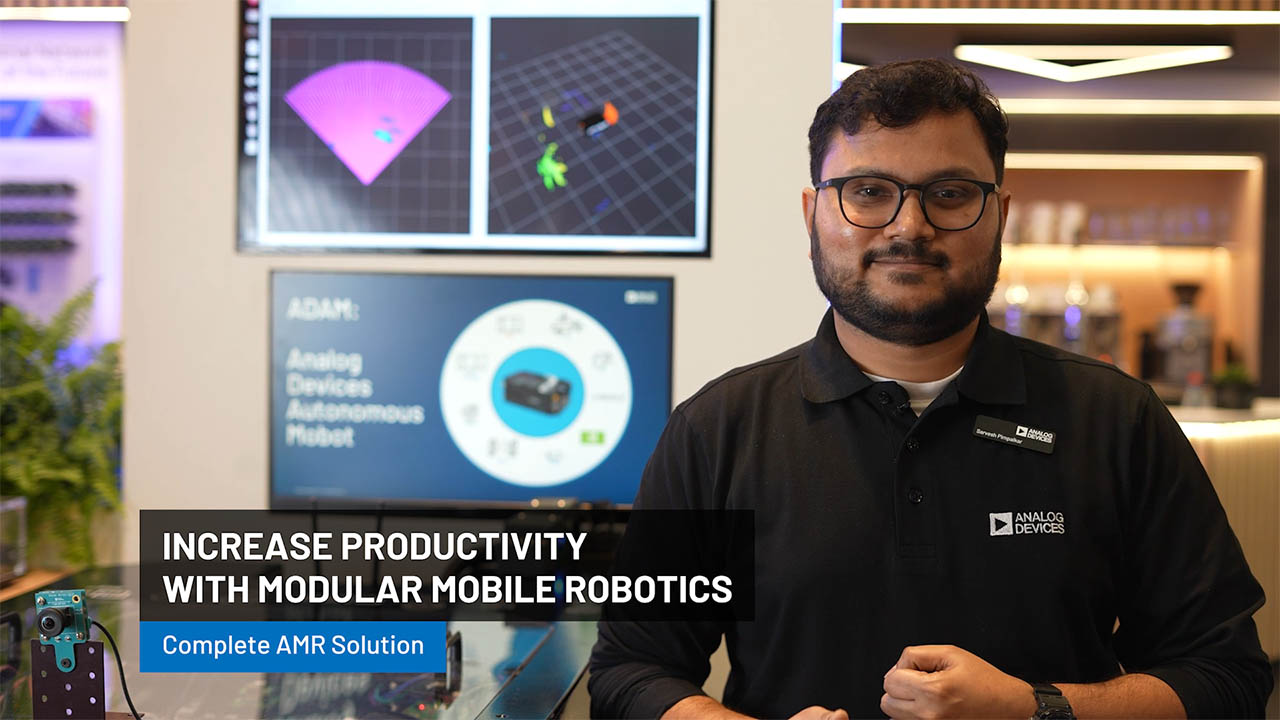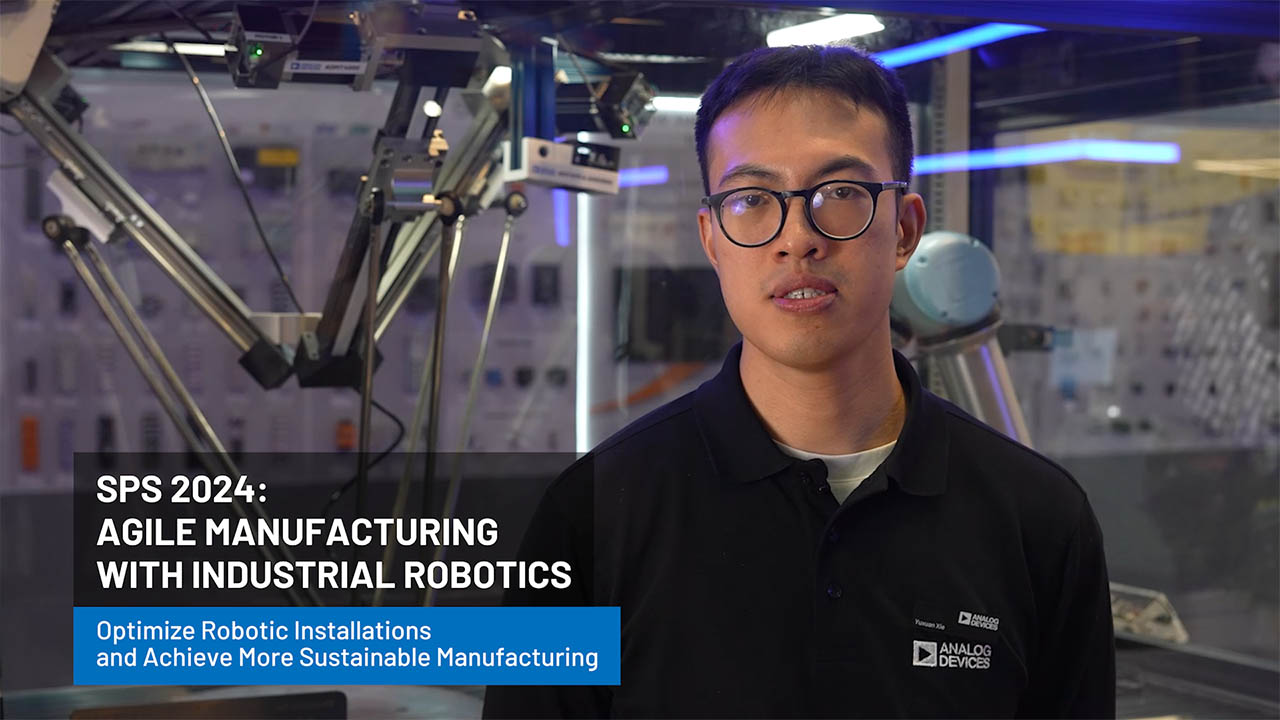熱解析でICの過渡応答を予測し、過熱を防止する
要約
このアーティクルでは、ICの熱挙動を予測する方法を紹介します。この情報は、自動車をはじめとする高温環境でPMIC (電源管理IC)を使用するとき、特に重要となります。熱挙動を把握後、チップ内の温度変化をシミュレーションする数式モデルを作成しました。その際、熱挙動を支配する物理法則を導入し、IC用に定義した熱物体モデルへの適用を評価しました。この解析結果に基づき、ICの過渡的な熱挙動をモデル化する受動的なRC等価回路も提案します。今回提案する解析手法の応用例として、LEDドライバ(MAX16828)のRC等価回路を作成しました。最後にこの手法の使用方法やメリットをまとめ、RCモデルの作成を短時間で行う方法を提案します。
このアーティクルはマキシムの「エンジニアリングジャーナルvol. 68」(PDF、5.1MB)にも掲載されています。
同様のアーティクルが「EDN」誌の2010年1月号にも掲載されています。
設計時には、一般に、ICの熱挙動を把握する必要があります。自動車用PMIC (電源管理IC)などは特にそうです。+125℃などの高温環境でICを動作させたとき、サーマルシャットダウン回路がトリガされないか、製品の安全動作温度範囲を超えないかなどが問題となるからです。この疑問に高い信頼性で答えるためには、しっかりした解析手法が必要です。つまり新しいICを定義する際には、ダイの過剰温度やサーマルシャットダウンを複雑な内部機能から予測する手法が必要になります。
DCモードで動作させる場合は、一般にθJA (熱抵抗)やθJC (ジャンクション・ケース間熱抵抗)などのデータシートパラメータからジャンクション温度を求めます1。しかし、DC以外のモード(PWM信号でパワーMOSFETを駆動してスイッチングレギュレータやLEDの制御を行う場合など)でジャンクション温度のピーク値を予測するためには、過渡的な熱データが必要となります。このデータは重要であるにもかかわらず、多くの場合、データシートで提供されていません。ある電力消費レベルで動作させたとき、どのくらいの時間で問題が発生するのかといった点も、簡単には答えが出せません。
このアーティクルでは、消費電力と環境温度からチップのジャンクション温度を時間の関数として求める数式を導出します。最初に解析のベースとなる物理法則を提出します。その後、発熱体が層状に折り重なる複雑な構造としてICシステムをとらえます。この熱物体モデルを理論的に解析し、過渡的な熱挙動を支配する数式を導出します。また、ICの熱特性を表す受動的なRC等価回路も提案します。最後に、この手法の有用性と精度を示すために、PWM調光機能を持つ高電圧、リニアHB LED (高輝度LED)ドライバのMAX16828について実験したデータを紹介します。
熱的動特性の法則
物体の温度と時間の関係は、2種類の基本法則から導出することができます。
ニュートンの冷却の法則:
ただし、
(式1)
TBは物体温度
TAは環境温度
kAは比例定数(> 0)
tは時間
顕熱エネルギー保存の法則:
ただし、
(式2)
Pは物体における発生熱量あるいは与えられる熱量(定数)
mは物体の質量
cは物体の比熱
上記法則を組み合わせると以下を得ます。
ICのデータシートには、一般に、θJAといったパッケージの熱データが記載されています。このデータを使うと、定常状態におけるパッケージの熱平衡を解析し、式3と一致しているかどうかを確認することができます。
(式3)
よって、定常状態において
式4を書き換えると次式が得られます。
P = mckA(TB - TA) (式4)
ただし、
(式5)
θBAは物体から環境の熱抵抗
TBはパッケージ内部の温度
TAは環境温度
よって、
(式6)
チップを熱システムとして定義する
システムを明確に定義すれば、熱挙動を正しく予測することが可能になります。チップをPCBにマウントした状態の断面図(図1)を見ると、ダイから周囲まで、少なくとも3種類の物質が存在することがわかります。ダイ自体、モールドのエポキシ、パッケージの3種類です。熱モデルにおける熱の流れは、支配的な発熱源がどこであるかにより、大きく2つのパターンに分けられます。1つは支配的な発熱源が外部にある場合で、外部熱源からダイへ熱が流れます。もう1つはダイが支配的な発熱源の場合で、ダイから周囲へ熱が流れます。以下にパターンごとの検討を加えます。

図1. PCBに実装したチップの断面図—ダイから周囲まで異なる物質が層になって
いることがわかります。
外部熱源からチップへ熱が流れる場合
図2に示すシステムを考えてみましょう。均一な物体がエネルギー(熱)を供給源から受け取り、周囲へ放出するシステムです。

図2. 外部の発熱源からチップ(物体1)に熱が流入し、それが周囲へ流出するケースの熱モデルです。
熱は、パッケージとモールド樹脂を通過して内部のダイに到達します。つまり、パッケージ外部に熱源がある場合におけるチップの熱過渡応答のモデルとなります。ダイは多量の金属を含むため、通常、パッケージよりも熱抵抗が大幅に小さくなります。そのため、ダイはほとんど遅れなしでパッケージ温度に追随します。言い換えれば、チップ全体が1つの物体であるかのような挙動を示します。この1物体システムは、式3で定義可能です。これをTBについて解くと、次式が得られます。
ただし、koは初期条件で決まる積分定数です。この式は、チップ外部に熱源があるという条件でチップの熱過渡応答を定義する際に便利です。
(式7)
実例を使い、このモデルを説明してみましょう。初期温度がTiのチップについて熱過渡応答を求めます。式7でt = 0、TB = Tiとすると、
よって、
(式8)
Ti = TAとなる特殊ケースの場合、
(式9)
式6を使って式9と式10を書き換えます。
(式10)
式11と式12は、パッケージ外部に発熱源があるとき、チップ(パッケージあるいはダイ)の温度を予測することができます。このような例は、発熱が大きい大電流MOSFETが近くにある場合などが考えられます。
(式11)
(式12)
kAとθJAがわかれば、温度の時間変化を計算することができます。Pが時間によって複雑に変化する場合も、時間ベースのシミュレーションという形で上式を用い、MATLAB®ソフトウェアでプログラムを書けば時間の関数として温度をプロットすることができます。
θJAはデータシートに値があります。ただし、セットアップ条件がJEDEC規格と異なる場合、データシートのθJA値を使うと計算結果が狂う可能性があります。JEDEC規格51-3には「大事なポイントとして、この試験基板で測定した値はあくまでパッケージ間の比較のためのものであり、これをそのまま用いて異なるシステムの性能を予測してはならない」と記載されています2。つまり、温度を適切に予想するためには、試作基板のθJAを測定するか、あるいは、以下のような形で直接評価しなければなりません。
ダイから周囲へ熱が流れる場合
図3に示すシステムを考えてみましょう。チップと同じような3物体システムがダイで熱を発生し、エポキシとパッケージを通じて周囲に熱を放散する場合です。物体1がダイ、物体2がエポキシ、物体3がチップパッケージです。

図3. 3物体モデルを図2のモデルと比べてみてください。ダイで生成した熱の流れが複雑になっていることがわかります。
このシステムについてθJAを求めるためには、3つの物体、それぞれに式を定義する必要があります。
物体1:
物体2:
(式13)
物体3:
(式14)
ただし、
(式15)
TB1、TB2、TB3はある瞬間における物体1、物体2、および物体3の温度です。
P12は、熱という形で物体1から物体2へ移動するエネルギーです。
P23は、熱という形で物体2から物体3へ移動するエネルギーです。
PGは、物体1で生成するエネルギー、あるいは物体1へ直接伝達されるエネルギーです。
ダイ(PG)で生成するエネルギーからダイが吸収するエネルギーを引きます。
エポキシが受け取るエネルギーからエポキシが吸収するエネルギーを引きます。
(式16)
式16と式17を式13、14、および15に代入します。
(式17)
式18、19、および20で表される3物体システムの解は複雑ですが、ラプラス変換で簡略化することができます。このとき、解は以下のようになります。
(式18)
(式19)
(式20)
ただし、
TB1 = T1em1t + T2em2t + T3em3t + TA + (θ12 + θ23 + θ3A)PG (式21)
θ12は、物体1から物体2への熱抵抗
θ23は、物体2から物体3への熱抵抗
θ3Aは、物体3から環境への熱抵抗
T1、T2、およびT3は積分定数
m1、m2、およびm3はk1、k2、およびk3の関数
式21を使うと、発熱するダイの温度を正確に見積もることができます。この式を使うためにはすべての積分定数とm1、m2、およびm3を知る必要がありますが、m1、m2、およびm3は複雑な関数であり、その解を求めるのは困難です。よって、微分方程式を解くツール、SPICEを使います。
RC回路モデルの熱過渡応答を表す微分方程式
次は、同じような微分方程式で表せる回路を提案し、この回路をシミュレーションすることによって温度を読み取ります。
式18、19、および20という微分方程式はシンプルなRC回路(図4)でモデル化し、ダイで生成するエネルギーを表すことができます。

図4. チップ内部で発熱する際の過渡的な熱挙動をモデル化したRC回路
図4では、コンデンサの初期電圧がダイ(C1)、エポキシ(C2)、パッケージ(C3)の初期温度を表します。VAは環境温度、コンデンサC1に流入する電流、ISはダイで生成するエネルギーを表します。このときコンデンサの電圧は、以下の微分方程式で表されます。
以下のように変数を読み替えると、この3つの式は式18、19、および20に対応します。
(式22)
(式23)
(式24)
VC1  TB1, VC2
TB1, VC2  TB2, VC3
TB2, VC3  TB3, lS
TB3, lS  PG
PG
コンデンサ電圧はそのままダイ、エポキシ、パッケージの温度を表します。このRC回路なら、どのSPICEパッケージでも簡単にシミュレーションを行うことができます。あるチップについてR1、R2、R3、C1、C2、およびC3さえ適切な値を求められれば、回路をシミュレーションし、コンデンサC1の電圧という形でダイ温度を直接読み取ることができます。
それでは、あるチップについて受動素子の値(R1、R2、R3、C1、C2、およびC3)を求めてみましょう。定常状態におけるダイの最終温度を測定すれば、前述の式5 (次の式25と同じもの)を用いてシステムの熱抵抗(θJA)が得られます。
ただし、
(式25)
TJは定常状態におけるダイのジャンクション温度
TAは環境温度
PGはダイから放散されるエネルギー
式25の放散エネルギー(PG)を使い、時間0からスタートし、さまざまな時間におけるダイ温度を測定すれば、チップの過渡的な温度変動を示すデータセットが得られます。測定データに対し、以下の制約条件で曲線のあてはめを行えば、R1、R2、R3、C1、C2、およびC3の値が求められます。
θJA = R1 + R2 + R3 (式26)
ダイ温度の測定
集積回路のダイ温度を計る実用的な方法は、いくつか存在します3。今回は、ESDダイオードの順方向降下電圧を用いてチップ温度を計る方法を採用します。簡便でありながら、誤差があまり大きくないのがこの方法の特長です。もちろん、一定レベル 以上の測定精度を得るためには、各チップに適したダイ温度測定手法を選ぶことが肝要です。有効なガイドラインを紹介しましょう3。
- 測定用のESDダイオードとして避けるべきなのは、寄生電気抵抗が大きいもの、電流が大きくダイオードの降下電圧を読み取る際に大きなオフセットを生じるものです。ICメーカに相談し、内部ボンドワイヤやメタルの電気抵抗を確認することをお勧めします。
- ESDダイオードの設置位置をチップの熱源近くや温度を測定したい部分にすることも大事です。こうすれば温度を正確に見積もり、精度の高い結果を得ることができます。
- FETのオン抵抗を温度インジケータに利用する場合は、計測ポイントで当該FETが完全にドロップアウトモードとなるように気をつけてください。
ダイオード電圧はほぼ一定の傾きで低下して行き、ずれは無視することができるレベルです。温度に対してプロットすると、図5のようになります。

図5. 定電流バイアスのダイオードの順方向電圧は温度によって変化します。
図5でTAは環境温度、VDAは環境温度におけるダイオード電圧です。つまり、グラフや傾きの元となる1点は既知です。この傾きは、温度制御機能を持つオーブンを用い、さまざまな温度でダイオード電圧を計るなどの方法で取得します。2mV/Kといった数字を使っても、幅広いダイオード電流でそこそこ正確な結果が得られます4。このような数字は他のチップに応用可能ですが、高い精度を確保したければ、ダイオードのバイアス電流における傾きを実測するべきです。いずれにせよ、温度はダイオード電圧から次式で算出できます。
ただし、
(式27)
Tはダイオード電圧がVDの場合の温度
sはグラフの傾き(s < 0)
これを式11と式12に代入すると、次式が得られます。
式18、19、および20に代入すると、次式が得られます。
VD = sθJAP + VDA + (VDi - sθJAP - VDA)e-kAt (式28) VD = VDA + sθJAP(1 - e-kAt) (式29)
ダイオードで測定した電圧トランジェントデータに対し、RC回路の定数を調整して適切に曲線のあてはめを行うためには、このほか、次式で表される電流ソースの大きさを設定する必要があります。
(式30)
(式31)
(式32)
s < 0ですから、電流ソースを逆向きとし、その大きさを|sPG|にすれば式33が成立します。
lS = sPG (式33)
実験によるRC回路定数の決定と検証
ここまでで導出した式とMAX16828/MAX16815などのリニアLEDドライバとを用いたRCシミュレーションモデルの応用例を紹介しましょう。MAX16828/MAX16815などのチップは少ない外付部品点数で最大40Vまで動作しますし、MAX16828ならLEDストリングに最大200mAの電流を供給することができます(図6)。MAX16815はMAX16828とピンコンパチブルでほぼ同等の機能を持ちますが、最大出力電流が200mAではなく100mAにおさえられています。

図6. HB LEDドライバMAX16815/MAX16828の標準動作回路
いずれのLEDドライバも、車幅灯、エクステリアリアコンビネーションライト、バックライト、インジケータといった自動車用途に最適です。大きなドロップアウト電圧と大電流という条件で内蔵MOSFETを動作させた場合、MAX16828から膨大な熱量が発生します(LEDストリングの順方向電圧が低い場合、MOSFETがこのような動作となります)。RSENSEの電圧は200mV ±3.5%に調整されるので、ここの抵抗でLED電流を設定できます。DIM入力も用意されているので幅広い範囲のPWM調光を行うことができるほか、耐圧が高く、IN端子に直接接続することが可能です。
ダイ温度を直接的に把握するため、DIM端子とIN端子を結ぶ内蔵ESDダイオードの順方向バイアス電圧を測定することにします。バイアス電流は約100µAとなっており、ダイオードの順方向電圧は2mV/Kで変化します(温度制御機能を持つオーブンでICを加熱すれば確認可能です)。これらの実験のセットアップを図7に示します。5Vソースと56kΩ抵抗で、ESDダイオードに対する順方向バイアス100µAを供給しています。ドライバは、LEDに200mAの出力電流を供給する設定とします。

図7. オンチップESDダイオードでダイ温度の過渡応答を測定するテスト装置。 *EPは、エクスポーズドパッドを表します。
この状態ではデバイスに大きな電流が流れており、その電流パスに測定対象のESDダイオードも入っています。そのため、ボンドワイヤおよび内部メタルの寄生電気抵抗による誤差が発生します。内部レイアウトやボンドワイヤ長から判断し、寄生電気抵抗はワーストケースで50mΩと見積もりました。電流が200mAのとき、ダイオードの測定結果に±10mV (max)の誤差が発生します。温度測定の精度は、±5℃以内となります。なお、ESDダイオードはオンチップのパワーMOSFETデバイスおよびサーマルシャットダウン回路のすぐ近くに実装されており、この領域の温度を測定するのにベストな位置にあると言えます。
システム定義1
ここでは、テスト装置を使って過渡的なサーマルダイオード電圧を捕捉し、式7と式21で提示したシステムの定義式で使う方法を紹介します。
(式11に代入する) kAとθJAを算出するために、チップをホットエアガンで加熱します。このときチップの電源は落としておきます。内部で発熱しないようにするためです。ホットエアガンで加熱するとパッケージとダイの温度が上昇します。ダイ温度の変化は、ダイオード電圧をスコープで測定して監視します(図8)。

図8. ダイオード電圧トランジェントのグラフ。外部ガンによる加熱(下降曲線)と外部ガン停止後の冷却(上昇曲線)、いずれも指数曲線となっています。
チップの温度があがると、式から予想されるとおり、ダイオード電圧は指数関数的に減少します。下降半ばでホットエアガンを切ると、パッケージとダイが冷え始めます。ダイオード電圧は上昇しますが、このときも指数関数的に変化します。
ホットエアガンからチップにどれだけの熱量が与えられているのか、正確にはわかりません。よって、不明な部分を避けられるように、式28を調整し、曲線の上昇(冷却)部分のみ(図8)にあてはめます。このあてはめが、kAについてベストな推測値を得られる方法です。冷却中、パッケージに流入する熱量はゼロ、つまりP = 0でパッケージは温度が低下するのみとなります。よって、式28は以下のように簡略化することができます。
VDAは既知であり(室温における最初の測定で643mV)、VDiもわかっています(t = 0における計測値)。あとは、上昇曲線上、複数の点を含むように式を調整すれば、kAを求めることができます。この結果、kA = -0.0175が得られました。測定値のグラフ(秒単位で表した時間に対し、mVで表したダイオード電圧をプロットしたもの)と、このkAを適用した式34のグラフを図9に示します。
VDB = VDA + (VDi - VDA)e-kAt (式34)

図9. 式34を、ダイオードによる電圧測定のデータ数個にあてはめると、ヒートガンで加熱後の冷却期間におけるチップ温度をダイオードで測定した結果をよく表すことができます。
図9を見れば明らかなように、kA = -0.0175のとき、式34は測定データとよく一致しています。導出した式が正しいことを検証するため、ここで求めたkAを用い、下降曲線と式28のあてはめを試みてみました。こちらも、良好な一致が得られました(図10)。つまり、「システム定義1」で検討したシステムについて、式34と実験データはよく一致したと言えます。

図10. 式28にあてはめを行うと、曲線の下降部分(加熱期間)の電圧測定の結果を表すことができます。
システム定義2
システム2の式30、31、および32のほうは検証が面倒です。ダイで熱を発生させる、ダイオード順方向電圧からダイ温度を測定する、測定した温度値に曲線をあてはめて、提案したRC回路のC1電圧値をシミュレーションするという手順が必要になります。この作業はMATLABでプログラムを書いて行います。
熱過渡応答を記録するとき、チップ全体の初期温度が既知であることが大事です。初期温度が既知ということは、RC回路のコンデンサの初期電圧も既知となるからです。さきほどと同じテスト装置(図7参照)を使い、電流をスタートさせてダイオード電圧をオシロスコープで記録します(図11)。

図11. オンにしたオンボードMOSFETから熱が発生されている状態でMAX16828内蔵ダイオードの信号から得た順方向電圧トランジェントです。
3通りの消費電力レベルについて過渡応答を記録し、そのデータに曲線をあてはめます。図12の回路は、消費電力が1.626Wのときのデータをもとに構成したものです。図13のグラフは、測定データとあてはめデータの比較です。同じように図14のグラフは、消費電力が2.02Wのときのデータと曲線の比較です。図15のグラフは、消費電力が1.223Wの場合です。

図12. 図のように部品の数値を用いた、ダイが発熱する際のチップの熱過渡応答をモデル化したRC回路の例。

図13. チップ加熱の測定値とあてはめ曲線の比較—ダイの消費電力が1.626Wの場合。

図14. チップ加熱の測定値とあてはめ曲線の比較—ダイの消費電力が2.02Wの場合。

図15. チップ加熱の測定値とあてはめ曲線の比較—ダイの消費電力が1.223Wの場合。
この実験結果から、測定結果と理論モデルがよく一致することがわかります。あるチップに合わせてRC回路のモデルを構築すれば、IC温度の過渡応答をシミュレーションすることができます。このモデルを似た大きさのチップに適用し、チップの熱特性を定義段階で確認することも可能です。ここからチップの動作限界がわかるわけです。これがわかれば、チップの動作モードを調整し、過熱を防ぐこともできます。
まとめ
このアーティクルでは、チップの熱挙動をRC回路という形でモデル化し、SPICEツールで簡単にシミュレーションできるようにする方法を紹介しました。以下の方法で、このモデルの精度を高めることができます。
- 電力消費レベルの上限と下限、中間の3個所についてデータを取得します。3レベルのデータを使ってRC回路のあてはめを行えば、実用的な電力消費レベルのほぼ全域に使えるモデルが完成します。
- 複数の環境温度でデータを集めるとモデルの精度が向上します。
リファレンス
- マキシムのアプリケーションノート3930 「Package Thermal Resistance Values (Theta JA and Theta JC) for Dallas Semiconductor Temperature Sensors」 (英文のみ)
- "Package Thermal Characteristics," Actel Corporation application note AC220, (February 2005).
- Rako, Paul, "Hot, cold, and broken: Thermal-design techniques," EDN online (3/29/2007).
- Pease, Bob, National Semiconductor, "The Best of Bob Pease. What's All This VBE Stuff, Anyhow?" (11/5/2008).
著者について
この記事に関して
製品
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}