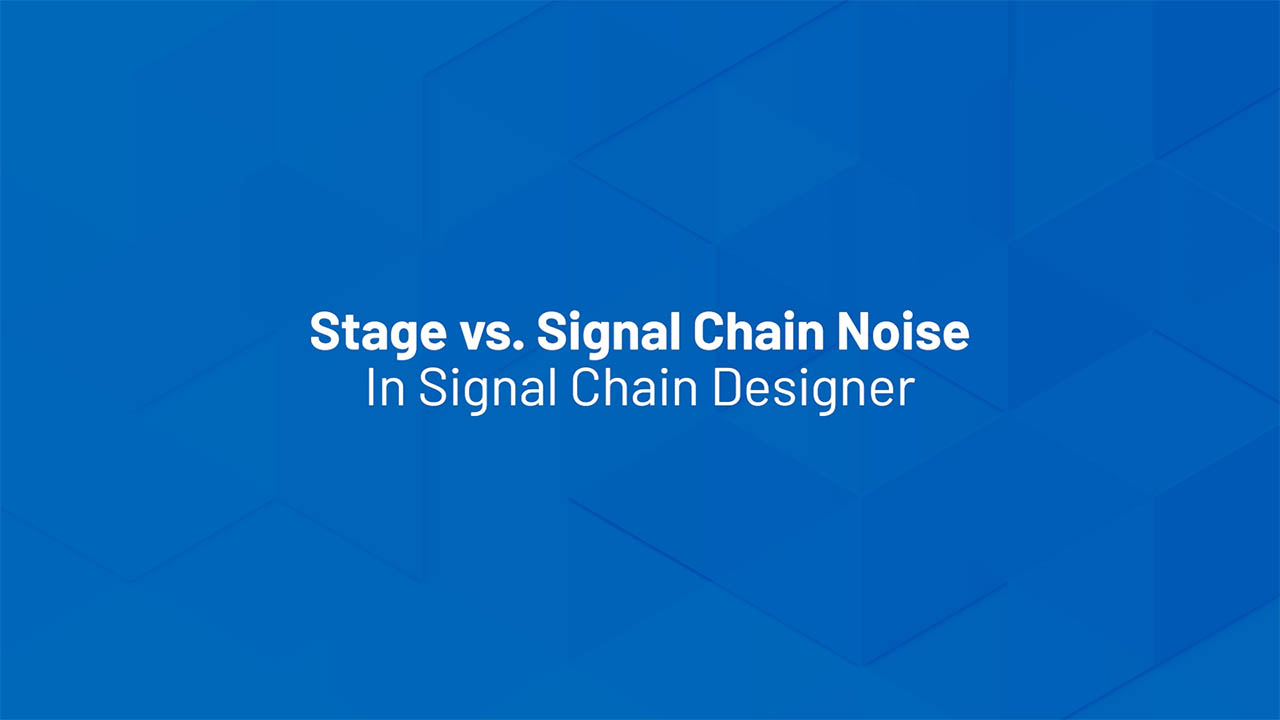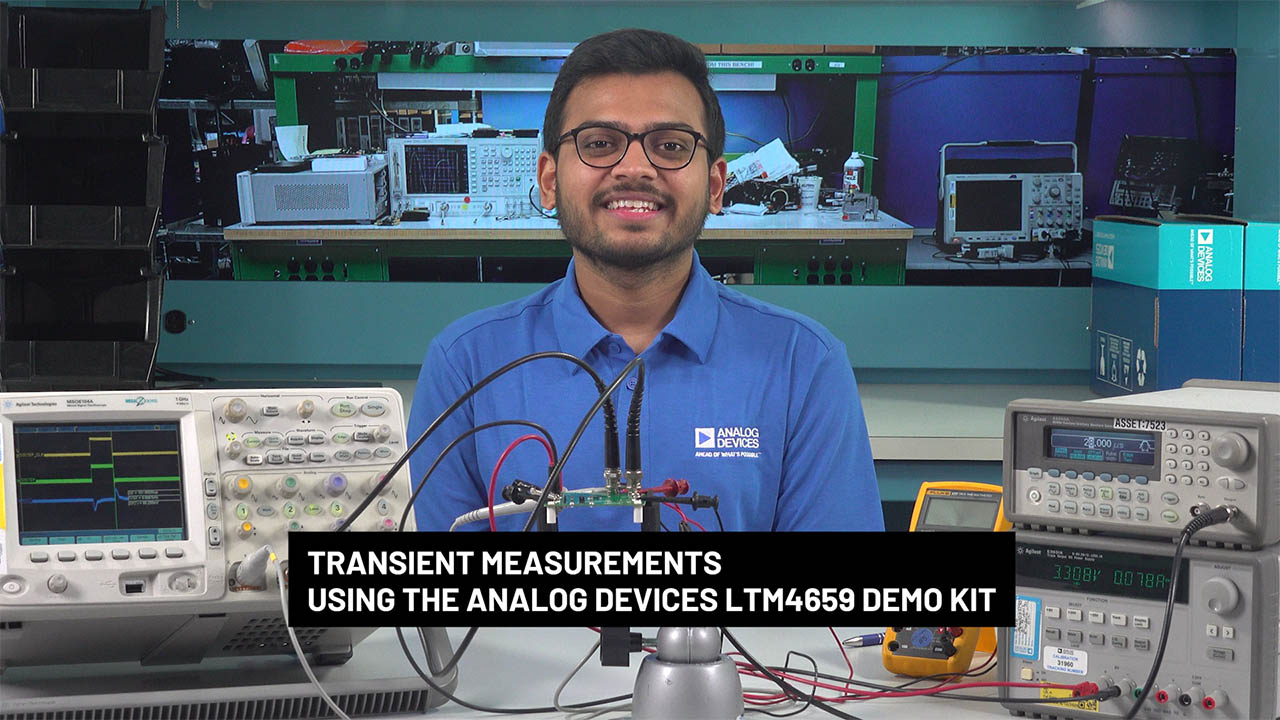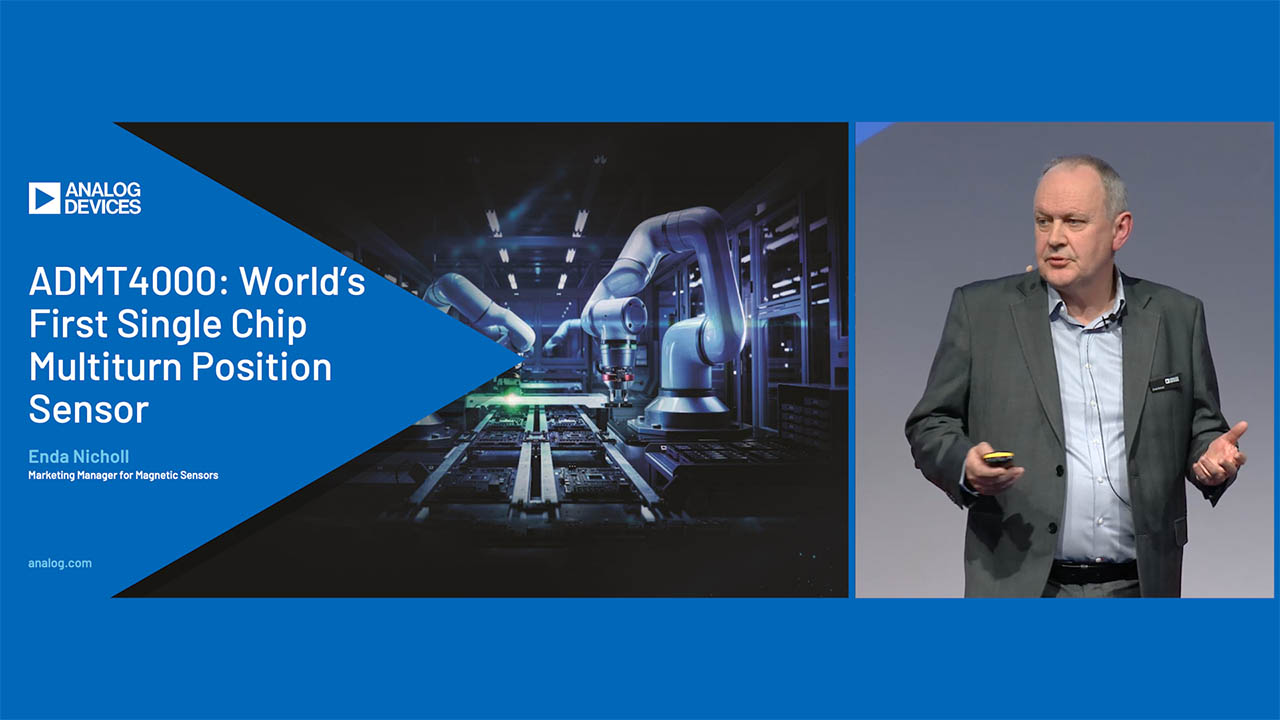要約
このアプリケーションノートでは、ヘテロダイントランシーバアプリケーションでの利得を測定するために、MAX2016 RFディテクタを自動テストシステムに実装する方法について説明しています。この記事では、「利得測定とキャリブレーション」、「オフセットのみを用いた利得測定」、および「オフセットと勾配のキャリブレーションを用いた利得測定」という3つの異なる手法の品質と測定精度を比較しています。
はじめに
デュアルRFパワーディテクタであるMAX2016は、単一のRFブロックや、より複雑なヘテロダイントランシーバ構成の利得測定を問題なく実行することができます。MAX2016の主な特長の1つは、オンチップのコンパレータ回路を内蔵していることで、この回路が、加えられた2つの電力レベルの差を計算します。利得 = POUTPUT - PINPUT = POUTA - POUTB = POUTDという単純な利得計算が、この回路を用いて容易に実現することができます。ただし、測定精度の要件を十分に満足することができるように配慮する必要があります。
アプリケーションによっては、回線の違いやカプラの損失、また製品間のばらつきに対処するため、1回限りのキャリブレーションが必要となる場合があります。以下のアプリケーションノートでは、RF利得の測定で採用したいくつかの基本的なキャリブレーション手法を概説しています。2つの一般的なアプリケーションを紹介しています。最初の例では、ヘテロダイントランシーバの利得測定を詳細に調べています。2番目の例では、工場の自動試験装置(ATE)のアプリケーションにおいて、キャリブレーション済みのMAX2016が、遅くて高価なパワーメータに取って代わる例を示しています。このATEの例では、キャリブレーションを行う場合と行わない場合によって得られる精度を参考のために比較しています。どちらの例も、測定セットアップのキャリブレーションを適切に行うことの重要性を示しています。
代表的なRFトランシーバの利得測定
MAX2016のパワーディテクタは、DC~2.5GHzの拡張周波数範囲を有しているため、単一の利得ブロック(図1a)、またはヘテロダインの受信/送信の全体構成(図1b)のいずれかの利得を測定するように、デバイスを容易に構成することができます。

図1a. 単一のRF利得ブロックの利得測定

図1b. ヘテロダインレシーバの利得測定
上記のどちらの構成においても、測定の不確実性によって利得測定の精度に影響を及ぼす可能性があります。絶対的な利得の測定値は、回線の違いやカプラの損失によって、さらにはMAX2016の製品間のばらつきによって不確実になるおそれがあります。MAX2016は、同一の内蔵ログディテクタを2つ搭載していますが、勾配とインターセプトポイントのわずかな違いが、差分出力で小さな誤差を生じる場合があります。
これらの変動を補償する簡単な方法は、工場出荷テスト時に勾配とインターセプトのキャリブレーションを1回だけ実行するというものです。図2は、ヘテロダインレシーバの場合の、このようなテストの構成を示しています。ここに示すように、既知の電力レベルを備えたRF信号をレシーバのフロントエンドに入力しています。次に、外部のパワーディテクタを使用して、ダウンコンバートされた信号の受信電力レベルを求めています。ダウンコンバートされた信号のサンプリングが容易でない場合、トランシーバのオンボード高速ADCを使用して受信電力レベルの近似値を求めることができます。ほとんどのレシーバは、ダイナミックレンジを高めるために、ある種の可変利得アンプ/可変電圧アンプ(VGA/VVA)を利用しているため、テストではこの構成の利得を変更し、次に測定を行って「利得」対「VOUTD応答」の勾配とインターセプトを求めることが可能です。応答の勾配とインターセプトはトランシーバの不揮発性メモリ(NVM)に格納されます。これによって、その後のVOUTD測定を絶対利得の値にマッピングすることが可能となります。さらに精度を向上するには、VOUTD対利得の値を多数備えた完全なマトリックスを作成してNVMに格納することができます。次に、補間アルゴリズムを実行すれば、測定したVOUTDのいずれの値についても利得を計算することができます。図3は、選択可能なこれら2つの手法を示しています。

図2. 工場での利得キャリブレーションのセットアップ―被試験レシーバ

図3. ヘテロダインレシーバの利得キャリブレーション方式
MAX2016の2つの内部ログディテクタは温度に対してともに適切にマッピングされているため、トランシーバの絶対利得を計算する際に温度オフセットを補償する必要がないことに留意してください。当然ですが、さらに精度を向上したい場合は、代表的な温度オフセットを測定してNVMに入力することができます。利得対VOUTDのアルゴリズムを使えば、現在の動作温度を測定して最大温度と最小温度の間を補間することによって、これらのオフセットを加えることができます。
ATEアプリケーションで2つのパワーメータの代わりにMAX2016を使用する方法
上述のように、被試験デバイス(DUT)の利得を測定する最も簡単な方法は、被試験デバイスの入力と出力の電力(dBm)をじかに測定し、出力電力から入力電力を差し引いて利得を得ることです。これまでは、広帯域の電力を極めて正確に測定するための唯一の方法は、パワーメータを使用することでした。ただし、パワーメータによる測定の速度は遅いため、テスト時間の短さが最重要となる生産環境ではパワーメータは使用することができませんでした。MAX2016のデュアルログディテクタの応答時間はかなり短いため(約100ns)、生産環境において迅速な利得測定が実現可能となりました。上の例で示したように、簡単な利得測定は、DUTの入力電力をMAX2016の1ポートに結合すると同時に、DUTの出力電力をMAX2016の第2のポートに結合することによって行うことができます。デバイスの利得に比例したDC電圧(VOUTD_MEAS)をVOUTDピンで取り込むことが可能です。利得は、以下の数式から計算することができます。
利得(dB) = (VOUTD_OFFSET - VOUTD_MEAS) / VOUTD_SLOPE (式1)
キャリブレーションは使用せず、MAX2016のデータシートからVOUTD_OFFSETとVOUTD_SLOPEの代表値を使用すると、この式は、利得(dB) = (1.0 - VOUTD_MEAS) / 0.025として簡素化することができます。詳細については、「MAX2016データシート」を参照してください。
利得を計算するために簡素化されたこの数式は有効ですが、利得測定の精度を向上するには、より徹底したキャリブレーションをお勧めします。複数のキャリブレーションステップを実行することで、さまざまな絶対精度を生み出すことでができます。以下では、VOUTD_OFFSETとVOUTD_SLOPEの正確な値を測定することを必要とするキャリブレーションの手法を説明しています。ユーザは、希望する精度のレベルに応じて、1つまたは両方のタイプのキャリブレーションを実行することを決定することができます。また、VOUTD_OFFSETのキャリブレーションのみを使用して得られる予想精度とVOUTD_OFFSETとVOUTD_SLOPEのキャリブレーションを使用して得られる予想精度を比較して概説しています(以下を参照)。
一般的なテストのセットアップ
より正確なVOUTD_OFFSETの値を得るためには、MAX2016の両方の入力ポートを同一の電力レベルで駆動する必要があります。VOUTDピン上のDCレベルは、VOUTD_OFFSETと同じです。MAX2016の入力ポートの1つに直列なキャリブレーション済みのアッテネータを使用してVOUTDの値を測定することによって、VOUTD_SLOPEを求めることができます。次に、所定のVOUTD_OFFSETとアッテネータの損失についてVOUTD_SLOPEを解くことができます。図4は、この特性測定のためのテストのセットアップを示しています。利得測定/キャリブレーションの手法の一部としてMAX2016EVキットを使用しました。

図4. 実験用の評価のセットアップ
この評価では、VOUTD_SLOPEのキャリブレーションを行うために固定電力のアッテネータを使用しました。ただし、得られた結果は利得を持つデバイスに等しくあてはまることに留意してください。選択した周波数と正確な減衰量はMAX3654 VGAのテスト要件に従って設定しました。MAX3654 VGAは、0dB~20dBの範囲にわたって利得を変動させるAGC付きのCATVトランスインピーダンスアンプです。さまざまな値の周波数とアッテネータを選択すれば、他のアプリケーションの要件を満たすことができます。
VOUTD_OFFSETとVOUTD_SLOPEのキャリブレーション
URV5 RFパワーメータを使用して、最初にさまざまなアッテネータの特性を測定しました。この測定は、真の減衰量を表せるよう、あらゆるケーブル損失を考慮に入れて、図4のポイントAで実施しました。
次に、各テスト周波数にてVOUTD_OFFSETとVOUTD_SLOPEの値を測定しました。
- VOUTD_OFFSETを測定するため、アッテネータをバイパスし、MAX2016の両ポートを同一の信号レベルで駆動しました。得られるVOUTD端のDC電圧が、VOUTD_OFFSETのキャリブレーション値になります。
- VOUTD_SLOPEを測定するため、キャリブレーション済みの10dBのアッテネータを挿入し、VOUTD端のDC電圧を再度測定しました(この値をVOUTD_MEASと呼びます)。以上から、VOUTD_SLOPEの値は、式1、所定のVOUTD_OFFSET、VOUTD_MEAS、およびアッテネータの既知の値10dBを使用して計算することができます。アッテネータの値は、式1で-10dBの利得として表されることに留意してください。10dBのアッテネータを選択した理由は、この減衰がMAX3654の利得範囲の中央値になるからです。表1は、VOUTD_OFFSETとVOUTD_SLOPEに対応する値を示しています。
| VOUTD_OFFSET (V) | VOUTD_SLOPE (mV/dB) | |
| At 50MHz | 1.044 | 27.8 |
| At 900MHz | 1.043 | 26.3 |
キャリブレーション精度の比較
各テスト周波数において6つの別個のアッテネータ(1、2、8、10、12、および20dB)についてVOUTDを測定しました。以下の3つのケースについて計算を行い、測定された減衰量と得られる精度を求めました。
- キャリブレーションなし
- オフセットのみのキャリブレーション
- オフセットと勾配のキャリブレーション
表2. データシートの代表値を使用したときのMAX2016の測定誤差 (VOUTD_OFFSET = 1.0V、VOUTD_SLOPE = 25mV/dB)
| VOUTD (V) | CALIBRATED ATTENUATION (dB) |
MEASURED ATTENUATION (dB) |
MEASUREMENT ERROR (dB) |
| 1.022 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 0.993 | 2.0 | 0.3 | -1.7 |
| 0.827 | 7.9 | 6.9 | -1.0 |
| 0.763 | 10.1 | 9.5 | -0.6 |
| 0.713 | 11.9 | 11.5 | -0.4 |
| 0.481 | 20.2 | 19.2 | -1.0 |
表3. オフセットのみのキャリブレーションを使用したときのMAX2016 50MHzの測定誤差(データシートに提示されている代表値VOUTD_SLOPE = 25mV)
| VOUTD (V) | CALIBRATED ATTENUATION (dB) |
MEASURED ATTENUATION (dB) |
MEASUREMENT ERROR (dB) |
| 1.022 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 0.993 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 0.827 | 7.9 | 8.7 | 0.8 |
| 0.763 | 10.1 | 11.2 | 1.1 |
| 0.713 | 12.0 | 13.2 | 1.2 |
| 0.481 | 20.2 | 22.5 | 2.3 |
表4. オフセットと勾配の両方のキャリブレーションを利用したときのMAX2016 50MHzの測定誤差
| VOUTD (V) | CALIBRATEDB ATTENUATION (dB) |
MEASURED ATTENUATION (dB) |
MEASUREMENT ERROR (dB) |
| 1.022 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
| 0.993 | 2.0 | 1.9 | -0.1 |
| 0.827 | 7.9 | 7.8 | -0.1 |
| 0.763 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
| 0.713 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
| 0.481 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
表5. オフセットのみのキャリブレーションを使用したときのMAX2016 900MHzの測定誤差 (データシートに提示されている代表値VOUTD_SLOPE = 25mV)
| VOUTD (V) | CALIBRATED ATTENUATION (dB) |
MEASURED ATTENUATION (dB) |
MEASUREMENT ERROR (dB) |
| 1.021 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 0.994 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 0.834 | 7.9 | 8.4 | 0.5 |
| 0.774 | 10.1 | 10.8 | 0.7 |
| 0.720 | 12.0 | 12.9 | 0.9 |
| 0.509 | 20.2 | 21.4 | 1.2 |
表6. オフセットと勾配の両方のキャリブレーションを利用したときのMAX2016 900MHzの測定誤差
| VOUTD (V) | CALIBRATED ATTENUATION (dB) |
MEASURED ATTENUATION (dB) |
MEASUREMENT ERROR (dB) |
| 1.021 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 0.994 | 2.0 | 1.9 | -0.1 |
| 0.834 | 7.9 | 8.0 | 0.1 |
| 0.774 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
| 0.720 | 12.0 | 12.1 | 0.1 |
| 0.509 | 20.2 | 20.3 | 0.1 |
生産テストでMAX2016をRFディテクタとして実装した場合の結論
上に示したデータからいくつかの考察を行うことができます。
第1に、キャリブレーションを用いない場合の誤差(表2)がかなり大きいということです。キャリブレーションされていないMAX2016を使用して、MAX3654 VGAのようなデバイスの利得を生産環境でテストする場合には、この大きな誤差をあらかじめ考慮に入れてVGAのテスト範囲を大きく広げる必要があります。この結果として、データシートに記載する利得の基準値の幅が広くなり、設計者にとって魅力の少ない製品になることでしょう。
第2に、0.9dBと2.0dBのアッテネータの誤差は、オフセットのみのキャリブレーションを用いることで容易に処理が可能です(表3および表5)。これは、DUTの利得の値を1つだけ測定するようなときに役立ちます。DUTの出力端における減衰量がDUTの標準想定利得に等しくなるようにDUTの基板が設計されていれば、パワーディテクタのポートへの入力レベルはほぼ等しくなります。利得の仕様の広がりが約2dB未満であると仮定すると、0.9dBと2.0dBのアッテネータの精度データが示すように、標準利得からの少量の偏差を正確に測定するのに必要となるのはオフセットのキャリブレーションだけであることがわかります。ただし、減衰値が増加すると、精度が急激に低下することになります。したがって、この手法は、利得の偏差が大きくなるケース(MAX3654のようなVGAでは一般的)では、問題が生じることになります。
表4および表6のデータでわかることは、広範囲にわたって利得を測定するときには、オフセットと勾配の両方のキャリブレーションを実行すると最良の結果が得られるということです。このキャリブレーションを実行するには、DUT基板のハードウェアがMAX2016の両方のパワーディテクタを同じレベルまで駆動可能であること、またキャリブレーション済みのアッテネータへの切り替えも可能でなければなりません。
図5は、MAX2016への入力に対してRFの切り替えが必要となる場合の1つの実装例を示しています。DUTの利得測定は、スイッチの位置をAにして実施されます。オフセットのキャリブレーションは、スイッチの位置をBにして実施されます。勾配のキャリブレーションは、スイッチの位置をCにして実施されます。勾配のキャリブレーションに使用するアッテネータの値は、DUTの利得仕様の代表値と同じです。勾配のキャリブレーションを実行したときの値(10dB)から遠く離れた減衰量についても誤差は最小限であることに留意してください。このデータは、利得対VOUTD曲線の非直線性が最小限であるという仮定を立証するものであり、また勾配キャリブレーションが1回だけ必要であることを示しています。

図5. MAX2016のRF入力キャリブレーションの切り替え
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}