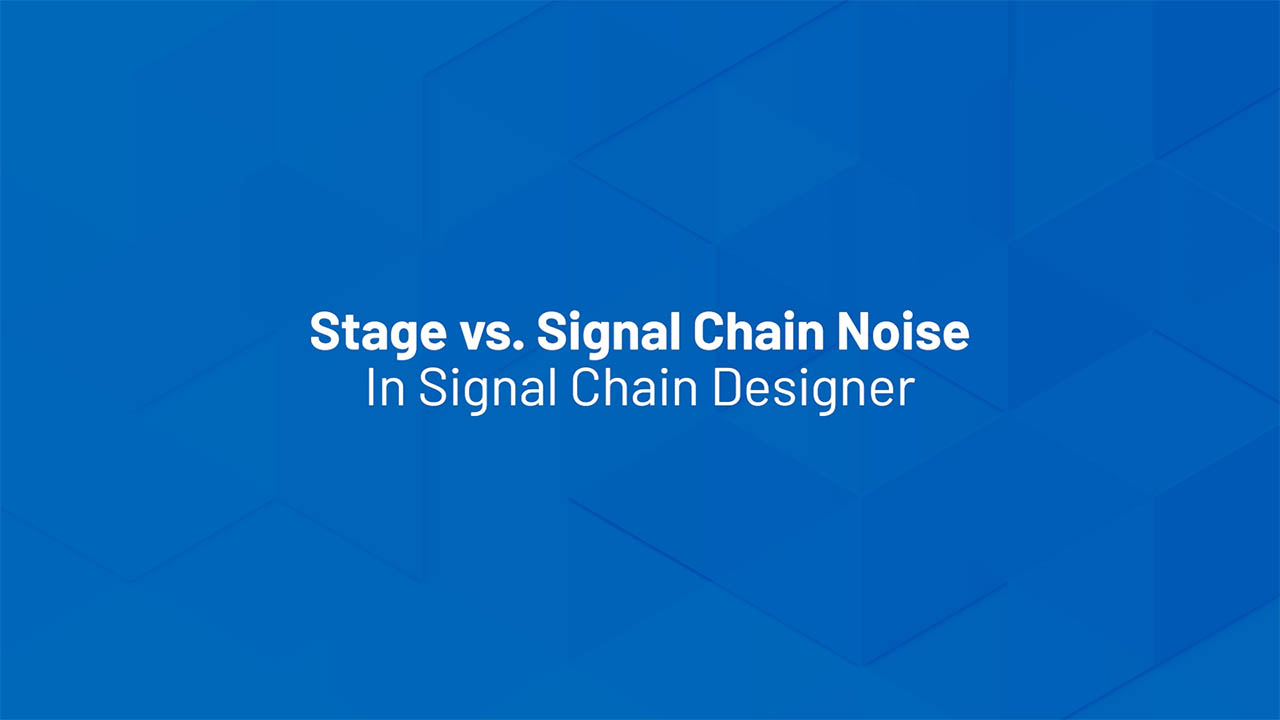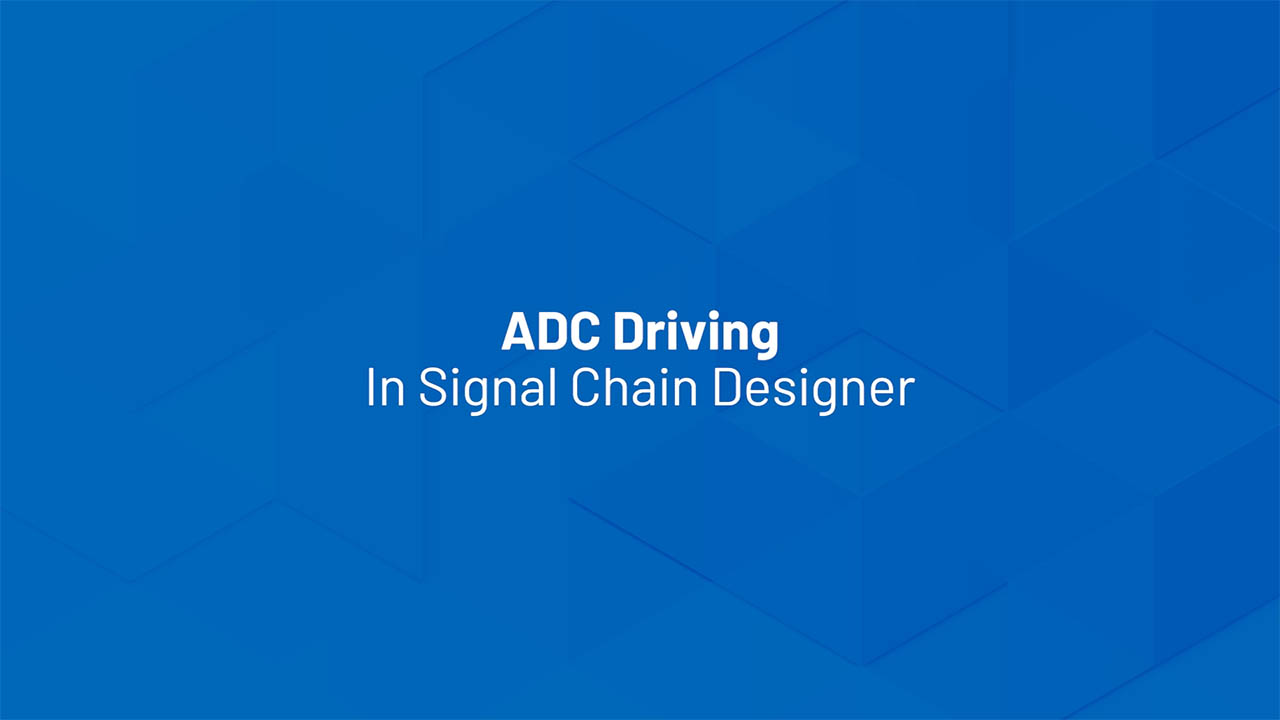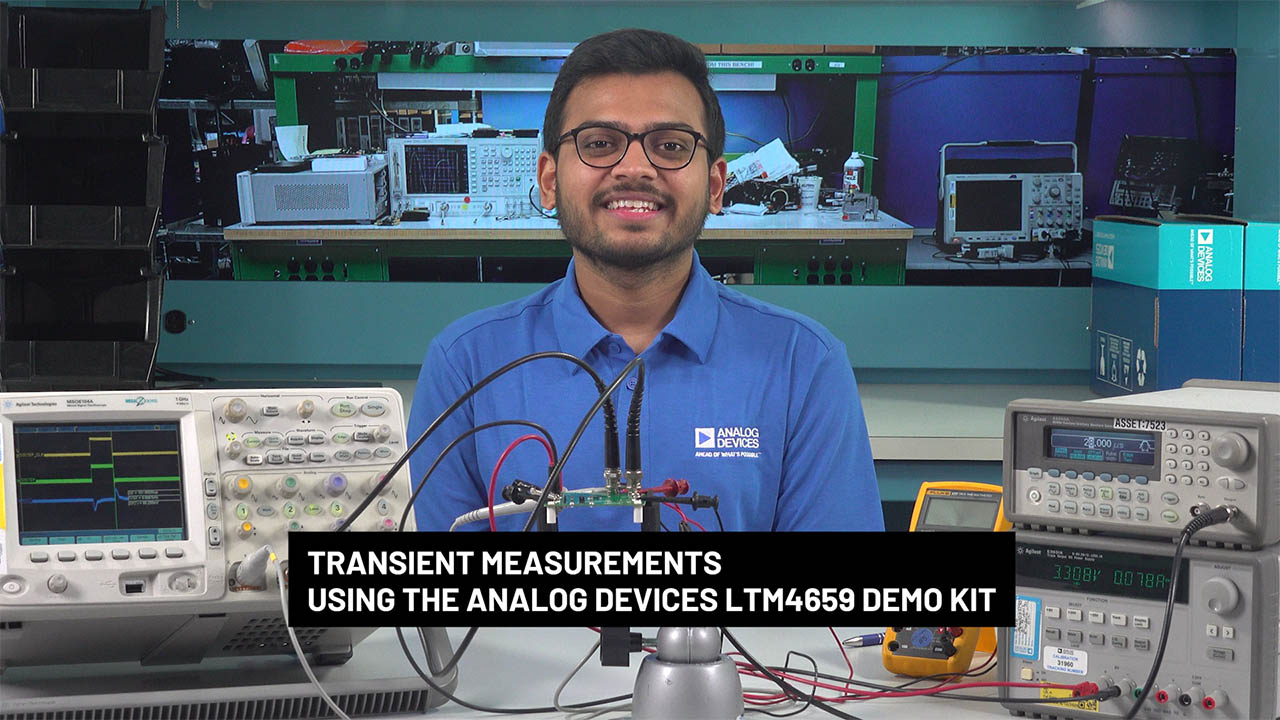TNJ-103:【回路設計WEBラボ 最終回】エンジニアの On The Job Training(OJT)と自らの駆け出しの頃からの思い出
TNJ-103:【回路設計WEBラボ 最終回】エンジニアの On The Job Training(OJT)と自らの駆け出しの頃からの思い出
著者
石井 聡
2024年09月09日
これまで長い間、ありがとうございました。
はじめに
大変、口惜しいと本人も思っておりますが、前回の技術ノートで「アナログ電子回路技術ノート」としての技術的話題のご提供は最後となります。 今回が回路設計WEBラボの最終回となり、最後ということで、これまで長い間とみに思ってきた、On The Job Training(OJT)について、自らの駆け出しの頃からの思い出を出だしに、つれづれなるままに綴ってみたいと思います。
2024年8月31日、秋田県大仙市「大曲花火大会」
8月20日あたりだったと思いますが、テレビで「大曲花火大会」が紹介されていました。開催は8月31日(土)。「俺、行ってみたい」と妻に話しをしたところ、彼女はホントに思いつきのダンナだなと思いつつも、ネットのサーチを開始してくれました。 宿泊施設に泊まらず、妻は新幹線もダメだろうと思い、弾丸バスツアーを選択。テレビ番組で紹介すぐにもかかわらず、サイトは停止せずにカード番号も入力でき、なんと!数日前にも関わらず、チケットを手配することができました。 千葉出発のツアーで、千葉駅前をAM 5:40分出発。大曲にPM 4:30到着(笑)、そのままPM 11:30出発で日帰りという恐ろしい弾丸バスツアーです。 この花火大会は、単なる観客を集めて花火を見せるという観覧型ではなく、「全国花火競技大会」…つまりコンペティションです(長い歴史があり、第96回)[1]。全国の花火師、それもトップの花火師が会して、まるで甲子園かオリンピックのように、1年間練り上げてきた花火を順番に(アナウンス後に)打ち上げていく、という花火大会です。 それはそれは、素晴らしいアートでした(図1、図2)。 ちなみに帰りのバス出発は、1時間遅延してAM 24:30。千葉駅到着がAM 10:30(笑)。弾丸バスツアー翌日はずっと寝ていました。
花火師も芸術家としての伝承が行われる
観覧していて思うわけです。「花火はアートだな」と。そして競技会であることから、1年間の鍛錬を一瞬で披露するんだなとも思うわけです。 花火も歴史は古いものでしょうが[2]、花火の多岐な光の軌跡を魅せる技術は相当なものです。綿々と先代から継承されてきた、花火玉を美しいアートとして披露できる製作・製造技術は、それこそ匠の技といえるでしょう。この継承は、座学による教育というより、現場での実践(製作作業と対話)による実務による学びによるものが大きいはずです。これこそ作業から学ぶ、On The Job Trainingに違いありません。


On The Job Training(OJT)に対する思い
新卒で製造メーカに入社した1986年ごろにOn The Job Training(OJT)という言葉を知ったのではないかと思います。以降、「OJT」として示していきましょう。 そのころ、OJTに対する思いは、「座学で教えることが面倒だろうし、単に作業負荷(量)に対応するためのマンパワーとして活用するための言い訳なのだろう」というものでした。 それが、結構経ってからだったと思いますが(これが頭の悪い証拠ですが…)、「OJTとは仕事を学ぶうえでの最高の教育手段だ」というところに至りました。教育という視点では、教育を受ける側の真剣度が最大レベルに達するもの、ということもいえるでしょう。
そのころから考えることは、OJTで適切に業務を学び、それだけでは業務に関わる分野全般において凹凸ができてしまいますので、そこを座学や自己学習で補うこと、それらにより業務関連分野全般に精通できる社会人ができるということです。 転職によるキャリアアップもOJTだといえるでしょう。
自らの電子回路技術OJT①…子供から学生まで
それは中学生のころでした。同級生のS君が、電波新聞社の月刊誌、「ラジオの製作」[3]を貸してくれました。彼のお兄さんが電子回路に興味があったようで(たしか工業高校に進学)、それを見ていて彼自身も興味を持ってきたようでした。 それを借りて読み始めた私は、それこそ鮮烈な印象をうけたものでした。内容もよく分からないまま、食い入るように読み、つづいて数冊を借り、以降、自身も購入するようになりました。
しかし内容は当時の私からすると高度すぎました。そして掲載されている記事をもとに何か電子工作をしてみようと思っても、部品を入手することができません。なかなか秋葉原に行くこともできませんし、お金もありません。ましては部品リストが何を示しているのか理解できないのです(笑)。いまでこそ、ネット通販による電子部品販売で、どこにいてもなんでも電子部品・機構部品、ICなどが入手できますが、当時は全く情報やルートがありません。
たまに秋葉原に部品を買いにいけば、高架下のラジオセンターの店員さんは「いくついるの?何百個?」といじめてきます(笑)。
それでも高校に入ったらアマチュア無線をやってみたい、と強く思ったものでした。
高校のころはアマチュア無線に没頭しすぎて…
中学校では運動部の部活と勉強に専念し、高校に入学しました。「高校に入ったら…」と我慢していた私は、さっそく無線部に入部しました。高校生の頃はそれこそ無線に没頭してしまいました。いや、没頭しすぎてしまいました。
アマチュア無線従事者の免許を取得し、最初は無線部の部室にある無線機を使って、無線局免許を取得してからは自宅も含めて、音声(Single Side Band = SSB)、モールス通信(Continuous Wave = CW)の通信を、アマチュア無線の定義である「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務」[4]という条文に倣って実践してきました(これはITUの「無線通信規則」の表記で、電波法では第五条第2項第二号に「個人的な興味によって無線通信を行うために開設する無線局をいう。」と規定されていますね[5])。
それはそれこそ、「OJT-自己訓練」そのものでした。ここで海外との通信で英語に興味を示し(これで今のお勤めがあるようなモノですが)、さらに電子回路に深く興味を示してきました。ラジオの製作を参考に製作してみた7MHzの受信機はオーディオの異常発振音が鳴るのみで全く動かず…。これが無線回路設計技術者になりたいと思うルーツとなりました。
文化祭では世間からすればマイナーな展示を行い、世間からすればメジャーな体育館で行われるバンド演奏は恐ろしくて足を踏み入れることができませんでした。オタクだったわけです。
大学のころは8ビット・パソコンに没頭しすぎて…
高校生活の後半は、「流石にこれはまずい」と思い、だいぶ学業に戻り、なんとか大学に入学しました。当時は共通一次という試験があり、入りたかった通信系、電子系の大学・学部には点数が足りなく挑戦できずで、なんとか二次試験逆転で電気工学科に滑り込みました。
大学では勉学もそこそこやりましたが、夢だったパソコンを、バイト代をはたいて富士通のFM-8 [6](CPUはMC6809)を購入。さらにオタク度がアップしてしまいました。
8ビット・マイコンの走りはNECのPC-8001 [7](CPUはZ80互換)でしたが、たしかMC6809の命令セット・アーキテクチャの美しさから、同CPUを用いたFM-8を購入したはずです。
購入後の途中からは、技術評論社の月刊誌、THE BASIC [8]を購入しつつ、その影響をうけてプロテクト外しに専念。最初はカセットの記録媒体(フロッピー・ディスクは高価で購入できず)で、そのゲーム・ソフトをIPL(Initial Program Loader)から逆アセンブル解析し、プロテクトを外すことに専念。以降になんとか5インチのフロッピー・ディスクを購入でき、今度はディスクのゲーム・ソフトのプロテクト外しに専念しました。ホントにオタクでした…。BIOS(Basic Input and Output System)の逆アセンブル解析もかなりやりました。
知り合い経由で紹介された設備会社にて、日立のS1 [9]というパソコンで業務ソフトをBASICで何本も書いたりしてお金を貯めました(そしてFM-8がFM-7 [10]にグレードアップ)。また立川にある開発メーカでZ-80のアセンブラ(当然デバッガ無し)開発もバイトで行い、これらでアセンブラ/BASICでのコーディングの力が相当つきました。これも「OJT-自己訓練」そのものでした。
アマチュア無線はこの期間からほぼお預けで、以降は今まで閉局状態です。それでもこのころ、数年かけてプロの無線技術士の資格を2級、1級と取得していきました。
大学4年になって、K先生の周波数精密測定の研究室に入りました。そこでは初めて「アラン分散」というもの、PLL技術、OPアンプ技術を学びました。周波数の精密測定ということで、位相ジッタが大切になるわけですが、当時はPLLの位相ノイズ(Sigle Side Band, SSBノイズ)の理論的仕組みが全く分からず、ただただOPアンプで作ったループ・フィルタで動作するPLLの周波数安定度を周波数カウンタを使って16ビットパソコンのPC-9801 [11]とGP-IBを使って計測していました。GP-IBもかなり突っ込んでやった覚えもあります。
さらにはPLL位相ノイズの仕組みが全く分からないのに、先生に「理論的に攻めたいです」などど、向こうみずなことを言っていたものでした。OPアンプに関する輪講などもありましたが、仮想ショートについて今一つうまく、正しく理解することができないという情けない状況でした。それでもその卒業研究も「OJT-自己訓練」そのものでした。
PLLの位相ノイズ・SSBノイズについては(以降に記述するように)、社会人になって無線通信機器を設計・開発するようになっても、忙しさにかまけて理論的仕組みは全く分からないままで、アナログ・デバイセズに入社後にOPアンプの知見も加わったうえでようやく理解できたものでした。
自らの電子回路技術OJT②…就職後に入った電子機器メーカでふたつの部署を渡り
入社した会社は、訳あって世間でメジャーではない会社に入社。最初は精密位置計測機を製造・販売する小さい部署に配属されました。
ホントは日本で超一流の無線機器を設計・製造するメーカに入社したかったのですが、訳あって諦めたのでした。その会社には会社見学にも行き、素晴らしい技術や製品を見て、「どうしても入りたい!」と思ったものでしたが…。そこに入社していたら全く違う人生になっていたものでしょう。
入社後7年間が一番成長したと思う
この部署では電子機器における先端に近い(大げさかな?)ことをやっており、16ビットのプロセッサMC68000 [12]を使った大規模なシステムや、Z-80ベースのシステムを開発していましたが、私はフォトダイオードの光電変換回路、アナログ回路を担当しました(いまでいうTransimpedance Amplifier; TIA)。
ここでもとりあえず動く回路は作ることができるものの、「光電変換回路の周波数特性はどう考える?」という質問には、「普通の電圧帰還アンプならわかるけど…」という感じで答えられるレベルではありませんでした。また「出力がなんだかノイズっぽいぞ…」と不安感を抱くこともありましたが、改善の手立てはありませんでした(分かりませんでした)。それでも書籍を読んでアナログ回路について一生懸命勉強しました。
論理回路も経験し、最初は(初めて)2000ゲート程度のゲートアレーを設計しましたが、そのときは同期回路という概念を知る由もなく、完全非同期でこのゲートアレーを設計しました。「論理設計はこんな混沌としたものではないはずだ」という思いから辿りついた本は、CQ出版の「ASICの論理回路設計法」[13]というもので、これで同期回路の概念を理解でき、大きく論理回路に開眼しました。またPAL(Programmable Array Logic)/FPGA(Field Programmable Gate Array)の走りの時期であったことから、LatticeのPAL 16V8をABEL(開発ツール)を使って、またXilinxのXC2000をXACT(同)を使って論理回路設計をしました。同期設計が理解できてしまえば、こんなに楽しいものはありませんでした。シミュレーションのとおり動くからです。IBM-PC互換機で走るXilinxの開発ツールXACTの合成時間が相当かかっていた覚えがあります。
余談ですがアナログ・デバイセズに入社後、広報の人と話しをしていたところ、その人は過去にXilinx Japanに在籍していたとのこと。XC2000やXACT、XCELL(Xilinxの無料技術誌)の話題でひと花をさかせました。
論理回路については、以降一回り大規模なゲートアレーを開発しMixed Signalシステムでの超低消費電力動作の測長機器を開発したり(これを経験論文として技術士試験を受験し合格)、VHDLを習得し、より大規模な回路設計に取り組むようになりました。
この部署には7年間いましたが、下手くそ英語レベルで通訳も結構やらされたりして、それこそ人生のうち一番エンジニアとして成長した、「OJT-自己訓練」そのものの日々でした。「社会人になったら無線機器の設計をしたい」と思ってはいたものの、本当にいろいろなことを経験しました。
無線機器の部門に異動
同じ社内に無線機器を設計する部門があり、8年目にそこに異動しました。ここは自らの求めていた「無線機器」とは毛色が異なった製品を設計・製造するところで、異動は気乗りしていませんでした。
送信電力的にもかなり小さい機器を開発していましたが、アマチュア無線をやっていたこともあり、放射電力が低いことから初めて担当した製品の設計で気を抜いてしまい、回り込みの高周波整流がマイコンIOポートの論理を変えてしまうという失敗をやらかして、市場回収という失態をしてしまいました(汗)。
それでも少しして、新規事業でマイクロ波の通信システムを開発するプロジェクトに参画し、本来求めていた「無線機器」にかなり近い製品を開発できるようになりました。Y大学のK先生の研究室に訪問するようになったのもこのころでした。
実際の通信システムの開発とK先生の指導で、それこそ日々は「OJT-自己訓練」そのものでした。結果、MHz帯からGHz対のいろいろな機器の開発を行いました。そこには高周波回路、マイコンの組み込みソフトウエア、論理回路、電波法とその申請作業などなど本当に多岐の業務がありました。
しかし忙しさにかまけ、PLLのSSBノイズの理論的仕組みは、大学の研究室からやってはいたものの、相変わらず全く分からないままでした。スペクトラム・アナライザの画面を見ながら「どうしてこのようなSSBノイズのスペクトルになるのか」とずっと不思議に思っていました。
またディスクリートでVCO(Voltage Controlled Oscillator)を作ったときに、用いるデバイスを、バイポーラ・トランジスタがまだ使える(ギリギリの)周波数であったにもかかわらず、低消費電流が必要なケースであったので、GaAs FETを使って組んだことがありました。「なんだかSSBノイズが大きいな」と思っていたのですが、GaAs FETの大きな1/fノイズがSSBノイズに影響を与えていることに気がつかず、そのままにしてしまった思い出などもあります(アナログは難しいです!)。
二束のわらじを3年間継続し
この部署に異動し結構経ってから、K先生からお誘いがあり、仕事にプラスして学業(研究)を行うという二束のわらじ状態が3年ほどつづき、なんとか学位を取得することができました(ホントに死ぬかと思いましたが)。ここで実践と理論とのギャップをかなり埋めることができたと思います。
帰宅後に自宅での研究を、翌朝近くまで眠さで訳わからなくなるまで行ったり、会社の仕事が終わってから、自家用車でアクアラインを西行して輪講に参加しトンボ返りするという日々、一回り以上離れた若い学生と議論できたこと、人生で一番濃い時代だったと思いますし(繰り返しますが、ホントに死ぬかと思いましたが)、今となれば楽しかった思い出です。
このころ憧れの「トランジスタ技術」誌に初めて記事を寄稿できるようになりました。
自らの電子回路技術OJT③…アナログ・デバイセズに転職し
アマチュア無線での海外通信をきっかけに高校生のころ興味を示した英語は、新卒入社以降も勉強を続け、そして二足のわらじ状態のときも結構実践したこともあり、外資メーカへの興味が膨らんでいました。アナログ・デバイセズも憧れの会社でした。
新卒で入社した会社は23年弱在籍していましたが、2009年1月1日からアナログ・デバイセズにお世話になることになりました。
アナログ・デバイセズでは、アナログを根幹から学ぶことができ、セミナーをアウトプットとして「OJT」の日々を送ってきました。
得られた、とくに大きな成果としては、① 上記に示したTIAの周波数特性とノイズ特性、② OPアンプやSW電源の帰還回路の安定性(位相余裕)、③ 上記に示したPLLの位相ノイズ(SSBノイズ)と安定性(これは帰還回路としてOPアンプなどと全く同じということも)、④ ADCシステムをシグナル・チェーンとして考えたときのNF(Noise Figure)の考え方、⑤ フィルタの伝達関数と2次アクティブ・フィルタ設計との関係、⑥ OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)通信方式の概念、このあたりといえるでしょう。
WEBラボの記事執筆もOJTそのものだった
このWEBラボの記事執筆も、OJT…自己訓練そのものだったといえるでしょう。記事のネタを考えるときは、自分が興味を示していたこと、これまで「どうなっているのだろう」と疑問をもっていたこと、深く追求してこなかったこと、これらを取り上げていきました。
そしてそれを答えが無いまま執筆をスタートしていきました。つまり執筆の最初は、答えがないまま・分からないままなのです。そして筆を進めるごとに、MS Wordの数式エディタで数式を書き進めるごとに、「ああ、なるほど、こういうことなのね!」と気づき、理解し、さらに次の記事につながっていく、というプロセスだったのでした。
これまでずらりと102の記事が並んだ結果になりましたが、それぞれ執筆してきたときのことを考えると、思い出深い記事ばかりです。40歳代、50歳代とWEBラボを執筆してきましたが、それこそ「OJT-自己訓練」そのものの日々だったといえるでしょう。
まとめ
人生全てが学びだと思う、今日この頃。OJTというキーワードを基に、この最終回の記事を組み立ててみました。それこそ齢によりインプット/アプトプットも減ってきているなと最近は思いますが、これからも長く安定して自己訓練/自己鍛錬ができればいいなと思っています。
長い間、本当にありがとうございました。またどこかでお会いできればと思います。
E N D
参考文献
[1] 大曲の花火 第96回全国花火競技大会公式ホームページ, https://www.oomagari-hanabi.com/
[2] 花火(「花火の歴史」の部分), Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/花火
[3] ラジオの製作, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/ラジオの製作
[4] アマチュア無線, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/アマチュア無線
[5] e-gov法令検索, 電波法, https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
[6] FM8, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/FM-8
[7] PC-8000シリーズ, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/PC-8000シリーズ
[8] The BASIC, Oh! FM-7, https://fm-7.com/museum/products/f53xxp8u/
[9] 最強の8ビットパソコン”の称号を得た機種の1つ「日立 S1」, AKIBA PC Hotline!, https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/retrohard/1266241.html
[10] FM7, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/FM-7
[11] PC-9801シリーズ, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/PC-9801シリーズ
[12] MC68000, Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/MC68000
[13] 小林芳直, ASICの論理回路設計法, CQ出版社
著者について
1963年千葉県生まれ。1985年第1級無線技術士合格。1986年東京農工大学電気工学科卒業、同年電子機器メーカ入社、長く電子回路設計業務に従事。1994年技術士(電気・電子部門)合格。2002年横浜国立大学大学院博士課程後期(電子情報工学専攻・社会人特別選抜)修了。博士(工学)。2009年アナログ・デバイセズ株式会社入社、現在に至る。2018年中小企業診断士登録。
デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...
デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...
この記事に関して
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}