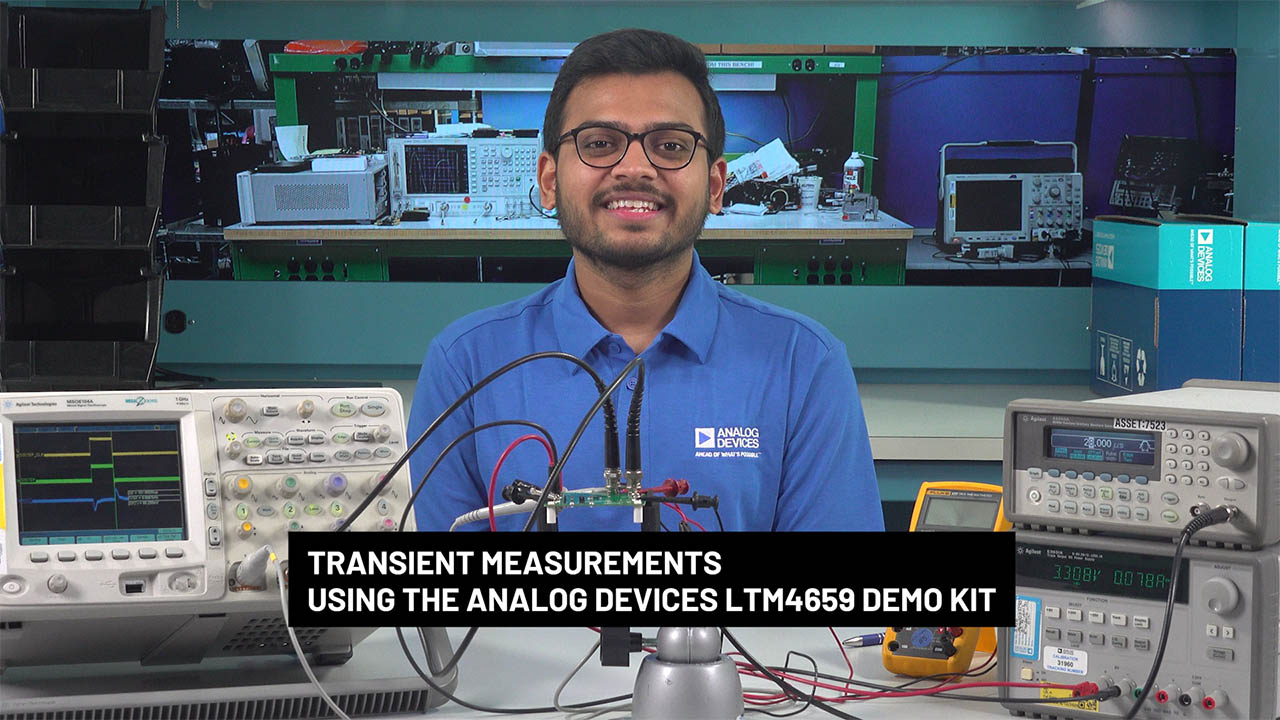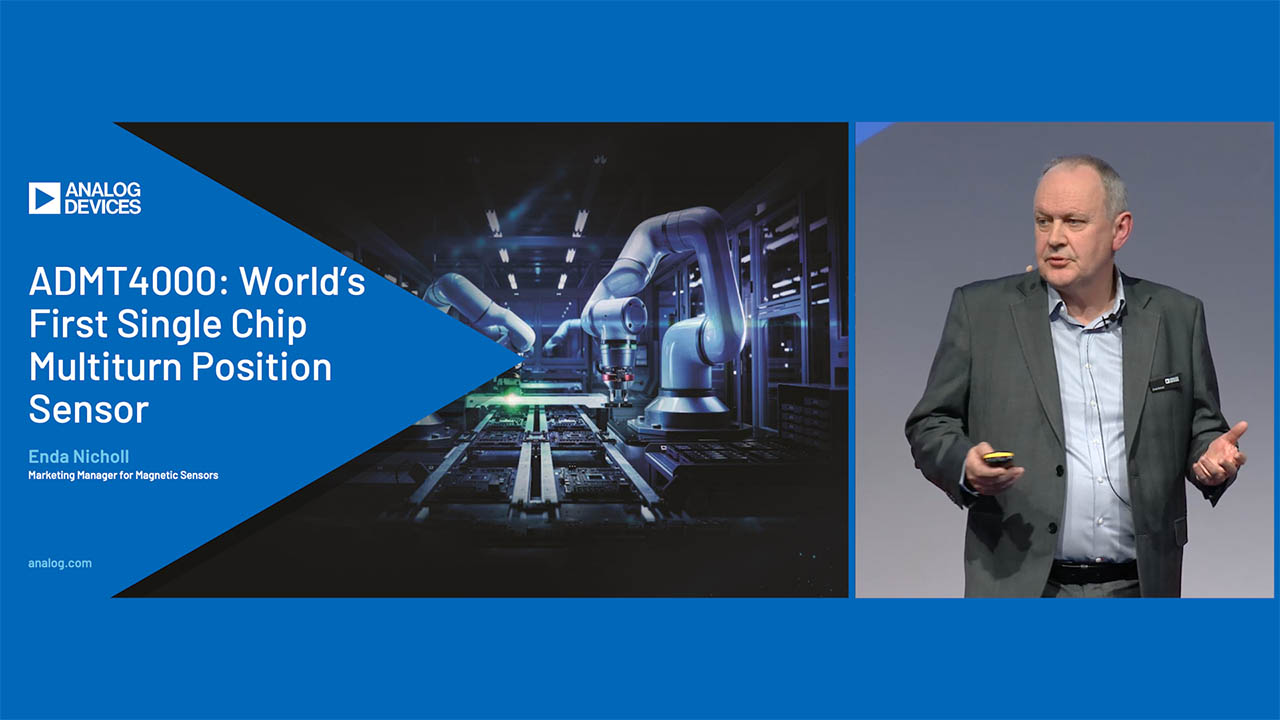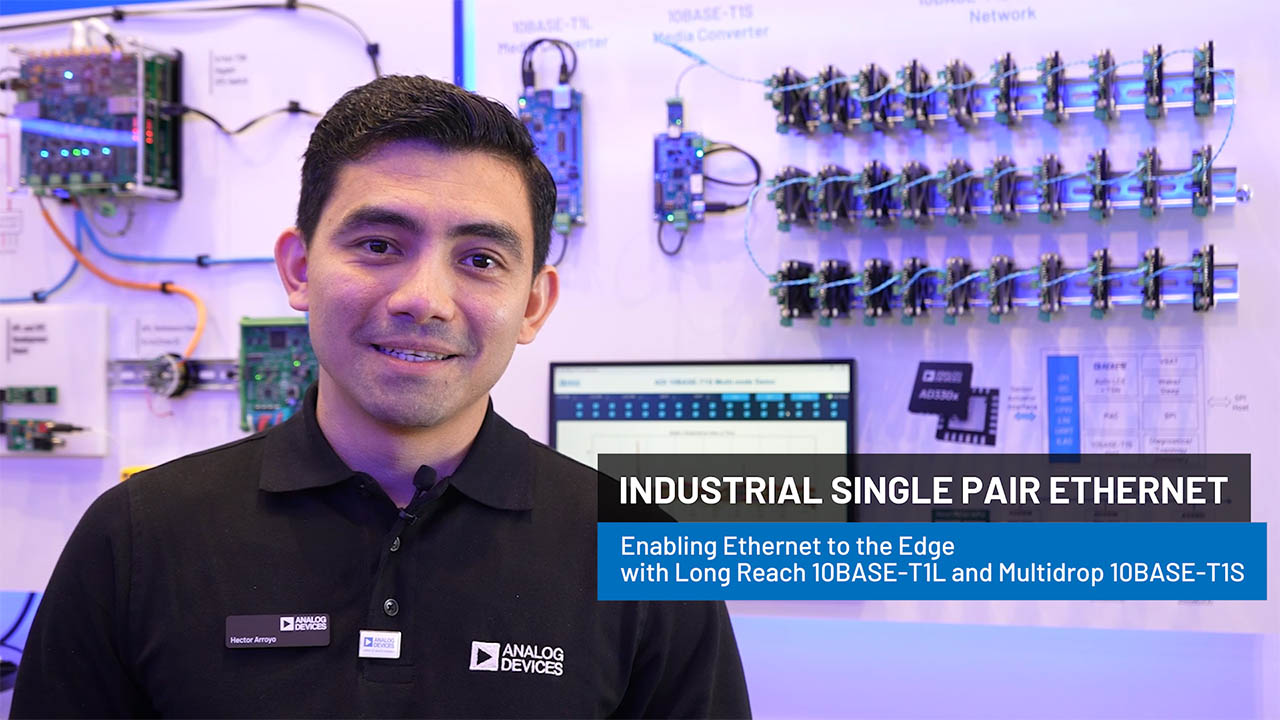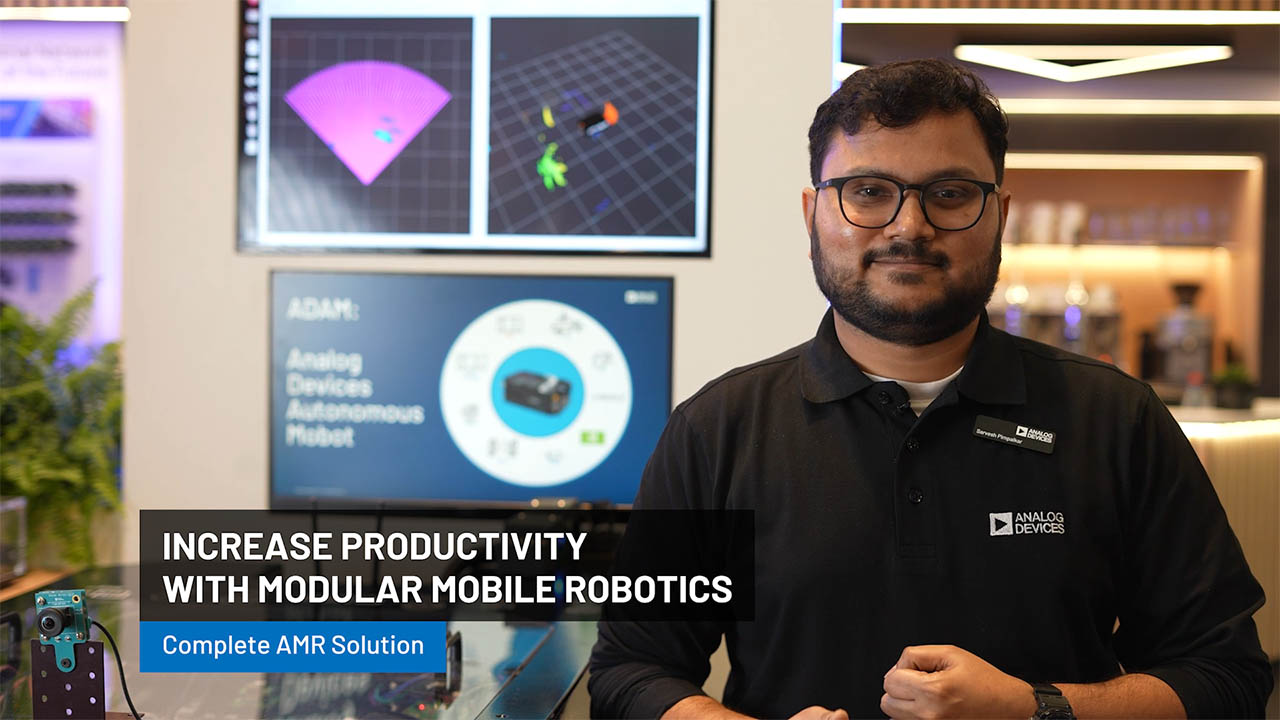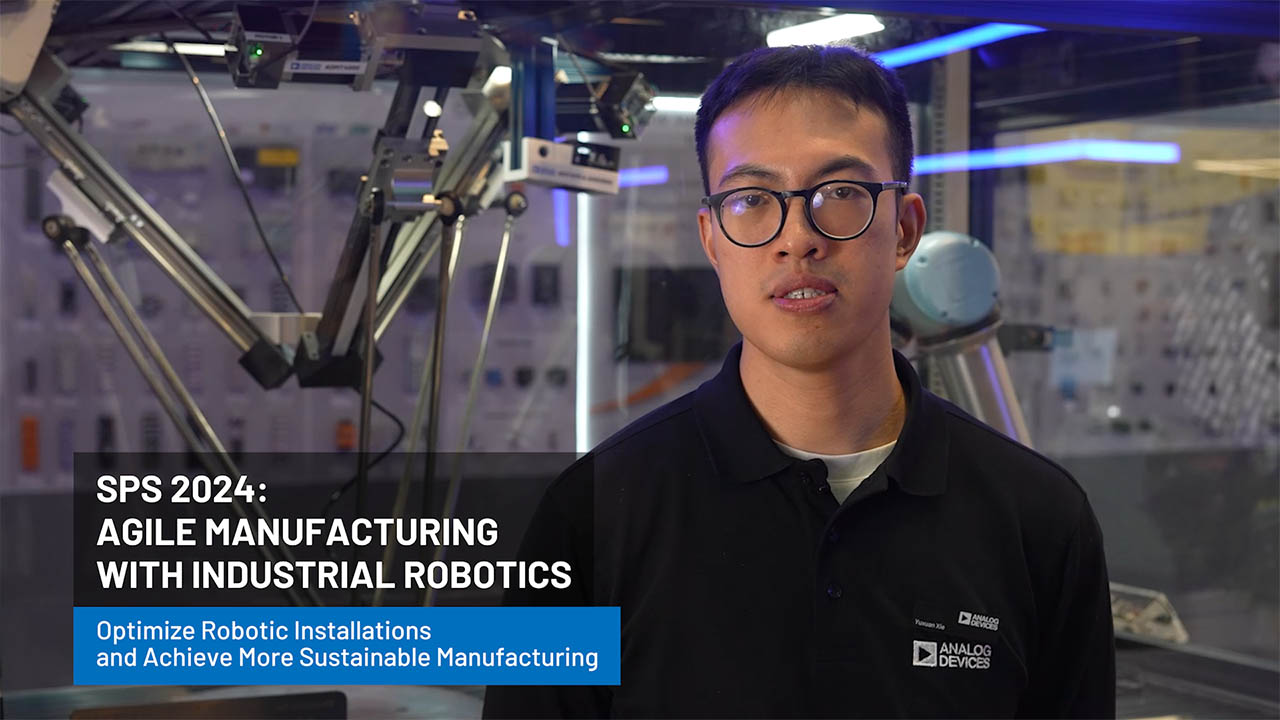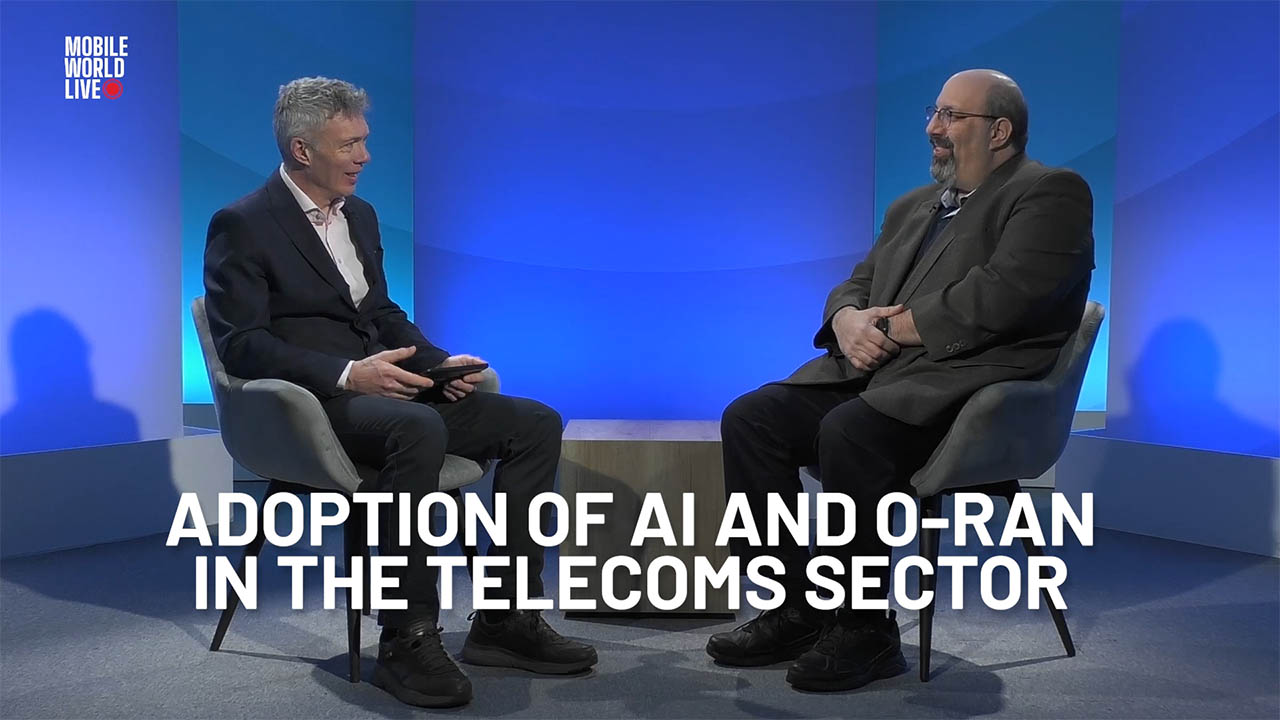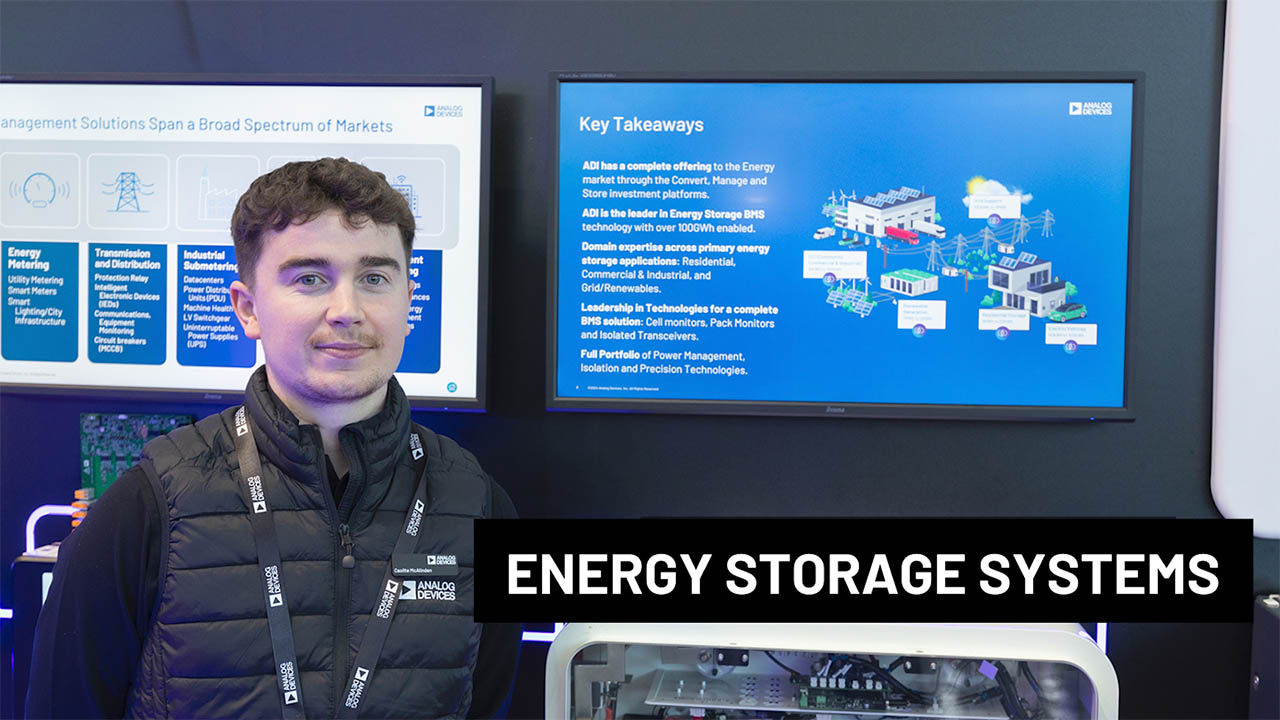TNJ-026:起動しないパソコンから故障した電解コンデンサを取り出して電気的に解剖してみる
2017年1月10日公開
はじめに
某年1月2日、お正月の寒い朝、私個人のPC(Personal Compuer)の電源を入れたら起動しません。「昨日も遅くまで使っていたのに」。ほうっておいて5分後くらいに電源再投入したら、なんとか起動。「ありゃ、これはいよいよ…」。そうなのでした、PCの電解コンデンサの故障なのでした。ネットで調べると、この故障はよくあり、(詳しい人は)電解コンデンサを交換しているようです。
予備で同じPCを準備してあり、HDD(Hard Disk Drive)を入れ替えて事なきをえました。しかし私も「電気屋のはしくれ」。自分で修理をしてみようと思いたち、また無駄な時間を消費してしまうことになるわけでした。
修理しても、もう一回起動不良が起きたら、諦めて買い直すしかないのかもしれません。みなさんも重要なデータのバックアップはお忘れなく!
さっそくPCのコンデンサを交換してみよう!
ということで、このPCのコンデンサを交換してみます。しかし数が40個くらいあり、先行きがどうなるかと不安がよぎります。参考用として、ヤフオクで同じMB(Mother Board)を探し出しました。落札したものは、他の臓物は摘出され、ケースとMBのみで2500円のジャンク品です。図1は、並んだ6.3V 1500μFの8個の電解コンデンサが底抜けしたようすです。図2は、同じPCの別のところのようすです。上側が盛り上がっています。下も抜けています。図3は、MB上に載っていたアナログ・デバイセズのIntegrated SoundMAX CODEC AD1981Bでした!
コンデンサの取り外しは意外と大変
コンデンサの取り外しは意外と大変です。MBは多層基板が使われているため、常温では内層に熱が逃げてしまうので、半田ごてだけだと難しいと思います。ホットプレートを150℃くらいにして、まずは時間をかけて基板(内層)を加熱し、それから半田ごて2本で取り外す必要があります。助手に裏側から引っ張ってもらう必要もあります。
なんとか数個無事にはずせました。ネットで調べると、
http://www.noseseiki.com/drhanda/condensa.html
ここで超良心的な価格でコンデンサの交換をやってくれているのを見つけました。この会社、電子業界でも有名なところですよね。
ご存知な方もいらっしゃる…
この図1、2の写真を見た方から「これは2001年頃から大騒ぎになった台湾製PCと思います」というコメントをいただきました。また「色からすると日本製の電解コンデンサのようですね」というするどいご指摘でした。おっしゃるとおりで…。そういう私は外国製のコンデンサとばかり思っており、このコメントをもとに再確認したところ、国産メーカの「マーク」を見つけられました。
PCだと、コンデンサは結構パンクするものが多いようです。Wikipediaを見ても「不良電解コンデンサ問題」というページもあります。一方でそのページにも書かれていますが、日本メーカはこれらの問題を克服し、近年は性能向上しているということのようです。
なお私のPC自体は日本のメーカのものです。2003年発売開始で、私は中古で2007年に入手しました。設計・製造が台湾なのかは分かりません。
コンデンサの取り外しには助手が必要
都合、3台のPCを修理することとなりました(汗)。
① 1月2日に故障したPC
② ヤフオクで落札した他の臓物は摘出されたPC
③ 予備で準備してあった同型式のPC
③は通常使用に必要ですので、とりあえずそのまま運用を継続させておりました。
春の三連休に、故障した①の1台とヤフオクでゲットした②の1台、つまり2枚のMBのコンデンサを「天の声(家庭の運行が鶴の一声で決まってしまうという意味。笑)」に助手をやってもらい、殆ど終わりにしました。
最初は息が合わなかったり、慣れなかったりで、うまく取り外せませんでしたが、慣れてくると面白いように取り外せます。「どう、おもしろくなってきた?」の質問に「全然…」 ^_^;
取り外したコンデンサや基板のようすを眺めてみる
図4は取り外したコンデンサです。図5はPCB(Print Circuit Board)上のようすですが、ミニタワーのためMB(PCB)は縦付けです。図5のようにプロセッサの上に問題の電源回路があり、プロセッサの熱が上側に上がってきて、この電源回路(コンデンサ)が周囲温度から上昇してしまうという残念な構造です。
アナログ回路でもそうですが、過大な熱が加わらないように、電子回路はレイアウト設計する必要がありますね(高精度回路などが特に)。
MB上のコンデンサは、高容量、低耐圧、おかしそうというORを取って1枚あたり33個交換しました。都合3台分を交換する必要があるので[またハイスペックな超Low ESR(Equivalent Series Resistance)コンデンサを購入したので]、発注金額はなんだかんだで1万円近くになってしまいました。まあコンデンサだけではなかったのですが。
取り外したコンデンサを解剖してみる
ということで三連休も終わりとなりました。PCオタクの記事ならこれで「めでたしめでたし」で終わりですが、私も「電気屋のはしくれ」。
容量抜けを時定数で測定してみる
さて、パンクしたコンデンサの特性を測定してみました。10Vの電源をステップ源として、1500μF 6.3Vの当該コンデンサと1kΩの抵抗をつかって、63%(つまり6.3V)まで上昇する時間(時定数)で容量抜けを確認してみます。
図6がオシロでの応答波形ですが、なんと10Vを加えても、ピーク電圧が4.28Vまでしかいきません。1kΩの抵抗に流れる電流を計算してみると、

となり、5mA以上のリークがあるようです。
また4.28Vの63%は2.7Vであり、その電圧までの上昇時間は272ms。つまり272μF相当の容量に、リークが5mA以上という特性になっています。
周波数特性も測定してみる
周波数特性も測定してみました。ネットワーク・アナライザの50Ω出入力のパスに並列にコンデンサを図7のように接続します。容量が大きいので、インダクタンスも小さくする必要もあると思い、こんなふうにしてみました。DCバイアスはなしです。
測定結果を図8に示します。REF LEVELが一番上で0dB、5dB/divです。やはりなんだか変な感じです。
注文してあるハイスペックな超Low ESRコンデンサが入手できたら、同じように周波数特性も測定してみたいと思います。しかし余計な仕事を作ってしまったなと改めて思いました…。いや、これはこれでシュミのうちでしょうか?(笑)
ハイスペックな超Low ESRが届いた
図6のテストではステップ電圧の10Vを入れてみましたが、あらためて考えてみると耐圧6.3Vでしたね。今更気がつきました。まあ1kΩでダンプさせているので、もし新品でも(ましてや短時間のテストだし)劣化は大丈夫ではないのかな、とか思いました。
さて某月某日に、千石電商にweb注文してあった超Low ESRコンデンサが多数到着しました。そのうちの1種類の写真を撮影してみました(図9)。金色+黒色ケースなのでなんかよさそうな感じです。これは1500μF 6.3V品で74円という結構高めのニチコンHZシリーズというものです。
前回と同じ条件で周波数特性も測定してみる
図7, 8と同じ条件で測定してみました(図10)。ESRが低いのでアウトレンジになっています。そこで10dB/divに変えてみました(図11)。このプロットからもESRがかなり低いことが分かりますね!
図11のプロットはフロア(ボトム)部分がノイズ気味ですが、ここを減衰のフロアとして考えると、さてESRは何Ωと計算できるでしょうか? 後半で考えてみたいと思います。

図9. 注文してあった超Low ESRコンデンサ(1500μF 6.3V品)
1台目をこのコンデンサに交換したところ、図12のような壮観な眺めになりました。黒金がきれいです…。このコンデンサを使えば、このPCまだ10年は長生きできそうです。今更ながらMB上にSATA(Serial ATA)のI/F(Interface)があることを発見し、当時は「ムフフ、まだまだ」と思ったのでした(笑)。
黒金のコンデンサが並ぶPCが動く日が楽しみだ
詳しくは確認していませんが、PCのプロセッサ電源は電圧1.5Vくらいで80W程度のようですから、50A以上のプロセッサ電流のようです。リプル電流は相当なモノのはず、コンデンサがおかしくなってもしょうがないかなあと、「電気屋のはしくれ」はちょっと思うのでした。
ここでいう「リプル電流」は、プロセッサのCLK脈動ではなく、スイッチング電源のリプルのことを意図しています。プロセッサのCLK脈動は(図1、図5の写真のように)プロセッサ周辺にセラミック・コンデンサがばら撒かれているので、これで対応というところでしょうか。
80Wだなんて…。アマチュア無線のHF帯(短波帯)なら地球の裏まで飛んでいく電力だ…。
作業はまだまだ続くのだった
交換作業はまだまだ続きます。ゆっくり作業できる時間もなく、まだTH(Through Hole)に半田を再度埋め込んだ状態でした。これからTHの半田抜き、コンデンサ実装、テストHDDでOSインストール、Prime95(プロセッサ負荷試験)やMEMTEST(メインメモリのテスト)でのテストランと続きます。1台目が立ち上るのにあと2週間くらいはかかるかも…というところでした。
いずれにしても黒金のコンデンサが並ぶPCが動くようすを楽しみにしている今日この頃でありました。
スルーホールの半田ヌキは皆さんどうしているのだろうか
しかしコンデンサ抜き取りまでは良かったのですが、THからの半田ヌキに相当てこずりました。ネットでは「高容量の半田ごてとアミアミの半田吸い取り(ソルダーウイック)でやりました!」とか書いてありますが、私には無理です…。超技です…。
私としてはホットプレート上で半田吸い取り器(アミアミではありません、「器」です)を使って、さらに反対側から助手(前出の「天の声」)に60Wのコテで熱してもらって漸(ようや)くTHから半田を抜けました。この設備で「漸く」なのですから、皆さんホントどうやっているのでしょうか??
とくに内層+L1, L4にベタがある、グラウンド・パターンが難しかったです…。
プロセッサの温度上昇を考える
交換後のPrime95の負荷試験とMEMTESTでのメモリチェックで合計数時間回して問題ありませんでしたから、問題なく実稼動するものと思います。
プロセッサは負荷をかけると消費電力が変わるようです。アイドルの状態でヒートシンクを手で触ると低い温度なのですが、Prime95負荷テストで100%状態にすると徐々に温度が上がってきます。普通の人なら「あたりまえじゃん」と思うかもしれませんが、デジタル回路としては、

として消費電力P [W]が決まってきます。kはゲート活性率、fCLKはプロセッサ内部ロジックの同期クロック周波数、この2つで流れる電流量Iが決まり、ゲート数nとコア電圧V2(のはず…電流IもVによって変るので)が加わり、これらが掛け算…関数式となって、電力Pが決まります。
ここには「プロセッサの負荷状態」の係数はありません。でもかなり温度が変ります。これはたぶん、
●ゲート活性率が変るのか?
●ダイナミック動作の部分が多いのか?
●クロックゲーティングをしているのか?
というところかなと部外者は思います…。
パワーFETも結構熱いものがある
図13はプロセッサ周辺のFET部分ですが、ここで5Vを1.5Vにドロップしています。流れる電流も多いようで結構熱くなります。放熱は内層に逃がして、半田面からピンク色の放熱シートでケースに逃がす構造です。でもかなり熱く、内層に熱を逃がせばその周辺のコンデンサの温度も上がってしまいます。どうなのかな?と思いました。
そこでAmazonでミニ放熱ブロック(これも図13。こんなものがAmazonで売っていること自体も凄いですが)を購入し、それをつけてみました。簡易計測で温度を測ってみると、放熱ナシ = 65℃、放熱アリ = 63℃で殆ど変りません。誤差の範囲です。なーんだと思う一方、内層に廻ってピンク色放熱シートに流れる熱量が相当なものなんだな、とも思った次第です。
なお「焼け石に水」ですが、ミニ放熱ブロックのフィンの向きはプロセッサから生じる熱のエアフローを考慮してこの向きにしてあります(無意味なコダワリ?)
なんとか順調に交換作業は進んでいく
引き続きはもう1台のジャンク購入分の改造です。このジャンク購入分は、1台目が動くことは確認できたので、CPU, MEM, ソケットリテンション, IDEケーブルなど、ジャンク購入時に不足していたものをヤフオクでゲットしていきました。P4 2.6G FSB 800M = 300円、PC2700-512M ×2 = 1200円という感じで、殆どゴミ値段で完成しそうです(笑)。
代替として使っていたマシンもケースを開けてみましたが、こちらもコンデンサがかなり膨らんでいました。ジャンク品の修理(2台目)後に、こちらもコンデンサ交換しようとあらためて思いました。
低ESR固体電解コンデンサも使われていた
少し話題が外れてきましたので、MBで使われていた超Low ESR「固体」電解コンデンサの話題に移ってみたいと思います。
黒金の超Low ESR電解コンデンサはニチコンのUHZ1C152MPM(1500μF 6.3V)というものですが、これはESR = 12mΩmax(10mm×12.5mm品)のようです。これが8個並列になっていますので、全体で1mΩちょっと程度になっていると推測します。
それプラス、図14のようなコンデンサがついていました。680 4Vと書いてありました。「これは何だろう?」とネットでサーチしながら考えていました。ケース上のマークが日本ケミコンに似てはいたのですが、単なる「四角」にしか見えず、そこまで気がつきませんでした。いろいろサーチした結果、日本ケミコンの「APSA4R0ELL561MHB5S 560μF 4V品」ということが分かりました。それで四角マークを「ああ、なるほど」と思ったのでした。現品もRSコンポーネンツでゲットし、交換することができました。
この固体電解コンデンサはESRがとても低い!
これは「CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID CAPA-CITORS(導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ)」という固体コンデンサで、さきのUHZ1C152MPMのESR = 12mΩmaxと比べて、1個で7mΩmaxというものです。有名なSANYO OSコンと同類なもののようですね。
これが2個ついていました。これはIntelのリファレンスデザインで決められているのかなあと、これも思ったものでした。
さきのネットワーク・アナライザの結果からESRを求めてみる
中盤のあたりでネットワーク・アナライザを用いてコンデンサのリアクタンス(とESR)を測定し、「さてESRは何Ωと計算できるでしょうか?」とクイズを出させていただきました。ここでいよいよ実際にその答えを求めてみます。
図15はネットワーク・アナライザ(以降「ネットアナ」と呼びます)を超簡単にADIsimPE上でモデル化したものです。ネットアナは、このように信号源と信号源抵抗RS、ネットワーク(回路)を経由した電力を測定する負荷抵抗RLにて構成されているものです。このRSとRLの間に測定対象DUT(Device Under Test)であるコンデンサを並列に接続します。
原理的には、ネットアナの信号源の大きさはいくらでもよく、図15のように接続して、そのときRLに生じた電力レベルを0dBとして設定します。これを「スルー校正(スルー・キャリブレーション)」といいます。
とはいえ、このADIsimPEでのモデル化では、この「校正」プロセスはありませんから、このように接続したときにRLに0dBm(1W)が発生するように、信号源の大きさを設定してあります(1V/√5)。
一応確認してみましょう。図16に図15の状態でRLで得られる電力を示します。ただしく1mW(0dBmになる)が得られていることがわかります。
実際の手計算を最初にやってみる
まずは図11のネットアナでの実測結果から、手計算で考えてみましょう。ADIsimPEで実際にシミュレーションしてみる回路にもなりますが、この手計算のための等価回路として、図17にネットアナでの測定系のモデルを示します。
コンデンサのESR(R_ESR)はRL = RS = 50Ωと比較して非常に小さいものです。
そのためネットアナ信号源からその信号源インピーダンスRS = 50ΩとコンデンサのESRと負荷抵抗RLとの分圧により、ESRの端子(負荷抵抗RLの端子でもある)に生じる電圧は、

R_ESR << 50Ωなわけですから、ESRの端子間に得られる電圧は「RLの影響により電圧が低下することなく」ほぼそのままネットアナの負荷側RL = 50Ω に加わることになります。つまり、

一方、校正を取った状態というのは、RL = RS = 50Ωとなり、上記の式同様に計算すると、

となります。たとえばネットアナが1Vを基準(0dB)に校正されていれば、このときの信号源電圧は「VSRC=2V 」になります(この「2倍」という考え方が高周波回路では大切です)。
つまり図11の結果が「-65dB」ということは、-65dB = 20log(VRL/1V)ですので〔1Vを基準(0dB)に校正されているので分母はこうなる〕、
VRL= 0.000562V
であり、再度、式(3)を簡略化して

とすれば、RS = 50Ωなので、上記を式変形して代入すると、

となりESRが 14mΩ程度になると計算できます。これは赤金HZシリーズ電解コンのESRmax(12mΩ)にかなり近い値ですね。測定時での実態は、-65dBより若干小さい値になっていたのでしょう。
ADIsimPEで検算してみる
ここまでの流れをあらためて説明します。図11でHZシリーズ電解コンのESRの実測結果を示しました。また図15にネットアナでの測定をADIsimPEでモデル化したようすを示しました。
図17ではシミュレーション系にDUTとなるコンデンサのESR(R_ESR = 14mΩ)を接続してあります。
前の節で計算結果が「14mΩ」として得られたので、いよいよこの節で検算してみましょう。
図15、図16で分かるように、このシミュレーション系ではスルー校正として0dBmが得られるように設定しています。
図17のようにR_ESR = 14mΩを接続しシミュレーションしてみると、図18の結果のように313.25pW = -65.04dBmとして計算できます。
つまり、ここまでの手計算での考え方は正しかったということが分かるわけです。
まとめにかえて
無事に3台のPCが立ち上がった(復旧した)数日後、福井に居る長男が、旅行先の山形の酒をもって帰ってきました。「合計3台パソコンが出来るが要るか?」「プロセッサは何?」「P4 2.6Gだよ」「ふっりぃーなあ。ワード・エクセルならいいんだろうが、オレは要らないよ」とのこと。「10年は使えるぞ!」「かー…PCで10年?!(笑)」。さてどうしよう…。
※現時点ではこれら3台のPCは全て廃棄し、秋葉原で中古で購入したマシンを使用しています(また中古…笑)
著者について
デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...
この記事に関して
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}