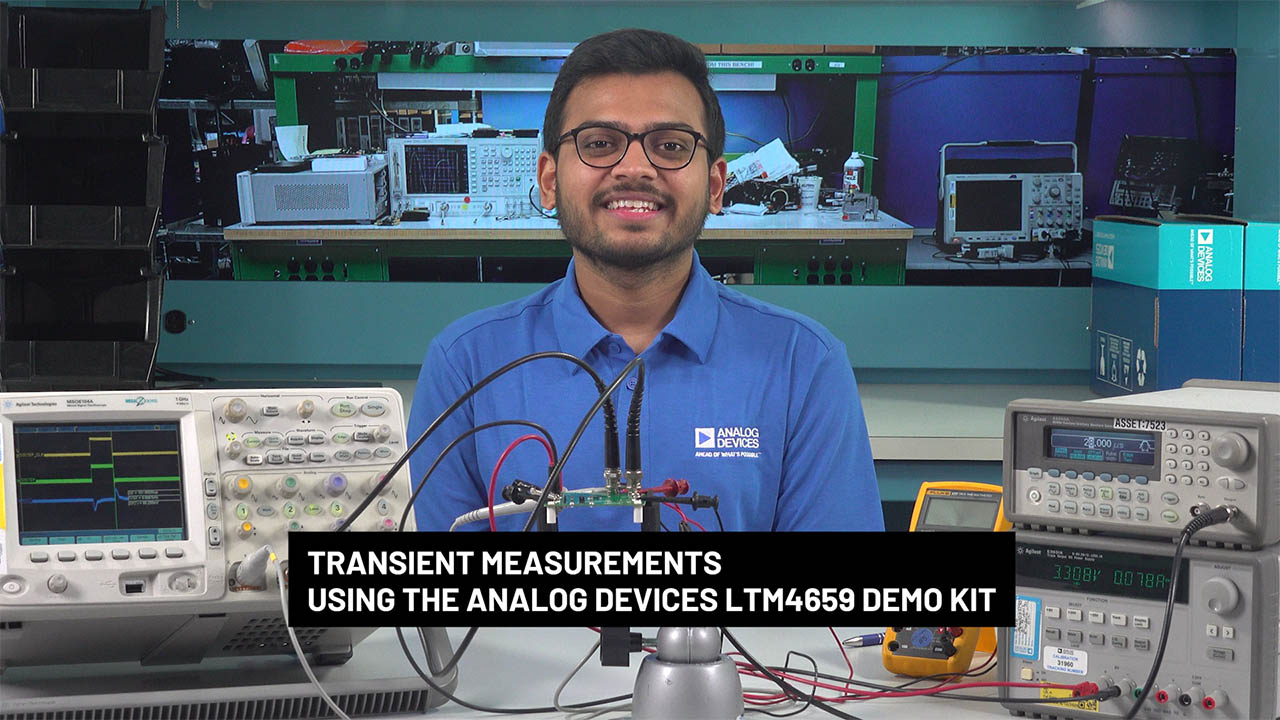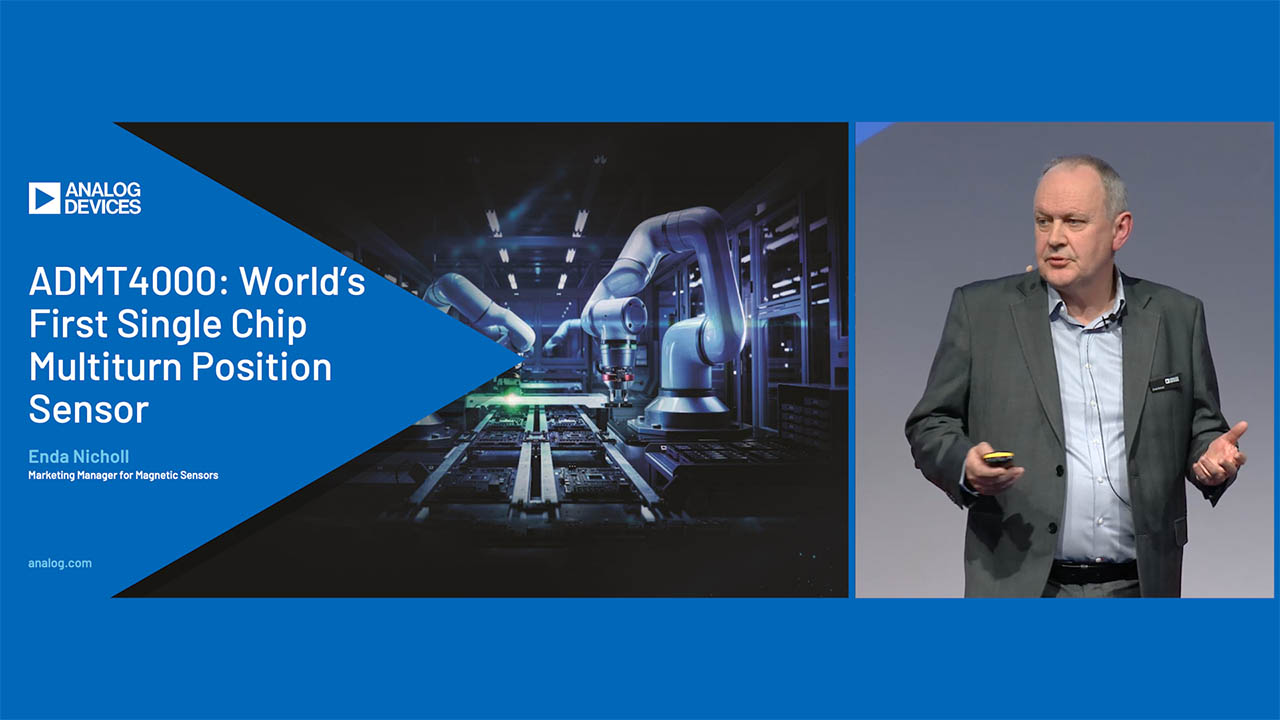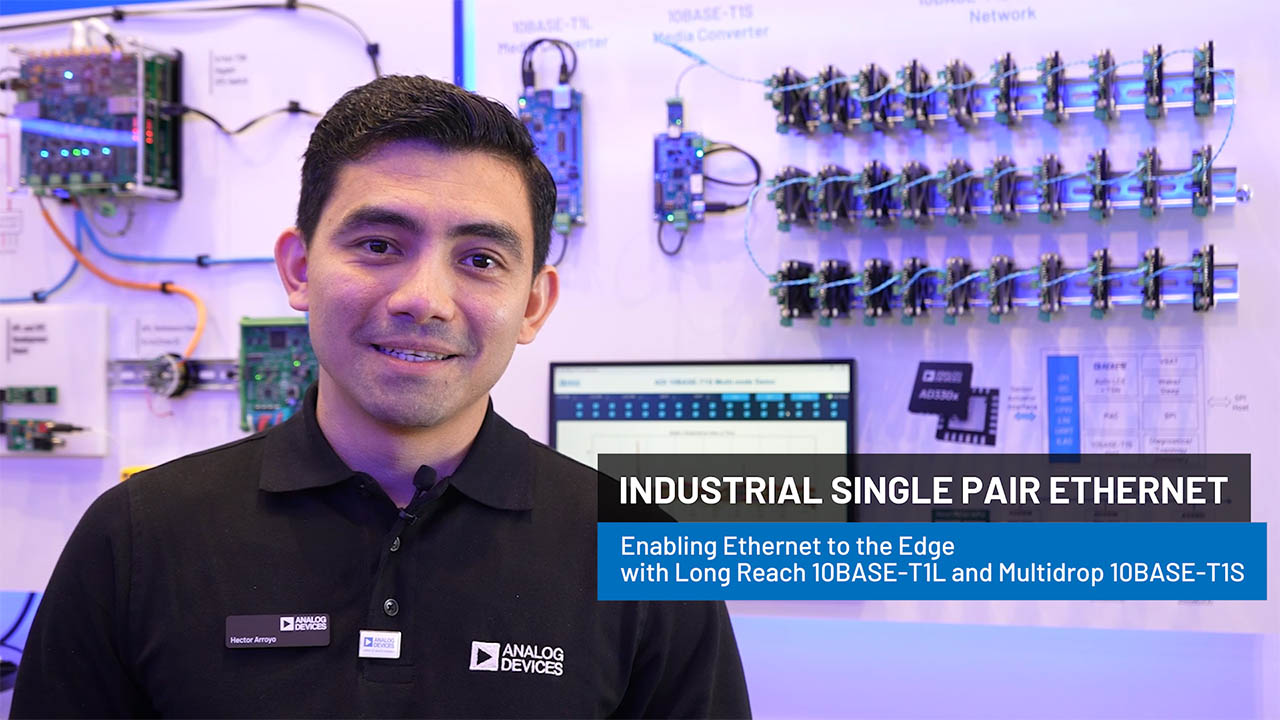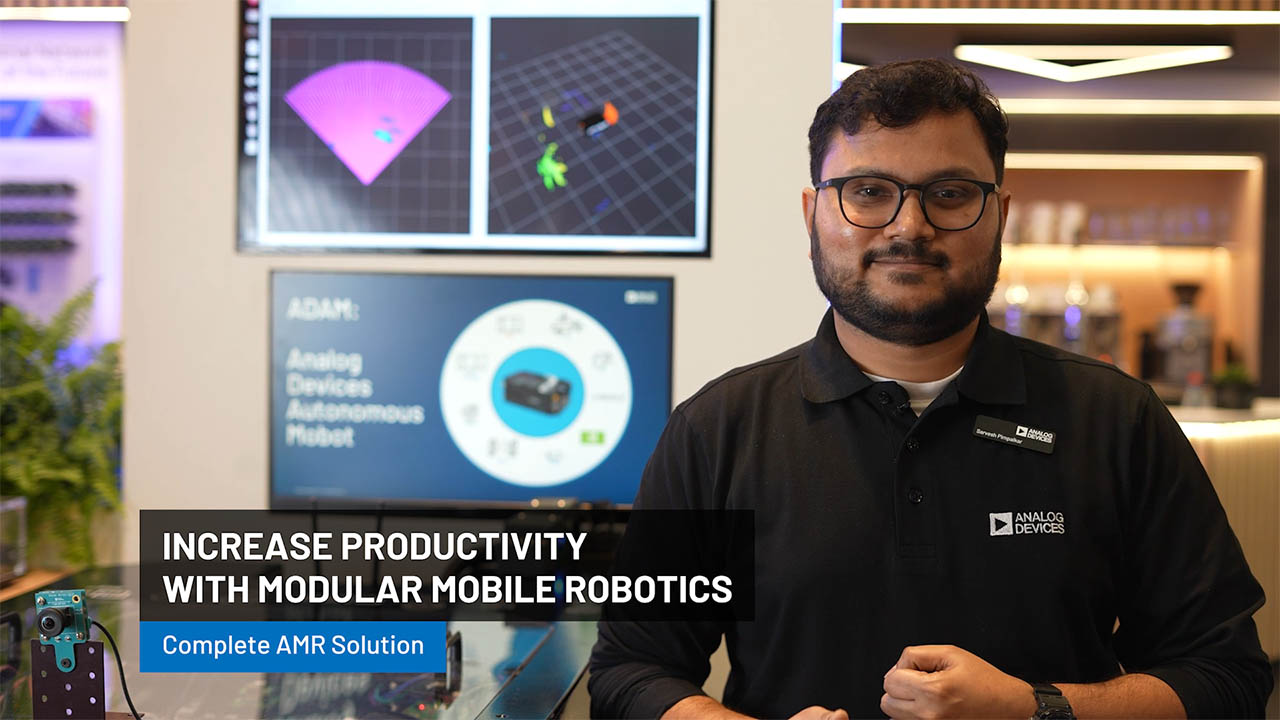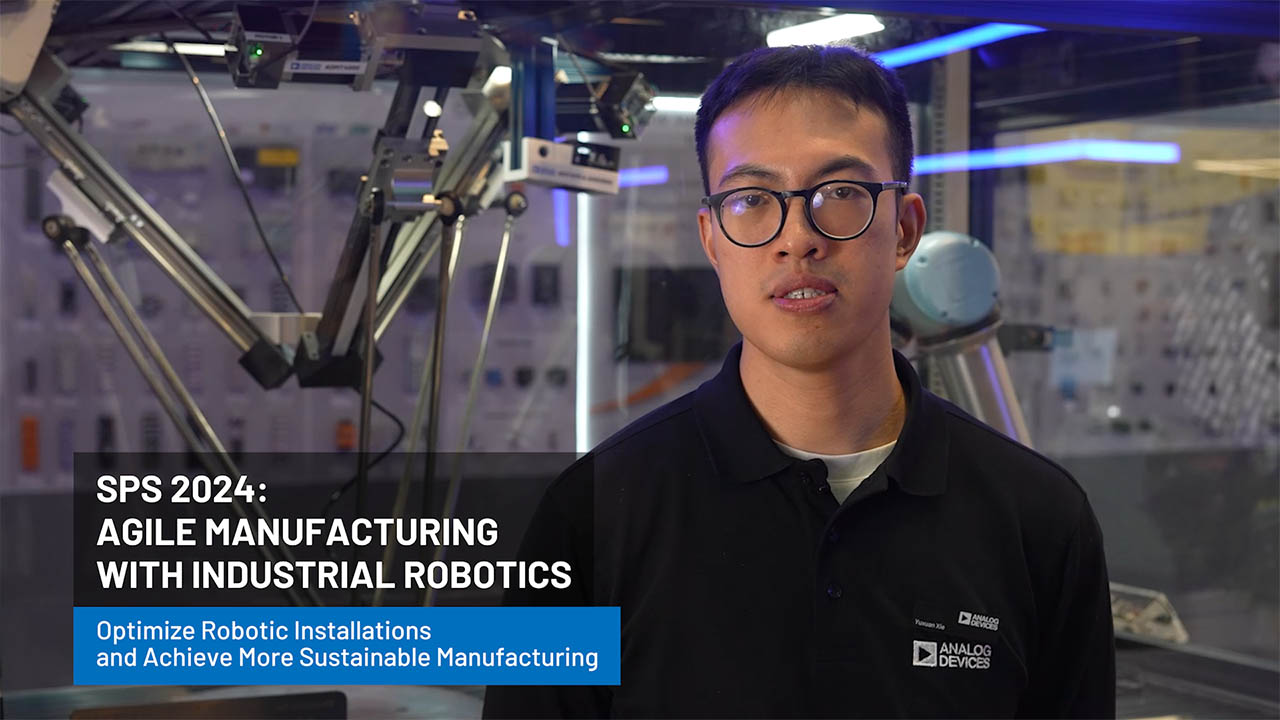要約
高ゲインや高CMRRが要求される高精度アプリケーションでは、長い間、3個のオペアンプによる計測アンプが業界標準でした。しかし、最近のアプリケーションに多い単一電源での動作において、このアンプは重大な限界があります。このアーティクルでは、従来、使われてきたオペアンプ3個構成のアーキテクチャによる計測アンプの問題点を解説し、単一電源動作の計測アンプにおいて大きなメリットを持つ、マキシムの間接電流フィードバックアーキテクチャを紹介します。詳細な分析とともに、その証拠となる実験波形も紹介します。
このアーティクルはマキシムの「エンジニアリングジャーナルvol. 60」(PDF、912kB)にも掲載されています。
計測アンプアプリケーション
計測アンプは入力インピーダンスが高いという特長を持ち、大きなコモンモード電圧が存在する状態で微小な差動電圧を増幅する回路です。このため、圧力や温度を検出するひずみゲージのブリッジインタフェースや熱電対による温度検出、ローサイドおよびハイサイドの各種電流検出アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションで広く使用されています。
オペアンプ3個構成の計測アンプ
代表的なオペアンプ3個構成の計測アンプ(図1参照)は、優れたコモンモード除去と、抵抗1個で設定可能な正確な差動利得を持ちます。このアーキテクチャは2段構成で、初段はユニティゲインのコモンモード利得と差動利得のすべて(あるいはほとんどすべて)、後段はユニティゲイン(あるいは小利得)の差動利得とコモンモード除去のすべてを提供します(図2参照)。
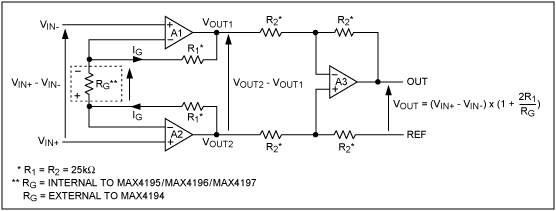
図1. オペアンプ3個構成の計測アンプであるMAX4194~MAX4197ファミリの内部アーキテクチャ
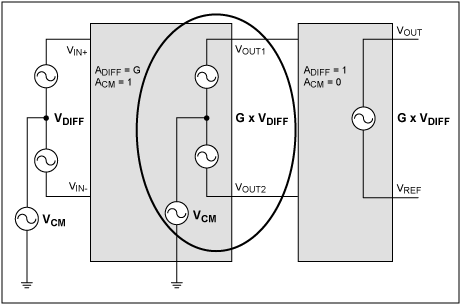
図2. 入力信号をこのように2段階で増幅する場合、入力コモンモード電圧は中間(円で囲ったところ)を通過します。
最近の低電圧アンプはほとんどがレイルトゥレイル出力を持っていますが、レイルトゥレイル入力を必ず持つとは限りません。ここでは、非常に高ゲインのレイルトゥレイル入力と出力を備えたオペアンプ3個構成の計測アンプ(図1のようなタイプ)を単一電源(VCC)で動作させる場合について検討します。
VOUT = 利得 × VDIFF + VREFであるため、次式が成り立ちます。
(VOUT1, VOUT2) = VCM ± (利得 × VDIFF/2)
= VCM ± (VOUT - VREF) / 2
VOUT1とVOUT2は電源電圧に達しないよう、次式の条件を満足する必要があります。
0 < (VOUT1, VOUT2) < VCC
(i.e., 0 < VCM ± (VOUT - VREF) / 2 < VCC)
ただし、
0 < VOUT < VCC
アプリケーションでは、一般に、VREF = 0 (ユニポーラ入力信号)とするか、VREF = VCC/2 (バイポーラ入力信号)とします。
VREF = 0の場合、前述の不等式は、次式のように簡略化されます。
0 < VCM ± VOUT/2 < VCC
VREF = VCC/2の場合、前述の不等式は、次式のように簡略化されます。
0 < VCM ± VOUT/2 ± VCC/4 < VCC
これらの条件は、図3のグラフを見ると最もわかりやすくなります。
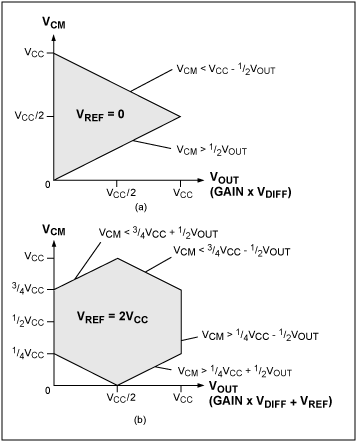
図3. オペアンプ3個構成の計測アンプを単一電源で動作させたとき、各入力差動電圧で利用可能なVCM。(a)はVREF = 0の場合、(b)はVREF = VCC/2の場合です。横軸は増幅された入力差動電圧(VOUT)です。
図3においてグレーで表示した領域は、図1に示すアンプ(A1とA2)の出力が電源電圧まで飽和しない、入力コモンモード電圧のレンジ(入力差動電圧に対する相対値)です。このレンジは、VOUTとVREFによって変化します。これは、VOUT - VREFが入力差動電圧を増幅したものであるため、許容されるコモンモード入力のレンジは入力差動電圧に よって変化します。
実際問題としては、もちろん、回路の利得を最大限に活用し、最大差動電圧が入力にかかったとき、最大の出力スイング(VOUT)を得ることが最善です。VOUT = 0あるいはVOUT = VCCとなるように最大入力差動電圧を計測アンプが増幅できる範囲が、図4において黒で示した領域です。
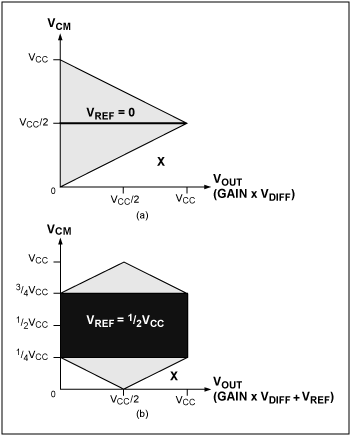
図4. 黒い四角の部分は、従来型のオペアンプ3個構成の計測アンプによる増幅で(最大入力差動電圧において)最大出力電圧を得ることができる入力コモンモード電圧の範囲を示します。(a)はVREF = 0の場合、(b)はVREF = VCC/2の場合です。
このように、いずれの場合も、入力コモンモード電圧には大きな制限があります。特に、
- ユニポーラ入力差動信号をフルに増幅したい場合(VREF = 0として、0~VCCのフル出力スイングを得たい場合)、信号には½VCCのコモンモード電圧を伴わせる必要があります。コモンモード電圧がこの値からはずれると、出力電圧がVCCというフルスイングにならなくなります(最大入力差動電圧が低下する)。バイポーラ入力差動信号の場合(VREF = ½VCC)、0~VCCのフルスイングの出力電圧を得ることができる入力コモンモード電圧のレンジは¼VCCから¾VCCまでとなります。
- いずれの場合も、入力コモンモード電圧がグランド(0V)に等しいか近い場合、このアンプで入力差動電圧を増幅することはできなくなります。つまり、(必要とする)入力差動電圧と(不要な)入力コモンモード電圧との間に関係はないと仮定する場合、VOUT全域が許容されるVCMの設計最小値と設計最大値は、黒で示した領域になります。この領域からはずれた場合、VDIFFとVCMの組み合わせによっては、VCMが不適切になるおそれがあります。なお、図4aにおいて、フルスケールのVCM変動幅が必要な場合、入力コモンモード電圧精度がゼロになる点に注意する必要があります。要するに、入力信号においてコモンモードの変動がまったく許容されないということです。
そのため、単一電源システムでは、オペアンプ3個構成の計測アンプのアプリケーションが限られてしまうことがわかります。続けて、以下の2点について検討してみましょう。
- 内部のアンプ(A1とA2)が電源電圧まで飽和したら、何が起きるのか。
- 入力アーキテクチャがレイルトゥレイルでない場合には、どうなるのか。
入力アンプ飽和の影響
アンプA1の出力がグランドに飽和したケースを考えてみましょう。つまり、VIN+ > VIN- かつコモンモード電圧が図4のXという場合です(VDIFFが、グレー領域で許される値よりも大きい)。
A1が飽和している(VOUT1 = 0)ため、動作がコンパレータ(非直線)モードとなり、反転端子の電圧が非反転端子(VIN-)と異なる状態となります。その場合、アンプA2は非反転端子(VIN+)の電圧に対して1 + R1 / (R1 + RG)の利得を持つ非反転アンプとして動作します。高ゲインアンプということはRG << R1であり、アンプA2は2という非反転利得を持つアンプとなります。
VOUT2 = 2 × VIN+ = 2 × (VCM + VDIFF/2)
= 2 × VCM + VDIFF
差動アンプの第2段、A3は、入力のVOUT1とVOUT2を比較して、その差を出力するだけです。
VOUT = (2 × VCM + VDIFF) + VREF
同様に、A2がグランドに飽和したケースでは、以下のようになります。
VOUT = -(2 × VCM - VDIFF) + VREF
この状態は、オペアンプ3個構成の計測アンプにとって危険な動作モードです。入力差動電圧の増幅をしなくなっただけでなく、何らかの方法で「思いやりを持って能力低下」しないで、入力差動電圧に対する相対的な入力コモンモード電圧を増幅するモードに入ってしまうからです。しかも、コモンモード電圧は基本的に制御されておらず、対象信号を劣化させる不要ノイズであることが多いことも、この問題をさらに悪いものとします。もともとそのようなノイズを除去することが、計測アンプを使用する目的であるため、これはとても重大な問題です。
非レイルトゥレイル入力アーキテクチャの影響
前述のように、基本的に、アンプ出力はレイルトゥレイルとなっていますが、入力はレイルトゥレイルとなっていません。高精度アプリケーションに対応するレイルトゥレイル入力段は設計が特に難しいと言えます。これは、VCCコモンモード電圧付近の動作とGNDコモンモード電圧付近の動作とのクロスオーバが理想的とはなりえないからです。この遷移が起きると、入力差動段におけるnタイプとpタイプのペア間にオフセット電圧が発生することがあります。高精度の計測アンプを設計するためには、低VOSと高CMRR が鍵です。CMRR = ΔVOS / ΔVCMであるため、コモンモード電圧がクロスオーバ領域をこえて変化するときのVOS変化が、CMRRを大幅に劣化させてしまいます。
そのため、負レイル(0V)を入力コモンモード電圧レンジ内に持ってはいるものの、高精度計測アンプは、基本的に非レイルトゥレイル入力のタイプとなる傾向があります。図3で入力コモンモード電圧の制限を考慮し、グラフを描き直すと、図5のようなグラフとなります。
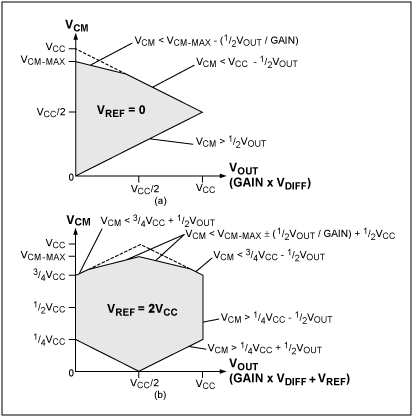
図5. オペアンプ3個構成の計測アンプを単一電源で動作させたとき、各入力差動電圧で利用可能な非レイルトゥレイル入力段を考慮に入れた入力コモンモード電圧。(a)はVREF = 0の場合、(b)はVREF = VCC/2の場合です。
間接電流フィードバックアーキテクチャ
間接電流フィードバックアーキテクチャは、計測アンプの新しい設計手法ですが、いろいろなメリットがあり、非常に人気のある方式となりました。計測アンプのMAX4462とMAX4209における間接電流フィードバックアーキテクチャを示したものが図6です。
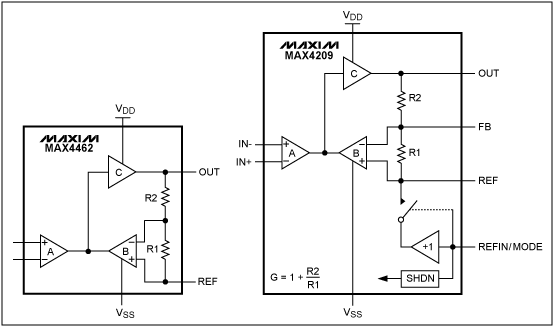
図6. 計測アンプのMAX4462とMAX4209には、間接電流フィードバックアーキテクチャが採用されています。
新しいこのアーキテクチャでは、1つの高ゲインアンプ(C)と2つの相互コンダクタンスアンプ(AとB)を使用します。2つの相互コンダクタンスアンプは、いずれも、入力差動電圧を電流に変換するとともに、入力コモンモード電圧を完全に除去して出力します。アンプの安定動作点では、アンプAのgM段からソースされる出力電流がアンプBのgM段によってシンクされる入力電流と等しくなります。この電流マッチングを実現しているのが、フィードバックアンプBの入力にかかる差動電圧をアンプAの入力にかかる差動電圧と強制的に等しくする、高ゲインアンプCによるフィードバックです。この設計では、出力抵抗チェーンとR2に定められた電流(VDIFF / R1に等しい)が流れます。つまり、OUTに出てくる出力電圧は、入力差動電圧に利得をかけたものとなります(利得= 1 + R2 / R1)。標準的なオペアンプ3個構成の計測アンプと同じように、REFに任意のリファレンス電圧をかけ、出力にオフセットを加えることもできます。
図7はこの動作を高レベルのブロックダイアグラムとしたもので、これを図2と比較すると、どのようなメリットを持つのかが明確にわかります。オペアンプ3個構成の計測アンプの場合、中間部分における信号は利得をかけた差動電圧だけでなく、入力コモンモード電圧も含んでいます。これに対し、間接電流フィードバックアーキテクチャでは、入力差動電圧の最新状態を表すものだけとなります。コモンモードは、すべて、初段で除去されます。第2段は、コモンモード除去を補強するとともに差動利得を提供し、必要に応じてリファレンス電圧によって出力をオフセットします。つまり、オペアンプ3個構成の計測アンプに存在した入力コモンモード電圧の制限が、間接電流フィードバックアーキテクチャでは存在しないのです。
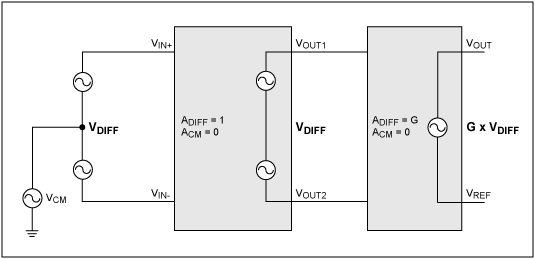
図7. 間接電流フィードバック計測アンプでは、第1段の出力にコモンモード電圧が出ることはありません。
入力コモンモード電圧の制限(つまり非レイルトゥレイル入力段)を考慮すると、伝達特性は図8のようになります。黒い領域が、フルレンジの出力電圧が得られる入力コモンモード電圧の設計限界を示します。グレーの領域は、計測アンプが期待通りに動作する、つまり、入力差動電圧に利得をかけた電圧が出力に得られ、入力コモンモード電圧が完全に除去される入力コモンモード電圧のレンジです。
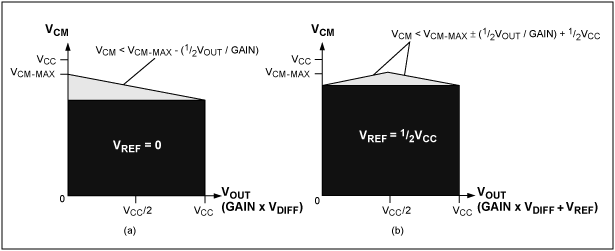
図8. 間接電流フィードバック計測アンプにおいて使用可能な入力コモンモード電圧のレンジをグレーと黒で示します。(a)も(b)も黒で示した領域(グレー領域に含まれる)では、フルスイングの出力電圧を得ることができます。
実験結果
間接電流フィードバックに関するここまでの検討結果を支持する実験結果が得られています。ここでは、MAX4197とMAX4209Hを比較します。いずれも、利得100を持つ計測アンプですが、MAX4197はオペアンプ3個構成型、MAX4209Hは間接電流フィードバック型です。ふたつの計測アンプとも、VCC = 5V、VREF = 2.5Vとして、デバイスのゼロ出力をオフセットしました。
この実験では、2種類の波形を計測アンプに加えました。
ケース1は100Hzの大きなコモンモード電圧が存在する状態で、1kHzの差動電圧を入力しました。計測アンプの出力は、1kHzの信号だけで100Hz成分がないことが期待されます。これらの波形は、次式で近似できます。
VIN+ = サイン波振幅= 2VP-P、 オフセット= 1V、周波数= 100Hz
(VIN+ - VIN-) = サイン波振幅= 30mVP-P、 オフセット= 0、周波数= 1kHz
ケース2は、1kHzの大きなコモンモード電圧が存在する状態で、100Hzの差動電圧を入力しました。計測アンプの出力は、100Hzの信号だけで1kHz成分がないことが期待されます。これらの波形は、次式で近似できます。
VIN+ = サイン波振幅= 2VP-P、 オフセット= 1V、周波数= 1kHz
(VIN+ - VIN-) = サイン波振幅= 30mVP-P、 オフセット= 0、周波数= 100Hz
結果は次の通りとなりました。なお、チャネル1がVIN+、チャネル2がVIN-、チャネル3が計測アンプの出力です。
ケース1の結果
図9aに示すように、MAX4209Hからは期待通りの出力が得られました。MAX4197が期待通りの動作をするのは、入力コモンモード電圧がグランド以上という条件においてのみでした(図9b)。MAX4197の出力電圧には、明らかに100Hz成分が乗っています。
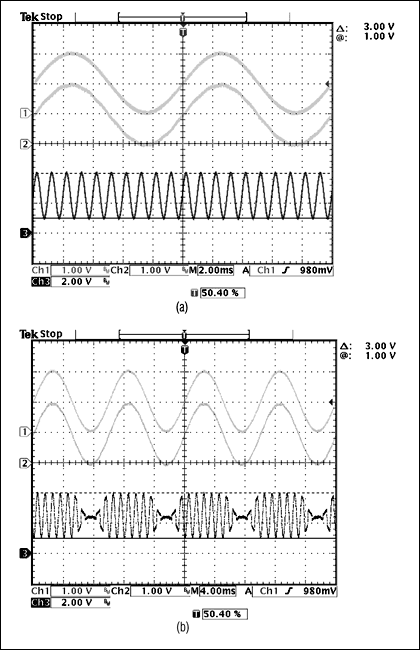
図9. ケース1の結果。(a)は間接電流フィードバックアーキテクチャを採用したMAX4209H、(b)はオペアンプ3個構成によるMAX4197です。入力1と入力2のトレースは、100Hz VCMが支配的であり、1kHzのVDIFFは見えないほど小さいことがわかります。
ケース2の結果
こちらも、MAX4209Hからは期待通りの出力が得られました(図10a)。MAX4197は、コモンモード電圧がグランドを大きく上回った状態においてのみ、入力差動信号の増幅を行いました(図10b)。コモンモード電圧がグランド近くになると、飽和したのがA1かA2かにより、出力電圧はコモンモード電圧を反転したものか、あるいはそれをバッファしただけのものとなります(前述の通り)。
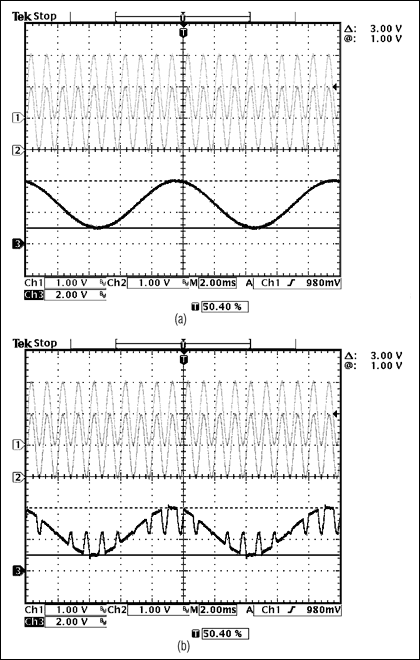
図10. ケース2の結果。(a)は間接電流フィードバックアーキテクチャを採用したMAX4209H、(b)はオペアンプ3個構成によるMAX4197です。図9と同じように、オペアンプ3個構成の計測アンプでは、所望する出力に1kHz VCMがかぶっていることがわかります。間接電流フィードバックアーキテクチャは、優れた性能を発揮しています。
まとめ
電子機器の高性能化は急速に進んでおり、消費者は、高性能はもとより、バッテリの長寿命化やエネルギー効率の向上を可能にするインテリジェントなパワーマネージメントの方式も求めるようになりました。そして、デュアル電源のアナログ回路から単一電源アーキテクチャへの移行が進んでおり、電子機器の設計方法や使い方が大きく変化しつつあります。昨日の夢を今日形にするのが、このアーティクルで紹介した間接電流フィードバックアーキテクチャなどの画期的なアーキテクチャです。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}