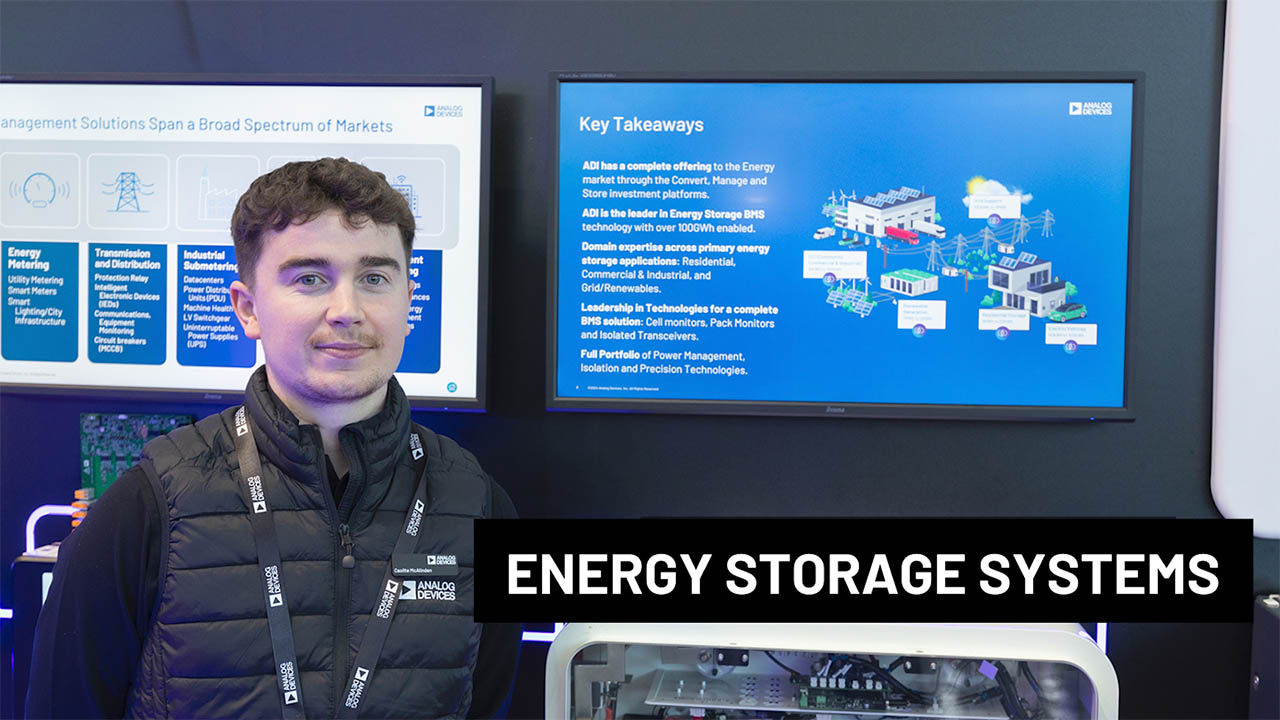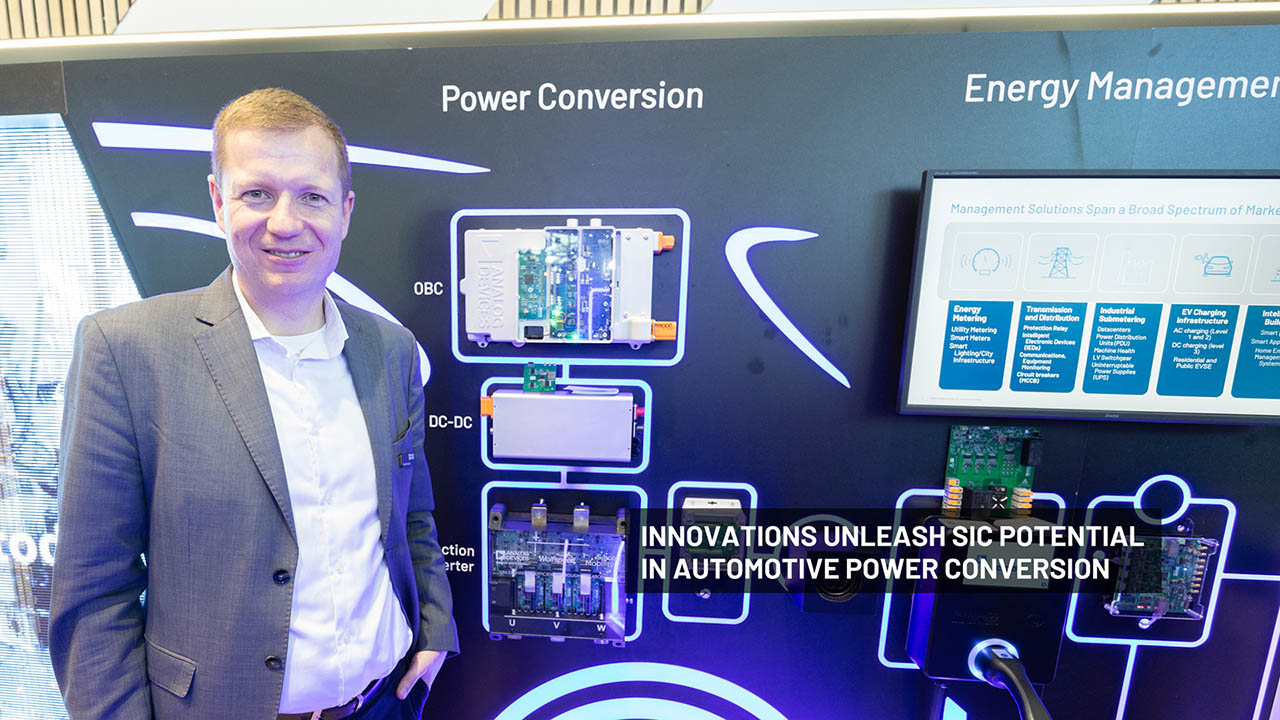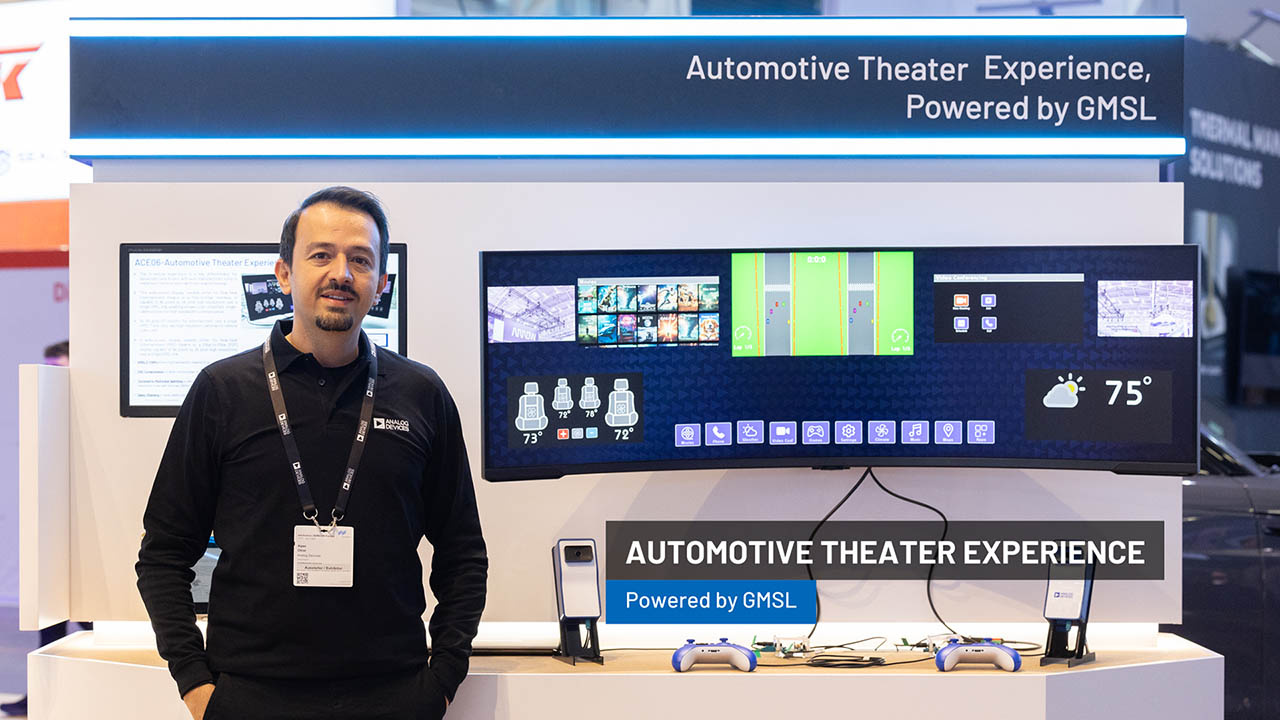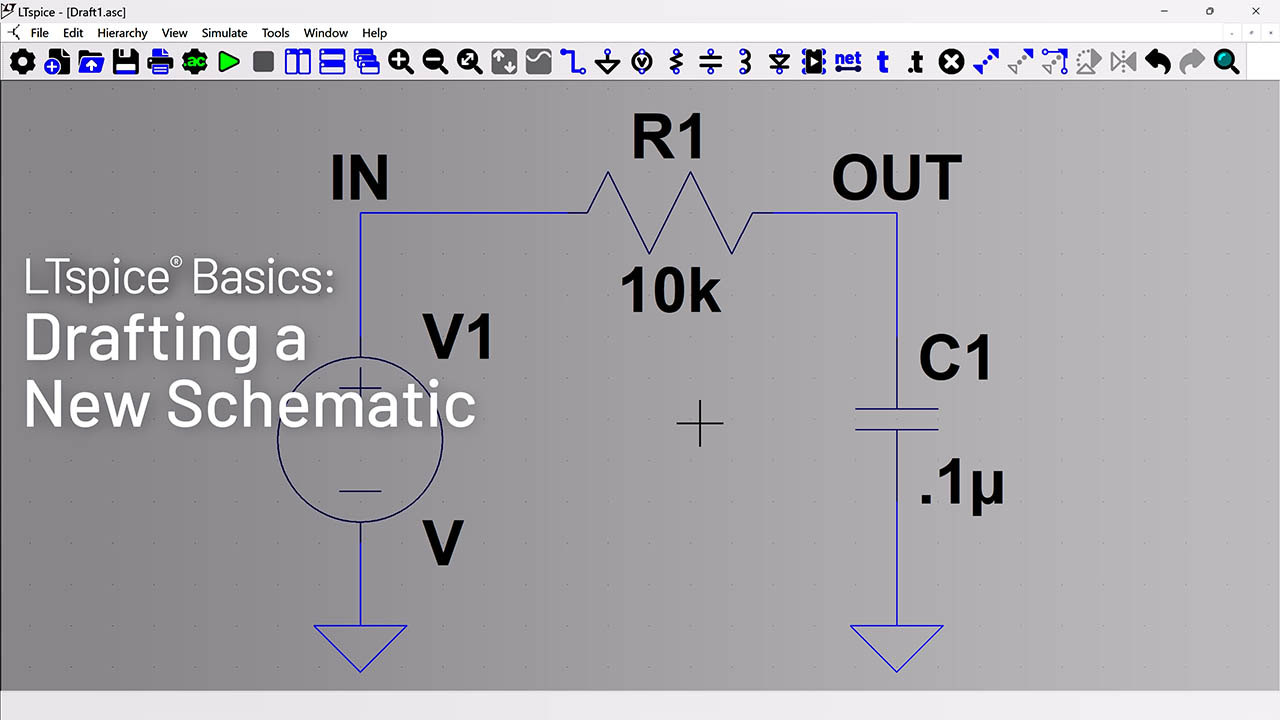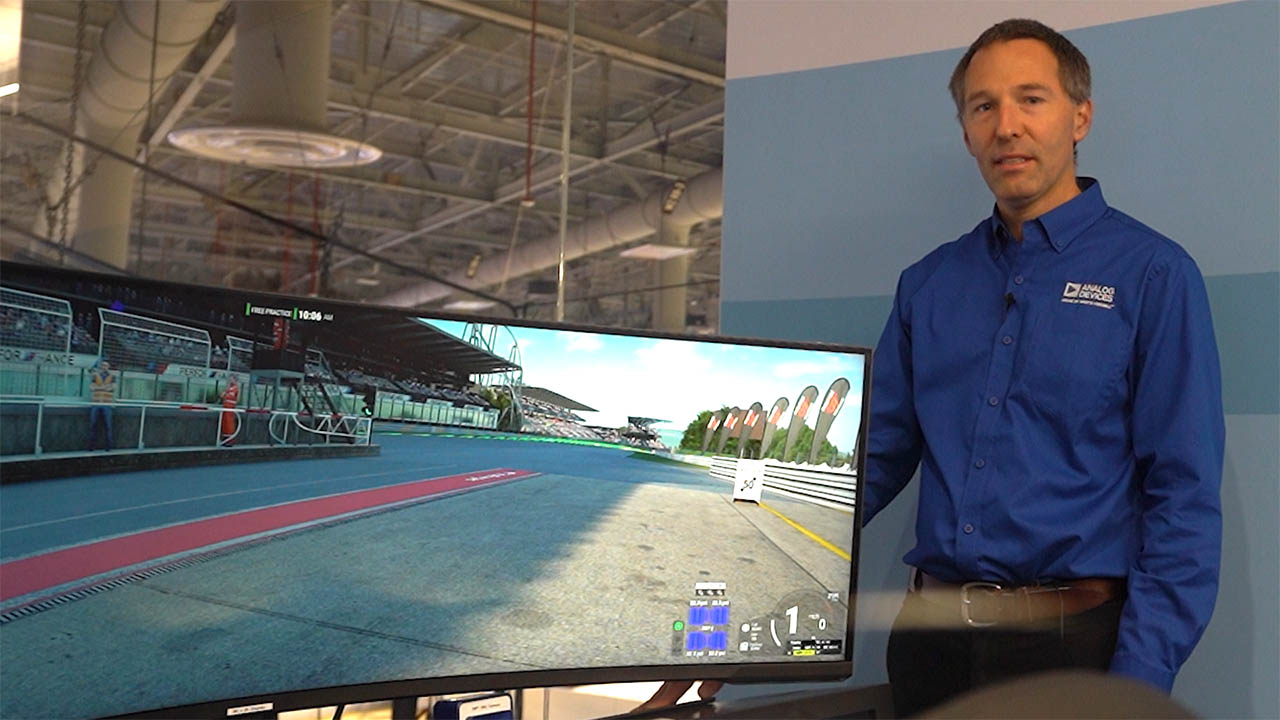要約
局部発振器(LO)からの残留位相ノイズは、集積回路ミキサの内部局部発振器ドライバ/バッファの追加ノイズによって劣化する可能性があります。強いRF信号とLOノイズの相互混合によって、レシーバの感度が低下します。集積ミキサのLOノイズの劣化を規定および評価すれば、システム設計者は、レシーバにおける感度の損失を計算することができます。
はじめに
セルラ基地局のレシーバは、高レベルのブロッカ/干渉源の存在下で動作しながら、アンテナで対象の弱信号を検出することが求められています。干渉源は通常、フィルタによって除去されますが、最初のダウンコンバージョン後の中間周波数(IF)においてのみ行われます。IFフィルタに先行するLNAおよびミキサは、高リニアリティ(IP3)と低ノイズ指数(NF)を持っている必要があります。
図1に、各ブロックを簡略化した標準的な基地局のレシーバが示されています。レシーバは、タワートップの超高Qキャビティ同調フィルタを備えたアンテナを起点とし、LNAがアンテナの近くに配置されています。長い同軸ケーブルによって、受信信号はトランシーバに接続されています。トランシーバユニットは、LNA、低ノイズミキサ、SAWフィルタ、およびIFアンプがカスケード接続され、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)に達しています。最初のミキサは、70MHz~100MHz (CDMA 800/GSM 900)または200MHz~300MHz (GSM 1800/GSM 1900/UMTS)の標準的なIFへのコンバージョンダウンを実行します。
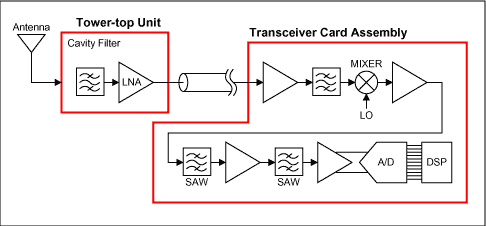
図1. セルラ基地局のレシーバの基本ブロック
ミキサブロックのリニアリティとノイズに必要な条件は通常、LOポートへの17dBm以上の駆動を必要とするパッシブダイオードリングミキサによって満たされます(図2)。これらの基地局のミキサは、外付けの50Ωバッファアンプによって駆動されるディスクリート設計またはハイブリッドモジュールです。したがって、ミキサに印加する前に局部発振器の残留ノイズにフィルタリングすることが可能です。ICを実装する場合、システム要件を満たすように局部発振器ドライバノイズの規定および設計に注意を払う必要があります。ノイズをkTに限定するために、フィルタリングは、低い発振器レベルのチップへの入力において実行することができます。LO位相ノイズフロアは、バッファアンプによって低下します。大きなブロッキング信号が存在する場合、レシーバノイズはLOノイズと強い干渉源の相互混合によって増大します。
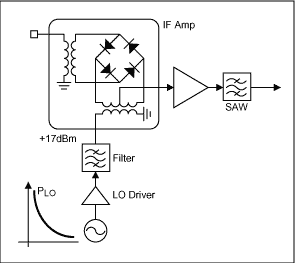
図2. LOフィルタ機能を備えた、ディスクリートパッシブレベル17基地局の受信ミキサ
ミキサのノイズモデル
熱雑音は、受信ミキサにおいて最も一般的に規定および測定されているノイズです。この熱雑音は、50ΩマッチングのRF入力ポート、および-174dBm/Hz (kTo)のノイズ電力密度を備えたミキサのノイズ性能を表します。入力換算の熱雑音は、ミキサのノイズ指数(10log10F)の規定から決定されます。

この場合
k = ボルツマン定数(1.381 x 10-23 J/K)
To = 絶対温度(290K)
および
F = ミキサのノイズ係数
相互混合は、RFポートに強いRF信号が存在する場合に発生します。これは、NFの測定時には説明されていない追加のノイズです。入力換算の相互混合ノイズNrmiは、特定のブロッカレベルSblにおいて求めることができます。ミキサへのLOノイズフロアが 、および帯域幅がBの場合、IFにおける相互混合ノイズは、次のようになります。
、および帯域幅がBの場合、IFにおける相互混合ノイズは、次のようになります。

干渉源周波数のオフセットが所望の信号から十分大きいオフセットである場合、位相ノイズは平坦であると前提されます。これら2つのノイズソースは独立しており、図4に示すように合計することができます。ブロッカが存在する場合、入力から出力への信号対雑音比の劣化は、次式で表すことができます。

LOノイズの規定
ミキサの出力において必要となる搬送波対干渉比(C/I)、入力ブロッカレベル(Sbl)、所望の信号レベル(Sdes)、およびレシーバノイズ帯域幅(B)に基づいて、必要なLOノイズ性能( 、単位:dBc/Hz)を概算することができます。GSM基地局の場合、ワーストケースブロッカ(Sbl)は、3MHzより大きいオフセットに規定された-13dBmです。ブロッキング条件下では、所望の信号感度は-101dBmです。GSMシステムの場合、帯域幅「B」は200kHzです。
、単位:dBc/Hz)を概算することができます。GSM基地局の場合、ワーストケースブロッカ(Sbl)は、3MHzより大きいオフセットに規定された-13dBmです。ブロッキング条件下では、所望の信号感度は-101dBmです。GSMシステムの場合、帯域幅「B」は200kHzです。

10のC/Iを必要とするGSM基地局の場合、位相ノイズフロア は-151dBc/Hzということになります。フロントエンド熱雑音に起因する劣化をより良く説明するために、実際の位相ノイズは1dB程度である必要があります。モバイル基地局は、より厳格でないブロッカ規定を持っており、
は-151dBc/Hzということになります。フロントエンド熱雑音に起因する劣化をより良く説明するために、実際の位相ノイズは1dB程度である必要があります。モバイル基地局は、より厳格でないブロッカ規定を持っており、 = -138dBc/Hzとなります。
= -138dBc/Hzとなります。
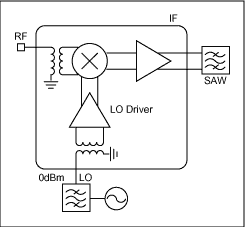
図3. IFにおけるLOバッファと利得機能を内蔵する標準集積回路基地局の受信ミキサ
LOドライバの効果的なノイズフロア
式3に代入された場合の式1および2は、レシーバの信号対雑音比に対するLOノイズフロア (単位:dBc/Hz)の効果を表します。高リニアリティミキサは通常、高いLOドライバレベルを必要とし、アンプのノイズフロアは振幅の次数によって増大します。式2で規定するように、相互混合がIFポートにおけるLOノイズを加えるため、IFにおける測定値からLOドライバのノイズフロアを測定することが可能です。ブロッキング条件下のミキサのノイズを測定するために、図5に示した構成を使用することができます。ノイズフロアは、信号なし条件で測定され、次にブロッキング条件下で測定されます。Nblは、出力熱雑音フロアNthoと、SAWフィルタおよびIFアンプによって変化する出力相互混合ノイズNrmoで構成されます。Nthoは、小信号ノイズ(F)および利得(G)の測定値から決定されます。
(単位:dBc/Hz)の効果を表します。高リニアリティミキサは通常、高いLOドライバレベルを必要とし、アンプのノイズフロアは振幅の次数によって増大します。式2で規定するように、相互混合がIFポートにおけるLOノイズを加えるため、IFにおける測定値からLOドライバのノイズフロアを測定することが可能です。ブロッキング条件下のミキサのノイズを測定するために、図5に示した構成を使用することができます。ノイズフロアは、信号なし条件で測定され、次にブロッキング条件下で測定されます。Nblは、出力熱雑音フロアNthoと、SAWフィルタおよびIFアンプによって変化する出力相互混合ノイズNrmoで構成されます。Nthoは、小信号ノイズ(F)および利得(G)の測定値から決定されます。
NrmoをNblから分離することができ、内蔵LOドライバの (dBc/Hz)を計算することができます。集積回路のミキサの効果的なノイズフロアを規定すれば、システム設計者は、信号対雑音比(SNR)を式3から概算することができます。
(dBc/Hz)を計算することができます。集積回路のミキサの効果的なノイズフロアを規定すれば、システム設計者は、信号対雑音比(SNR)を式3から概算することができます。
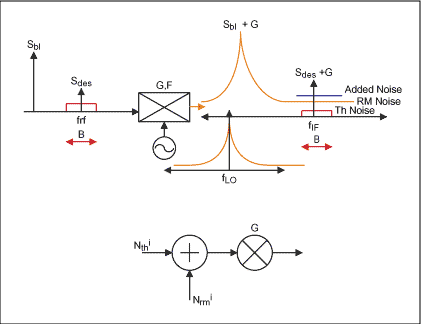
図4. ミキサのノイズを熱雑音と相互混合ノイズの合計として表現
計算例
MAX9993は、PCS/DCS/UMTS (1.7G~2.2G)アプリケーション用に設計されたアクティブミキサです。この製品は、8.5dBの標準利得、9.5dBのNF、IIP3 = 23.5dBm、P1dB = 13.0dBmを備え、0~6dBmの局部発振器駆動PLOで動作します。入力換算の熱雑音Nthiは-174 + 9.5 = -164.5dBm/Hzで、出力の熱雑音フロアNthoは-174 + 9.5 + 8.5 = -156 dBm/Hzとなります。この例における動作周波数は、fIF =190MHz、fLO = 1800MHz、およびfRF = 1990MHzです。fRF (fbl=2015MHz)から5dBmブロッカオフセット25MHzを注入し、215MHzに発生したブロッカの除去に190MHzのIFフィルタ(SAWTEK 855770)を使用すると、NblはAgilent E4404Bスペクトラムアナライザで-127dBm/Hzと測定されます。ブロッカがない場合、構成のノイズフロアはNtho = -134dBm/Hzにおいて測定されます。構成で使用されたIFアンプは、29.5dBの利得と2.5dBのNFを持っています。測定されたNthoは、実験構成におけるブロックの利得とNFを使用した計算値と一致します。
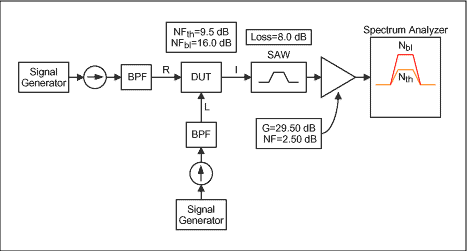
図5. ブロッキング条件におけるノイズ測定実験構成と の推測
の推測
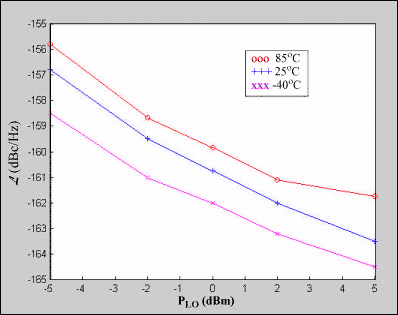
図6. MAX9982への局部発振器ノイズ( 、単位:dBc/Hz) 対 入力の局部発振器駆動電力を温度関数として表現
、単位:dBc/Hz) 対 入力の局部発振器駆動電力を温度関数として表現
ブロッカが存在する場合のノイズフロアの増大の原因は、NthoからNblへのミキサの信号対雑音比出力の劣化にあります。スペクトラムアナライザによって測定されたノイズフロア(Nbl)には、熱、相互混合ノイズ、SAW、およびIFアンプからのノイズ寄与が含まれます。測定された総出力ノイズ電力をカスケードブロック解析で説明するために、ミキサの効果的なNFは9.5dBから16dBに増大されています。合成ノイズ(Nbl)から、相互混合ノイズNrmiをミキサノイズの項で作成した各式を使って取り出すことができます。式3で表された信号対雑音比の低下は16dBです。式3のNrmiを求めると、次のような結果になります。
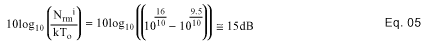
入力換算の相互混合ノイズNrmi = 15dBm/Hz - 174dBm/Hz = -159dBm/Hzです。5dBmのブロッカが使用されているため、 は-164dBc/Hzです。これは、-151dBc/HzのGSM要件より十分に下回っています。
は-164dBc/Hzです。これは、-151dBc/HzのGSM要件より十分に下回っています。
信号対雑音比(dBc/Hz)として定義されたLOノイズは、駆動信号がLOバッファによって制限されるため、LO駆動とともに変化します。これは2番目の例に示されています。
MAX9982は、セルラCDMA/GSM帯域(825MHz~915MHz)の高リニアリティミキサで、26dBm以上の入力IP3、3dBの利得、およびNF = 11dBを備えています。このミキサは、-5dBm~+5dBm範囲のLO駆動で動作可能です。大部分の規定は駆動信号によって変わりません。図6は、 (dBc/Hz)のプロットを駆動レベルの関数として示しています。この測定に使用される構成は、図5で示したものと同じです。IFにおけるブロッカ信号を減衰する(DUTで5dBm)ために、SAWTEK (854823)の86.6MHz GSM IFフィルタが使用されています。
(dBc/Hz)のプロットを駆動レベルの関数として示しています。この測定に使用される構成は、図5で示したものと同じです。IFにおけるブロッカ信号を減衰する(DUTで5dBm)ために、SAWTEK (854823)の86.6MHz GSM IFフィルタが使用されています。
結論
この記事では、基地局用ICミキサの設計規定における局部発振器バッファアンプノイズの役割が考察されました。単純なノイズモデルを使えば、ブロッキング条件下での総ノイズから相互混合成分を取り出すことができます。ブロッキング条件下における総出力ノイズの測定によって、2つの集積回路化された基地局ミキサの内蔵バッファアンプのLOノイズの特性が示されました。このデータを使って、ブロッキング条件下におけるレシーバ感度の損失を計算することができます。
参考文献
- Frequency Mixers Level 17 (www.minicircuits.comで入手可能)
- H. Wohlmuth and W. Simburger 「A High IP3 RF Receiver Chip Set for Mobile Radio Base Stations upto 2GHz」 IEEE JSSC、2001年7月
- H. J. Yoo and J. H. Kim 「The Receiver Noise Equation: A Method for System Level Design of an RF Receiver」 Microwave Journal、2002年8月、20~34ページ
- E. Ngompe 「Computing the LO Noise requirements in a GSM receiver」 Applied Microwave and Wireless、54~58ページ
- Draft GSM 05.05 V8.1.0 「European Telecommunications Standard Institute」 29ページ、1999年11月
- J. Lin et al 「A silicon MMIC active balun/buffer amplifier with high linearity and low residual phase noise」 2000 IEEE MTT-S Digest
- R. G. MeyerおよびA. K. Wong 「Blocking and Desensitization in RF Amplifiers」 IEEE JSSC、1995年8月
- Maxim Integrated のMAX9981、MAX9982、MAX9993
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}