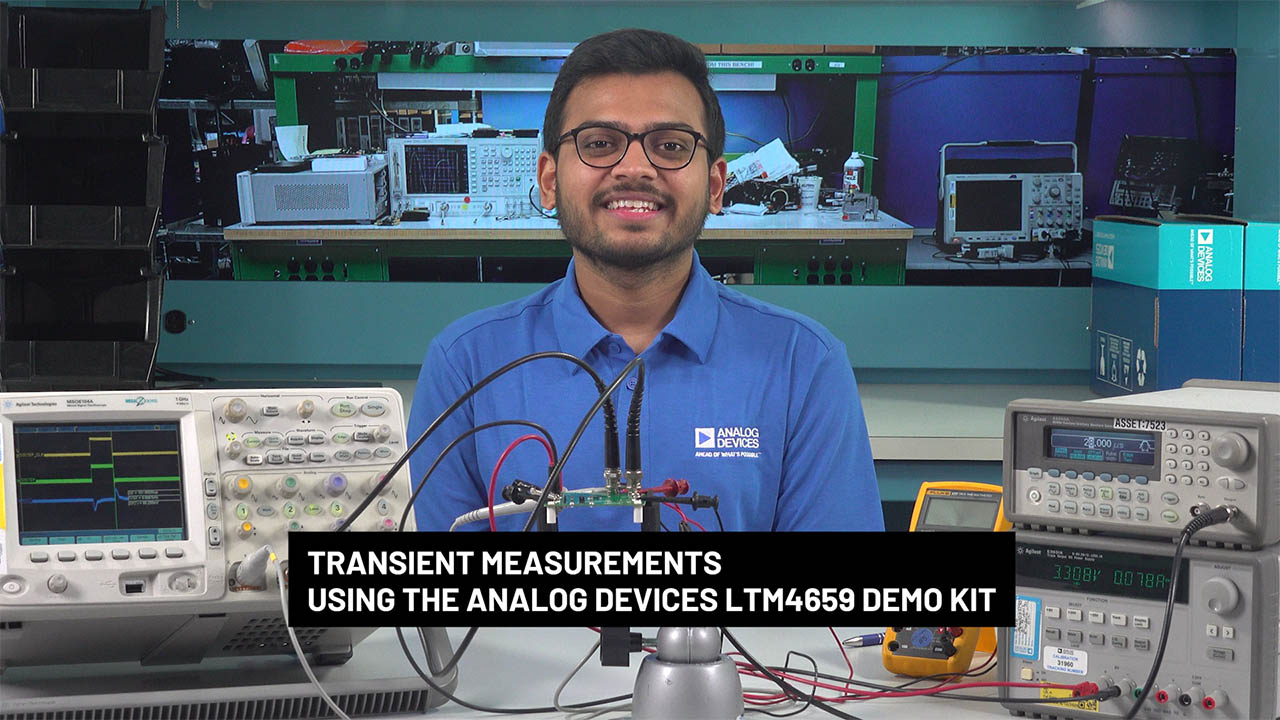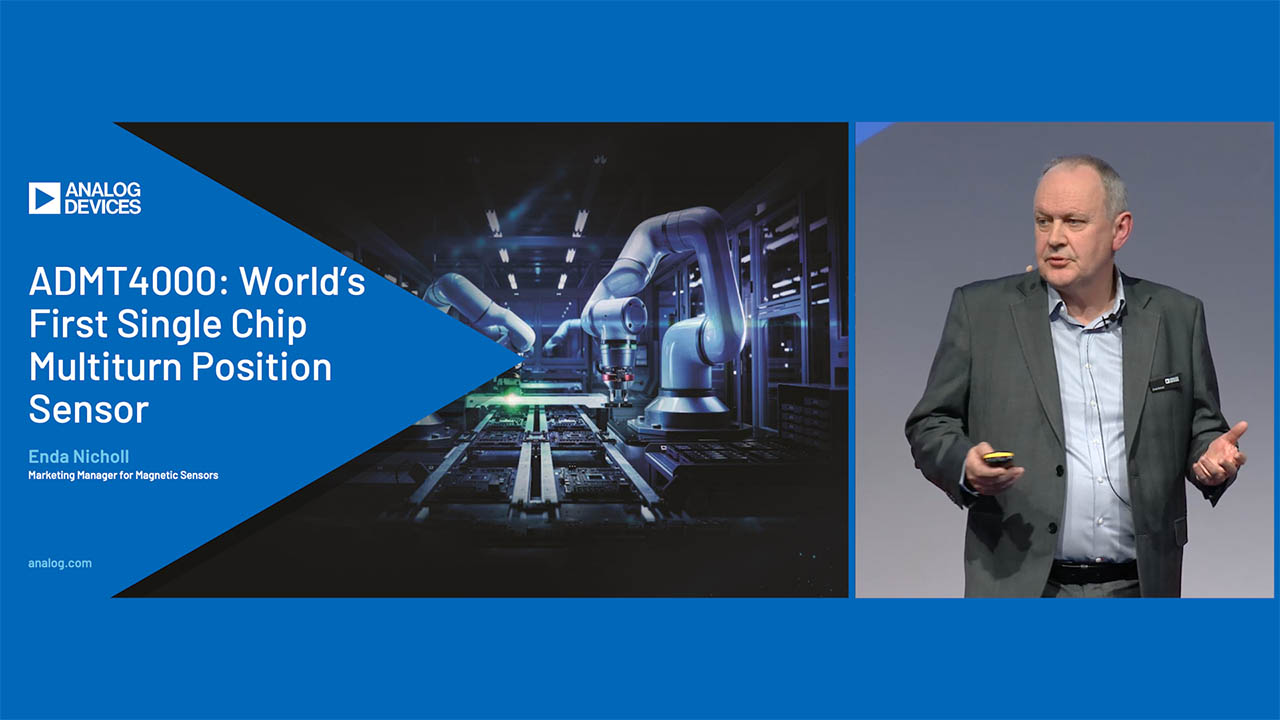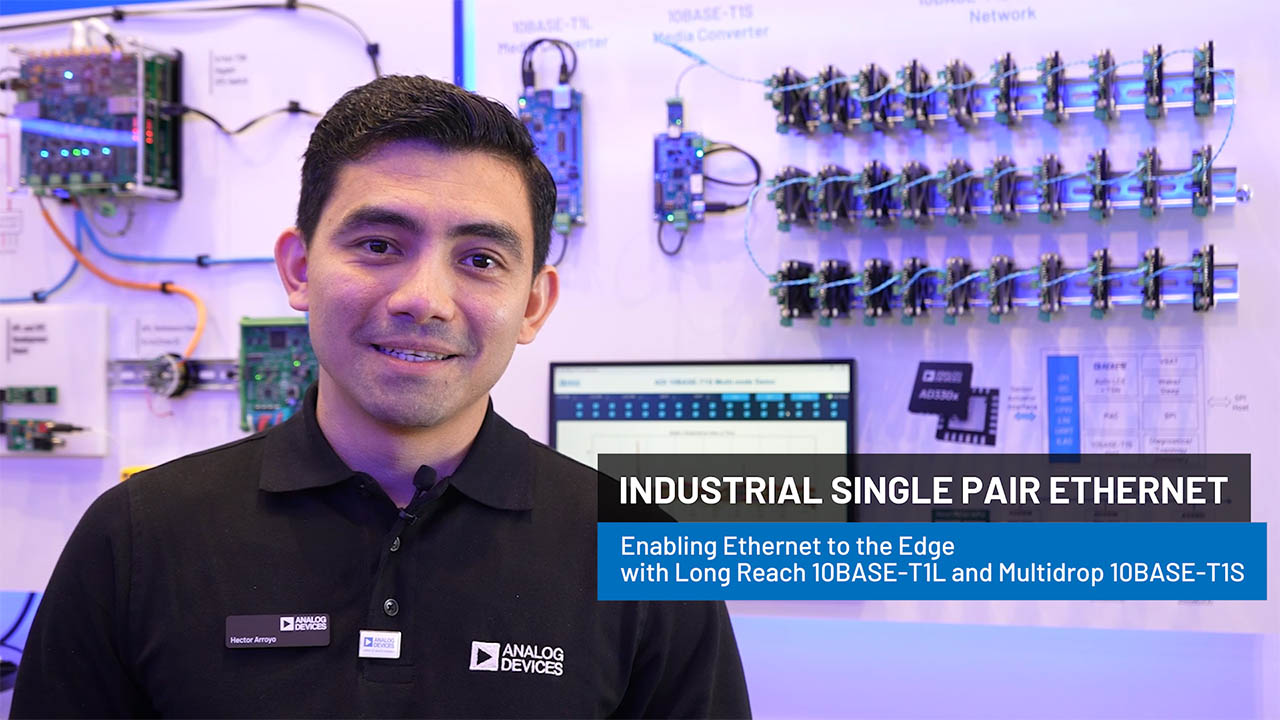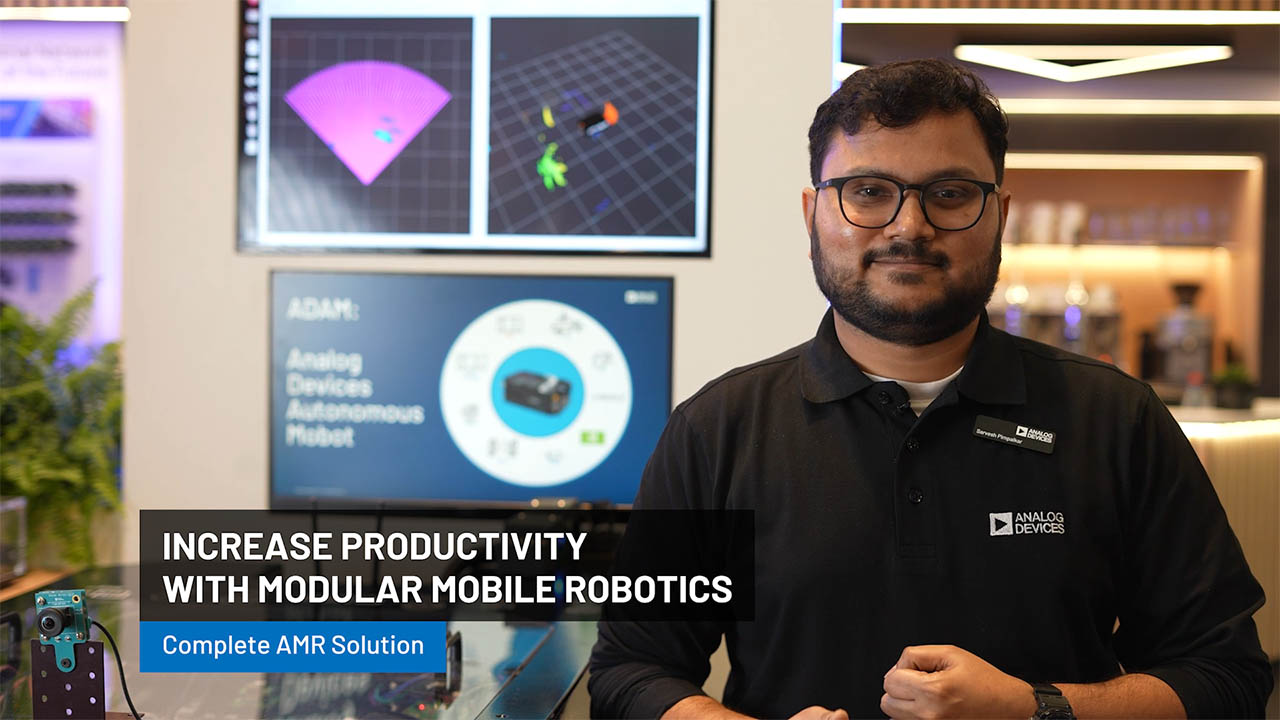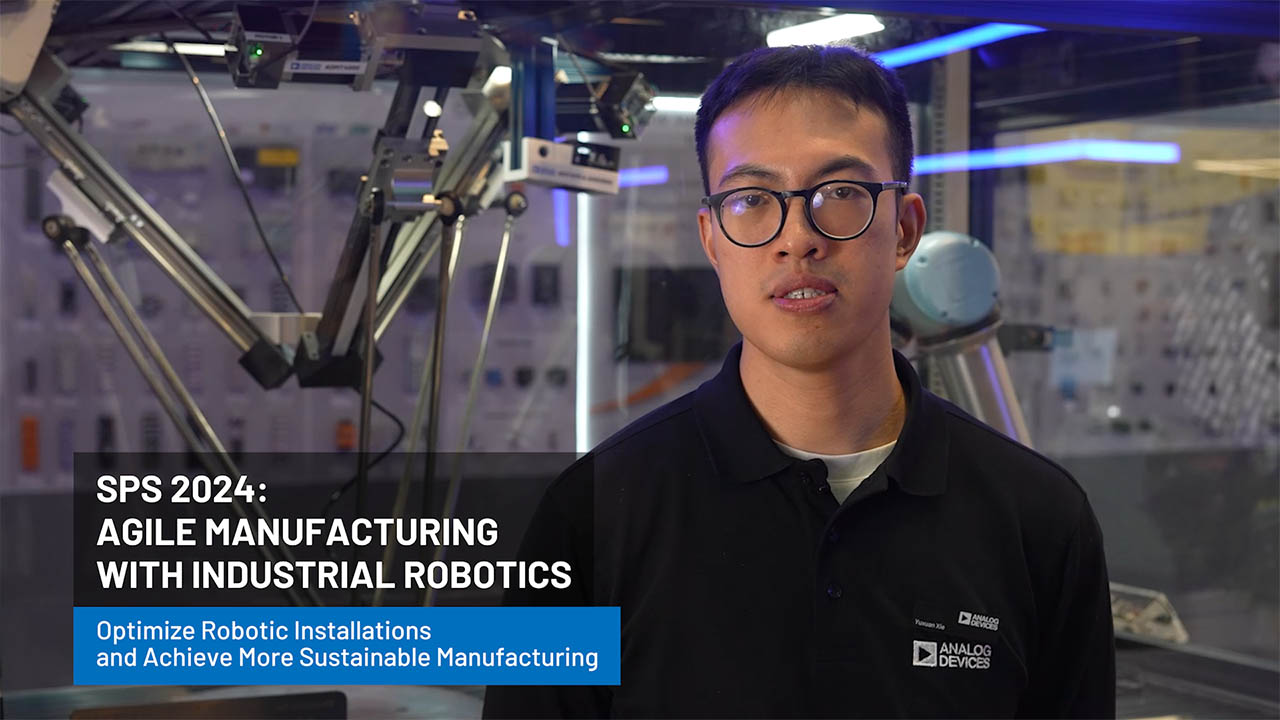要約
オペアンプが発明された結果、アナログ設計者の考え方には変化がもたらされました。現在、オペアンプは基本的なコンポーネントとして非常に広く用いられています。その結果、システムで使われる可能性のあるほぼすべてのオペアンプ回路は、既に誰かの手によって設計済みだと言えるような状態になりました。現在の技術者が行うべきことと言えば、回路で使用する部品の値を調整することくらいです。そのため、設計作業はかなり迅速に進むことになります。しかし、この状況には1つ大きな問題があります。それは、設計者が回路の動作理論を理解しているとは限らないというものです。ほとんどのオペアンプ回路の伝達関数は、節点解析法という簡単なプロセスによって導出することができます。本稿では、この手法について解説します。
オペアンプの基本
完璧な電子部品というものは存在しません。つまり、基本的な概念どおりの理想的な特性を示す部品は設計/製造できないということです。もちろん、オペアンプもその例外ではありません。オペアンプを扱う際には、設計プロセスにおけるどこかのタイミングで現実の世界に存在する限界のことを考慮しなければならなくなります。そのことは事実として押さえつつ、以下では理想的なオペアンプについて考えてみることにします。
まず、オペアンプの入力インピーダンスは無限大で、出力インピーダンスはゼロであると仮定します。また、オペアンプ回路のフロントエンドにとって、どのような形でもオペアンプ自身が負荷になることはないと仮定しましょう。そして、オペアンプの出力は、入力に忠実に応答するために必要なだけの電流をソースまたはシンクできるとします。このような仮定の下、負のフィードバックを適用したオペアンプについて考えると、次のような動作が得られます。すなわち、2つの入力の電圧は同一の値になり、その状態が維持されるように出力電圧が調整されるというものです。
加えて、オペアンプの帯域幅としては回路の要件に十分に対応できるだけの広さが確保されているとします。更に、オープン・ループ・ゲインは無限大であると仮定しましょう。
今日のほとんどのオペアンプ製品は、上記のように仮定して考察を進めても問題ないレベルの性能を達成しています。上述した理想的な条件からの隔たりは存在しますが、回路の性能に大きな問題が生じるケースは少ないと考えられます。
節点解析法
オペアンプが発明されるよりもはるか前に確立された理論があります。それはキルヒホッフの法則です。この法則は、電気回路の任意の節点(ノード)に流れ込む電流の総量と、その接点から流れ出す電流の総量は等しいというものです(実際には、同法則には前提となる条件が存在しますが、ここではそれは無視できます)。オペアンプ回路については、節点の列に分解して考えることが可能です。そして、各節点に対しては節点方程式が成り立ちます。それらの方程式を組み合わせれば、伝達関数を求められます。
ここで、オペアンプの入力について考えてみましょう。その入力ピンに向かって流れる電流の値は、ピンから離れる方向に流れる電流の値と等しくなります(入力インピーダンスが無限大だと仮定しているので、ピンに電流が流れ込むことはないからです)。ただ、オペアンプは電流をソース/シンクできるので、出力についても同じことが言えるわけではありません。
電流‐電圧コンバータ
図1に示したのは、簡単な電流‐電圧コンバータです。すなわち、電流を電圧に変換する機能を提供します。この回路の動作は、上で説明した節点解析法を使用すれば簡単に理解できます。オペアンプの反転入力に向かって流れる入力電流IINは、結果としてフィードバック抵抗Rに流れます。これが、反転入力から離れる側の電流となります。この電流により、Rの両端では以下の式で表される電圧降下が生じます。
V = IIN × R.
先ほど説明したとおり、反転入力の電圧は、非反転入力に印加される電圧と同じ値になります。これは、このオペアンプ回路に負のフィードバックを適用しているからです。結論として、反転入力の電圧はVREFに固定されます。この状態は、「反転入力は仮想接地(virtual ground)されている」と表現されます。この状態を維持するために、オペアンプはRを流れるIINの値に応じて出力電圧VOUTの値を絶えず調整します。VOUTの値は、入力電流がゼロのときにはVREFと等しくなります。IINの値が増加すると、VOUTの値はそれに比例して低下します。つまり、以下の式が成り立ちます。
VOUT = VREF - (IIN × R)

図1. 電流‐電圧コンバータ
差動アンプ
上記の内容を更に発展させてみましょう。図2に示したのは差動アンプの構成例です。

図2. 差動アンプ
この回路の伝達関数も、各節点に流入/流出する電流について考えることで導き出せます。まず、非反転入力ピンに向かって流れる電流について考えると、次の式が成り立ちます。

同様に、この節点から離れる方向に流れる電流は次式で表せます。

式01と式02から、次の式が得られます。

ここで、抵抗値の代わりにコンダクタンスを使用すると、式が簡素化されます(分数の使用を最小限に抑えられます)。つまり、次のような式が得られます。

ここで、R1とG1、R2とG2の関係は以下に示すとおりです。

コンダクタンスを導入した式を変形すると、次のようになります。

したがって、電圧V+ は次のように表せます。

反転入力のノードの節点方程式も、以下のように簡単に表せます。

ここで、伝達関数を得るために、以下の条件を使用します。

式03と式05を式04に代入すると、次の式が得られます。

これを変形すると、次のようになります。



つまり、この回路の出力は、2つの入力電圧の差とゲインを設定するための抵抗の値によって決まります。これは、予想どおりの結果だと言えます。
ウィーン・ブリッジ発振回路
節点解析法は、受動部品を含む回路の解析にも適用できます。上の例では、抵抗についてはコンダクタンスを使用して解析を進めました。それと同様に、受動部品については、アドミタンスを導入することによって式を簡素化することができます。ここでは、コンデンサの代わりにアドミタンスsCを導入することにします。その場合、ラプラス変換によって複素領域への変換を行った場合に対応する用語が用いられることに注意してください。そのような注意点はありますが、式が簡素化されると、絶大な心理的効果が得られるはずです。なお、回路の位相について検討したい場合には、sの代わりにjwを使用します。これについては後ほど実例を示します。
上述したとおり、受動部品を含む回路にも節点解析法を適用できます。そこで、図3に示したウィーン・ブリッジ発振回路の解析を行ってみましょう。この回路について考える場合、ほとんどの技術者は式を簡素化するために、まずはすべての抵抗の値とコンデンサの値が同一であるケースを想定するはずです。この回路には並列回路と直列回路の両方が含まれています。そのため、アドミタンスを使用してもリアクタンスを使用しても、式の複雑さに差はありません。以下では、ここまでの流れに従ってアドミタンスを使用することにします。

図3. ウィーン・ブリッジ発振回路
まず、式03から反転入力ピンの電圧は次のようになります。

ここで、2つのアドミタンスが直列に配置されている場合、トータルのアドミタンスはそれぞれの逆数の和の逆数になります(2つの抵抗が並列に接続されている場合と同様です)。一方、2つのアドミタンスが並列に配置されている場合には、トータルのアドミタンスは各アドミタンスの和になります。したがって、オペアンプの出力から非反転入力までのアドミタンスは次の式で表されます。

同様に、非反転入力ピンからグラウンドまでのアドミタンスは、次のようになります。

先ほどと同様の解析方法を使用して式の形を整えると、次のようになります。

ここで、s = jwとR = 1/Gを代入すると、次の式が得られます。

以上のように、節点解析法を用いることで、ウィーン・ブリッジ発振回路の伝達関数を導出することができました。この式からは2つの結論を導き出せます。それらはどちらもウィーン・ブリッジ発振回路の発振条件として広く知られています。
発振が生じる1つ目の条件は、入力から出力までの間に位相差がないことです。この条件は、1つの周波数でのみ成立します(w = 1/CRの場合)。この周波数では、分子の実数項が相殺され、分子と分母の両方の虚数項で表される位相のシフトが相殺されます(基本的に、分子にも分母にもjの項がなければ位相差は生じません)。2つ目の条件は、この周波数においてV+(すなわちV-)に対するVOUT比が3になることです。この比が3よりも小さい場合、発振の振動は減衰していきます。一方、この比が3よりも大きい場合には出力が飽和します。以上のことから、発振を維持するためのGfとGiの比が決まります。つまり、Rfの値は正確にRiの2倍でなければなりません。
まとめ
本稿では、節点解析法によってオペアンプ回路の伝達関数を導き出す方法を説明しました。具体的には、キルヒホッフの法則を用いて、オペアンプ周辺の各節点に流入/流出する電流に基づく式を導き出します。それらの式から伝達関数を導出することができます。本稿の例では、インピーダンスの代わりにアドミタンスを使用しました。ただ、原理は同じなので、どちらを使用するのかは技術者の判断に委ねられます。式を導出できさえすれば、(回路の複雑さにもよりますが)伝達関数を求めるための計算は基本的には難しくありません。得られた方程式に対して計算処理用のプログラムを適用すれば、様々な分析を実施できるはずです。例えば、どのような場合に動作が不安定になるのか、部品の値のバラツキによって回路の動作がどの程度左右されるのかといったことを、必要に応じて検討することが可能です。
なお、「New Electronics」の2002年12月号に、本稿と同様の記事が掲載されています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}