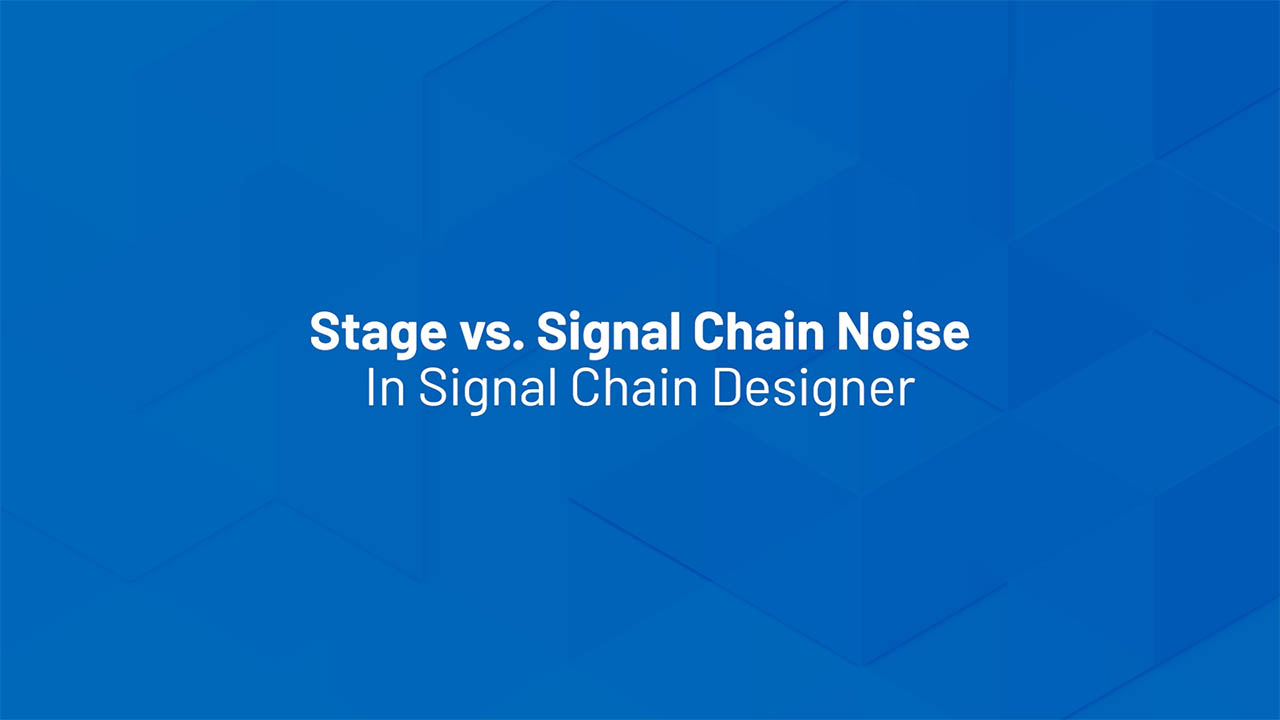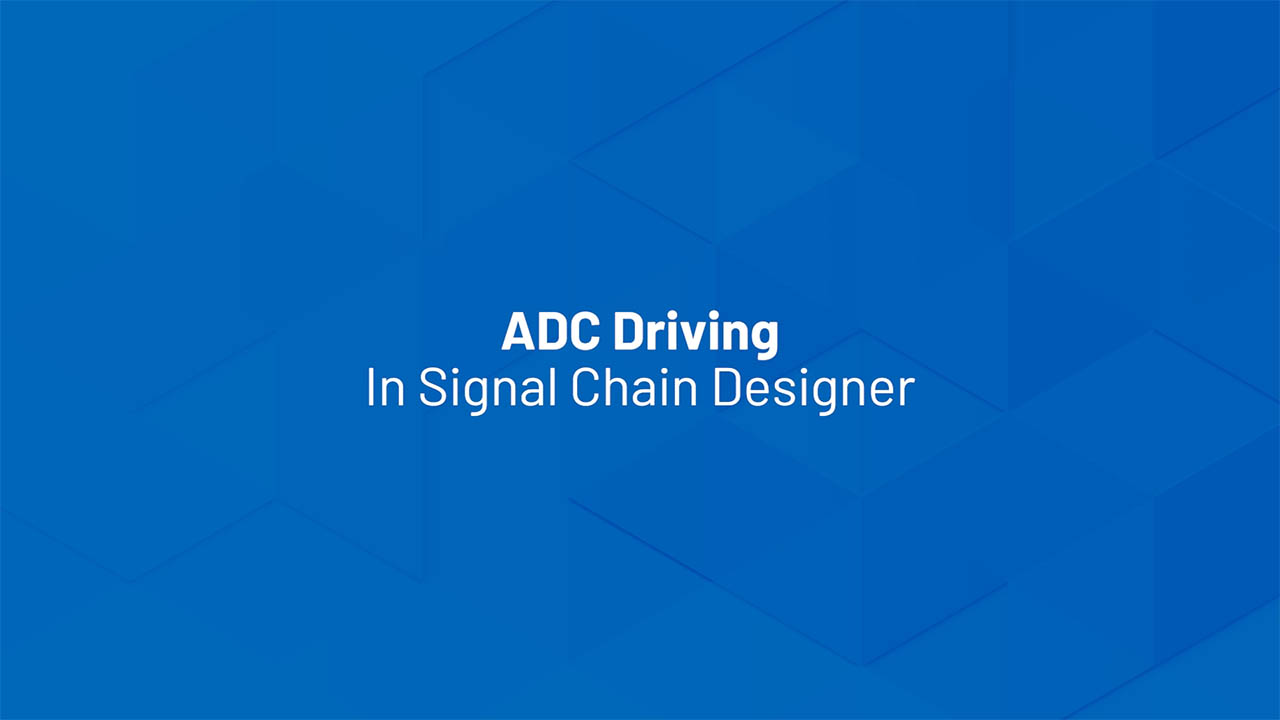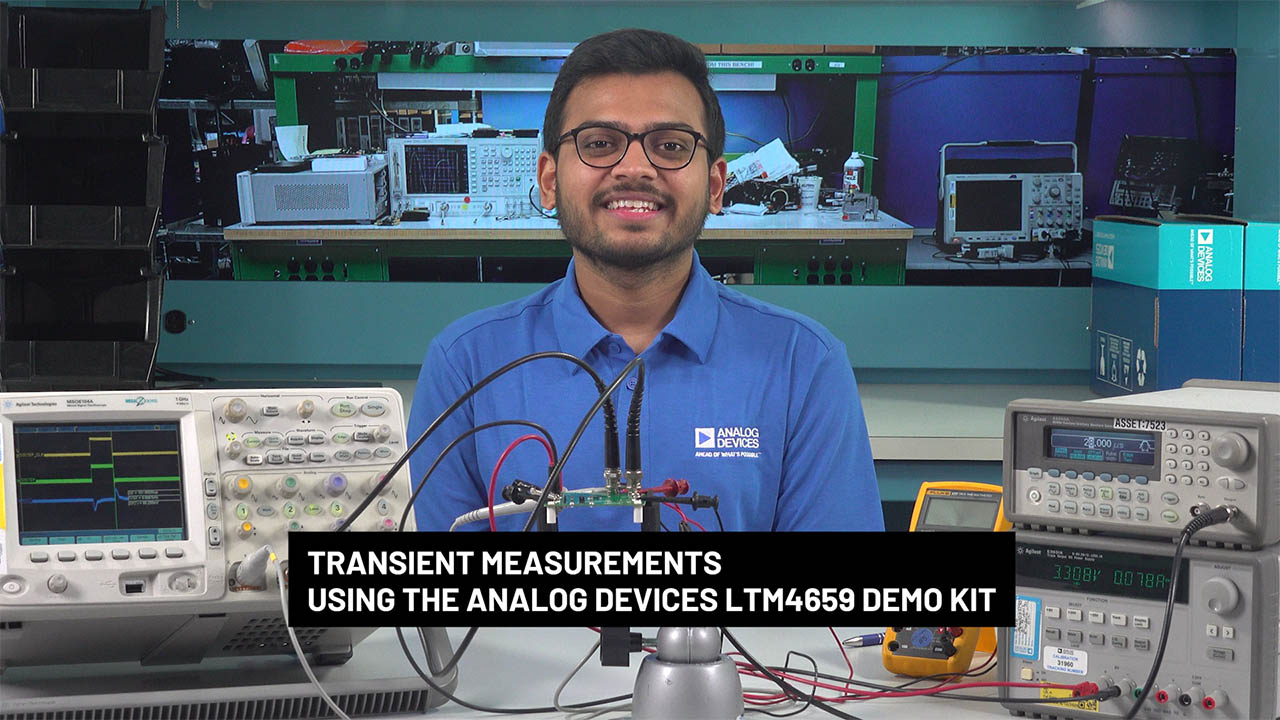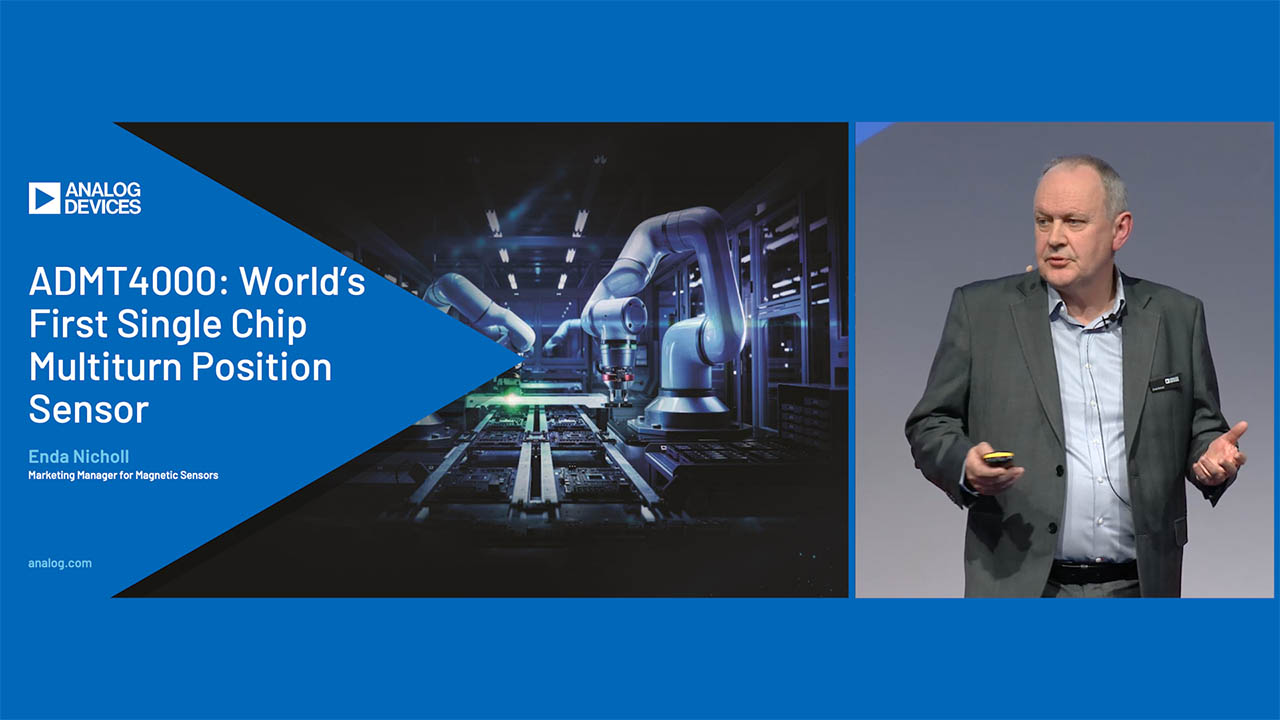要約
現在のノートブックコンピュータとポータブルDVDオーディオが抱える問題の1つに、利用可能なスピーカのダイナミックレンジが限られているという点があります。サイズの制約によってスピーカは小型のものであることが多く、したがって限られた周波数範囲でそれなりの音圧を生成することしかできません。このアプリケーションノートでは、小型スピーカに伴うオーディオの問題を除去する上で、自動レベル制御(Automatic Level Control:ALC)がどのように役立つかを説明します。
はじめに
オペレーティングシステムの警告音やそれに類するオーディオソースは、ユーザが動的ピークによる歪みの発生を心配せずにボリュームを上げることができるよう、ダイナミックレンジが十分に制限されているのが一般的です。しかし、比較的広いダイナミックレンジを持つDVDのサウンドトラックの場合は、ノートブックコンピュータ用スピーカの限られたダイナミックレンジによって、極めて明白な問題が発生します。会話と効果音の音量差が非常に大きい場合があるため、会話を聞くためにボリュームを上げ、大音量のシーンでは音割れを防ぐためにボリュームを下げるという操作を強いられるのです。
ボリュームの調整をしない場合は、動的ピークに対して高すぎる設定を選んで歪みを我慢するか、低すぎて会話が聞き取れない設定を選ぶか、どちらかの妥協が必要になります。小型スピーカを搭載したノートブックコンピュータは、このオーディオの問題があるため、DVDの視聴にはほとんど使えないものになる恐れがあります。
自動レベル制御の理論
自動レベル制御(ALC)を備えたアンプは、小型スピーカに伴うオーディオ音量の問題を除去する上で役立ちます。アンプは、電源電圧を大きくしない限り最大出力電圧を増大させることはできず、小型スピーカの許容入力を増大させることもできません。しかし、オーディオの再生中にRMS出力電圧を動的に変化させることはできます。オーディオ波形のピーク(あらかじめ定義されたスレッショルドより上の部分)を、残りのオーディオ信号に近いレベルに低下させれば、ピークでの音割れなしに全体の信号ボリュームを増大させることが可能になります。圧縮率の違いによって圧縮またはリミッティングと呼ばれるこの手法は、オーディオ業界全体を通して広く実践されています。
小さな圧縮率の場合(たとえば2:1では)、圧縮スレッショルドを超える信号について、入力における4dBの増分が出力では2dBの増分に減少されます。より大きな圧縮率(20:1以上)の場合は、一旦スレッショルドに達すると、入力の増分に関係なく出力波形は常に同一の振幅になるため、リミッティングと呼ばれます。圧縮は、録音とミキシングの段階で適用されるのが一般的ですが、もっと後のオーディオストリーム中で適用することも可能です。
MAX9756などのアンプで実装されているALCは、基本的にはリミッタと同様の働きをします。設定されたスレッショルドを超える出力信号を検出し、利得を減少させて出力をそのスレッショルド以下に保ちます。スレッショルドから上でのMAX9756の利得応答はほぼフラットであり、無限に近い圧縮率を示します(図1)。
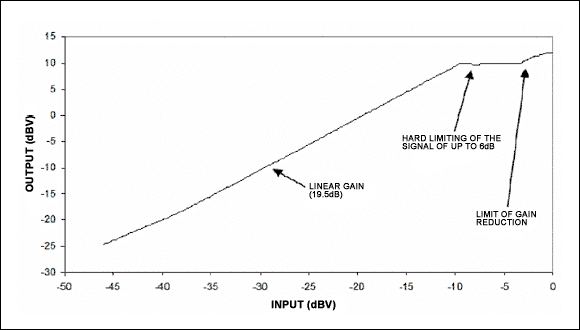
図1. 低いボリュームレベルに対して、このアンプは通常のリニアアンプとして動作します。スレッショルドを超えるレベルに対しては、利得を減少させ、出力がスレッショルドを超えるのを防ぎます。この利得低減は最大6dBに制限されており、それ以上の場合は出力電圧がスレッショルドを超えて増大することになります。
自動レベル制御のタイミング
信号の振幅の変化に対するリミッタの反応速度は、音質に劇的な影響を与えます。出力信号がスレッショルドを超えると、アンプはアタック時間によって規定される速度で利得を低下させます。その後、信号の振幅が減少するまで、低下したレベルに利得が保たれます。リリース時間は、アンプが利得を増大させ、最終的に元の値に達する速度を示します。MAX9756のようなアンプの場合、CT端子とグランドをつなぐコンデンサの値でアタック時間を指定します。次式によって、そのコンデンサの値からアタック時間が導かれます。
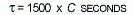
リリース時間はアタック時間に対する比率の形で計算され、DR端子に印加する電圧を変えることによって調整します。VDD、VBIAS、またはGNDをDR端子に印加することによって、3種類の比率の中から1つを選択することができます。MAX9756は、すべてのリリース時間の値に50ms固定のホールド時間を加算します。ホールド時間の間は、利得の調整は行われません。
図2は、全体的に振幅の小さな信号の中で、大きな信号パルスが発生した場合の影響を示しています。出力波形の中の大きなパルスの振幅は、利得の立下りに伴って明らかに減少しています。利得低減制御電圧とは、CTのコンデンサ両端にかかる電圧であり、それによってアタック時間が設定されます。その電圧は、特定の時点における利得の低減(dB)に比例します。
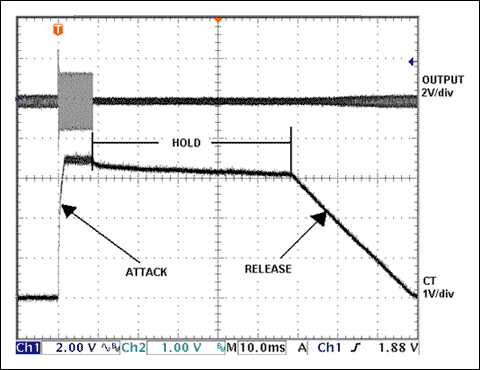
図2. 短く大きな信号を印加することによって、ALCの全サイクルを見ることができます。MAX9756アンプのホールド時間は50msに設定されており、アタック時間とリリース時間は外付け部品で調整することができます。
アタック時間とリリース時間の長さは、音源の素材と希望する効果に応じたものにする必要があります。たとえば、これらの時定数を短くするとALCは信号レベルの変化に迅速に追従するようになり、信号レベル中の最も短いスパイクに対しても防護効果を発揮します。この動作によって、大きな信号がスピーカを損傷しないことは保証されますが、その一方で、信号の動きに合わせて利得が急速に調整されるため、「ポンピング」や「ブリージング」などの人為的雑音(アーチファクト)が聞こえるようになる可能性もあります。
信号レベルが絶えず変化する映画のサウンドトラックの場合、より長い時定数によって人為的雑音を防ぎ、最高の音質を得ることができます。その場合の利得は、信号レベルが急速に変化している間も比較的固定した値に保たれ、変化が長期的でアンプが反応するのに十分な時間がある場合にのみ調整が行われることになります。損傷につながる恐れのある信号のほとんどは依然としてALCによって低減されるため、スピーカの保護が損なわれることはありません。
利得低減制御電圧と信号の波形を監視することによって、長短それぞれのアタック時間とリリース時間の影響を見ることができます(図3)。典型的な波形を示すため、入力信号はフルボリュームのオーディオ信号にしてあります。短いアタック時間とリリース時間の場合、全体として比較的一定の信号強度を持つ部分で頻繁に利得の調整が行われます。より長いアタック時間とリリース時間の場合は、スムーズな利得応答が確保され、アンプの過剰反応が防止されます。こうして全体としての信号レベルが維持され、信号の動きがより忠実に保たれます。
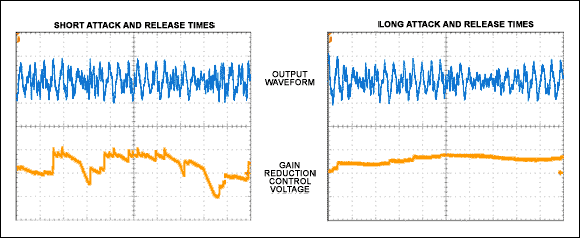
図3. 短いアタック/リリース時間(a)の場合、頻繁に利得が変化して音質が劣化する恐れがあります。より長いアタック/リリース時間(b)の場合、よりスムーズな利得応答が得られます。
ALCのスレッショルド
ノートブックコンピュータのスピーカアンプは、5V電源で動作するのが一般的です。8ΩのスピーカをBTL (bridge-tied load)構成で駆動する場合、理論上の最大連続許容出力は次のようになります。
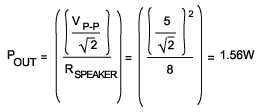
5V電源であるため、負荷により多くの出力を供給しようとすると、波形がクリッピング歪みを起こすことになります。MAX9756のようなアンプでは、PREF端子をグランドに接続する抵抗を選択することで、利得低減のスレッショルドを調整することができます(MAX9756は12µAの定電流を抵抗に流します)。次式によってこの抵抗の値を(この場合は1.4Wのスレッショルド用に)計算することができます。
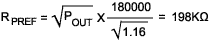
スレッショルドは、RPREFの値を調整することによって任意のレベルに変更することができます。場合によっては、スピーカの許容入力によってサウンドシステムが制限されます。そうした場合、スレッショルドをアンプの最大出力よりもかなり低く設定して、絶対に許容入力を超えないようにすることができます。スピーカの許容入力がアンプの最大出力を上回っている場合は、スレッショルドをクリッピングレベルのすぐ下に設定することによって、最高の音質を得るとともに、スピーカを長期的な損傷から保護することができます。クリッピングした波形は単に音が悪いだけでなく、いずれはスピーカに永続的な損傷を与える可能性があります。クリッピングした波形の鋭いエッジは、スピーカの機械的要素にとって再生が困難であり、長期的には障害の原因になる恐れがあります。
図4は、アンプの最大出力のすぐ下にスレッショルドを設定した場合の効果を示しています。入力信号は、ハイレベルとローレベルの間を交互に遷移する正弦波バーストです。アタック時間の間、出力波形は明らかにクリッピングを起こしていますが、利得の低減が完了するとすぐにクリッピングが終わっています。
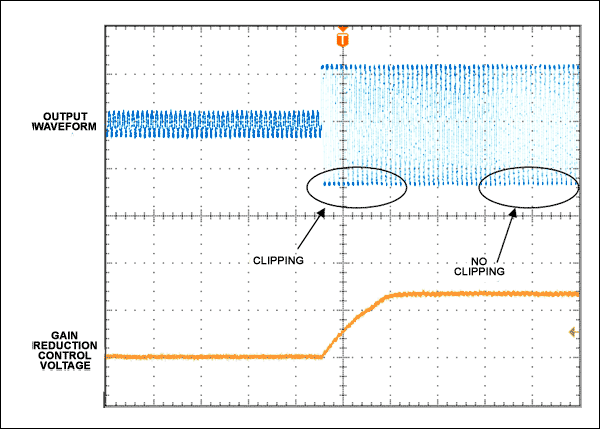
図4. この小さな信号から大きな信号への遷移過程では、最初は出力波形がクリッピングを起こしています。利得低減の立上りに連れて、希望通りクリッピングのない状態に出力波形が戻っています。
圧縮率の低減
MAX9756で提供されているリミッティングは、スピーカの保護とクリッピングの防止に役立ちますが、ALC動作中の動的変化が完全に排除されます。圧縮率無限が意味するのは、入力信号の強度が増大しても出力にはまったく影響せず、結果として精彩を欠く単調なオーディオサウンドが生成されるということです。出力波形の厳密な制御が必要でない場合は、圧縮率を低減することで、一定の動的内容を維持したままクリッピングを防止するのに役立ちます。圧縮率を下げると、オーディオ信号の動きが完全に排除されるのではなく、減少することになります。MAX9756の圧縮率は、図5に示すように、外付け回路の付加によって低減することができます。
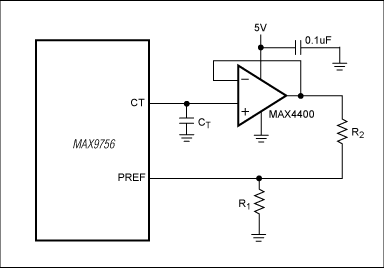
図5. MAX4400などのオペアンプと抵抗R2をMAX9756の外付け回路に追加することで、ALCの圧縮率を低減することができます。
MAX4400オペアンプは、MAX9756のCT出力に対するバッファとして機能し、追加した回路がCTの電圧に影響を与えないこと、ひいてはリリース時間に影響を与えないことを保証します。MAX4400の標準入力インピーダンスは1000GΩであり、漏れ電流によってコンデンサが途中で放電される恐れがありません。オペアンプの出力はR2を通してPREFに与えられます。こうして、R1とR2の並列組み合わせによって新しいALCスレッショルドが決まります。この構成では、次式によってスレッショルドが決定されます。
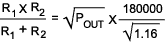
スレッショルドに達する直前の段階でPREF端子に現れるインピーダンスは、その時点でR1とR2の両方がGNDに接続されているため、両者の並列組み合わせになります。こうして、この並列組み合わせの設定によって、この構成におけるALCのスレッショルドが設定されます。右辺はRPREFを計算するための先ほどの公式(式3)であり、左辺はR1とR2の並列組み合わせの抵抗値の式(式4)です。
R2とR1の比が、新しい圧縮率に寄与します。R2がR1よりはるかに大きいと、ALCはMAX9756の標準のハードリミッティング構成に似た高い圧縮率を持つことになります。R2がR1より小さいとALCの圧縮率は低くなり、オーディオ信号が持つ本来のダイナミックレンジがほぼ維持されます。したがって、有益な圧縮率の一例である3:1を実現するには、R2をR1の値の2.5倍に設定します。図6に、標準のリミッティングとR2/R1 = 2.5の結果得られる圧縮率について、MAX9756の電圧利得に対する影響を示します。
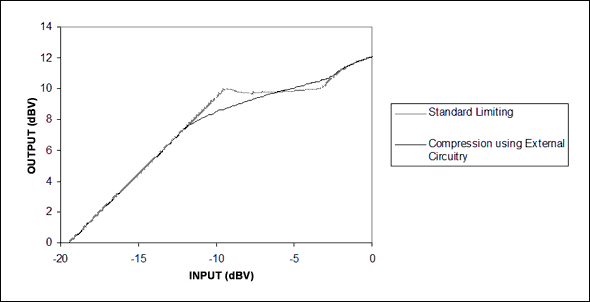
図6. MAX9756の標準のリミッティングと、外付け回路で実現した圧縮とを比較すると、利得の調整がより連続的であり、水平部分がないことが分かります。
ALCによる改善効果
ALCによる改善効果は顕著です(図7)。グラフ(A)は、DVDの映画の中で特に大音量の部分におけるALCなしの出力波形を示しており、グラフ(B)は同じ入力と同じボリューム設定でALCを有効にした場合の出力波形を示しています。
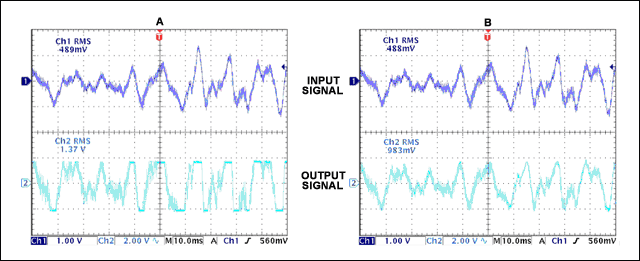
図7. ALCなし(A)では、入力信号の強さが原因で出力が激しくクリッピングしています。同じ入力波形に対してALCを有効化した場合(B)、出力波形のクリッピングが除去されています。
ユーザがボリュームを調整する際に、会話が聞き取れるレベルに合わせても、他の部分が大音量になりすぎる心配はありません。それ以上に、クリッピングが発生しにくいため、音質も良くなります。さらに、ALCは(クリッピングの減少によって)スピーカの寿命を延長し、低出力スピーカの保護にも役立ちます。最大ボリューム設定は、同じシステムでALCなしの場合に比べて6dB高くなります。
ALCは、ディジタル方式で実装することも可能です。恐らく既存のDSPハードウェアで実現することも可能であり、マルチバンド圧縮などの高度な処理を行うことによって、音質とスピーカ保護をさらに改善することができると思われます。ディジタル領域のALCは確かに便利ですが、より多くのサイクル数と、恐らくより多くの電力を要求するため、DSPシステムにとって負担になります。ここで示したように、アナログALCをスピーカアンプに取り入れる手法は、バッテリ寿命が最優先であり伝統的に音質が犠牲にされてきたノートブックコンピュータとポータブルDVDプレーヤにとって、優れた妥協点と言えます。
類似の記事がPortable Design誌2005年11月号に掲載されています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}