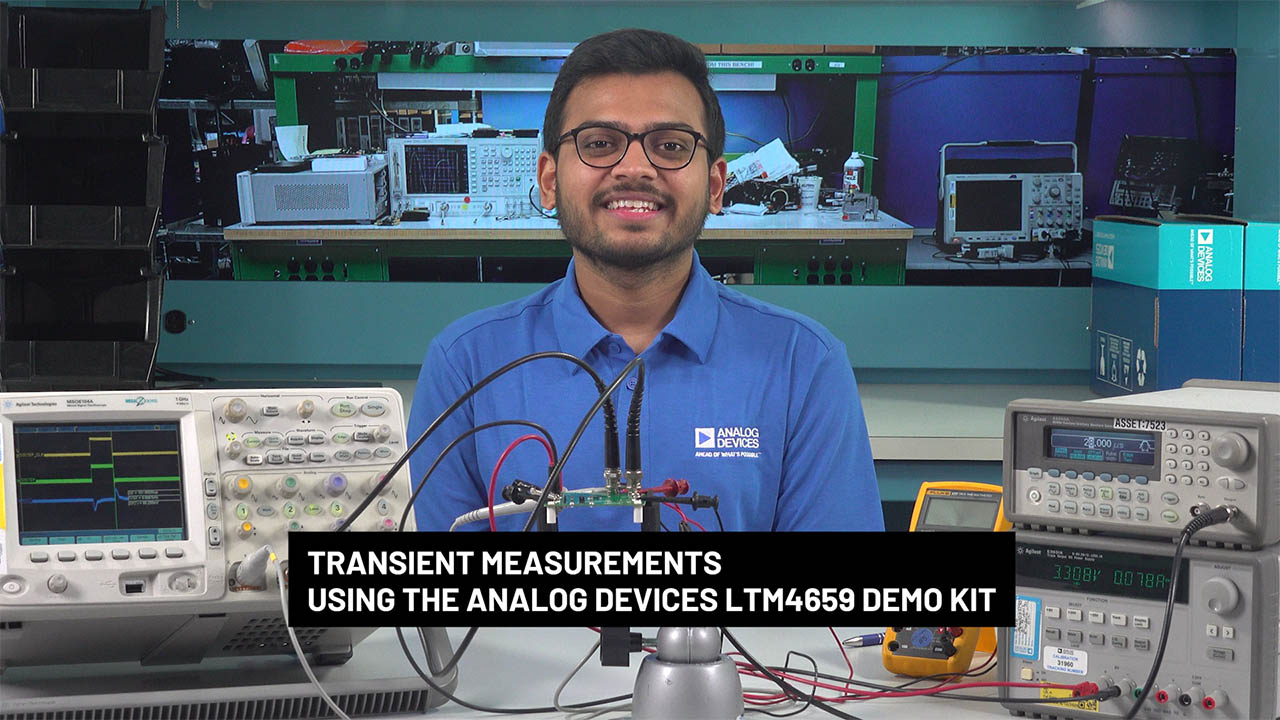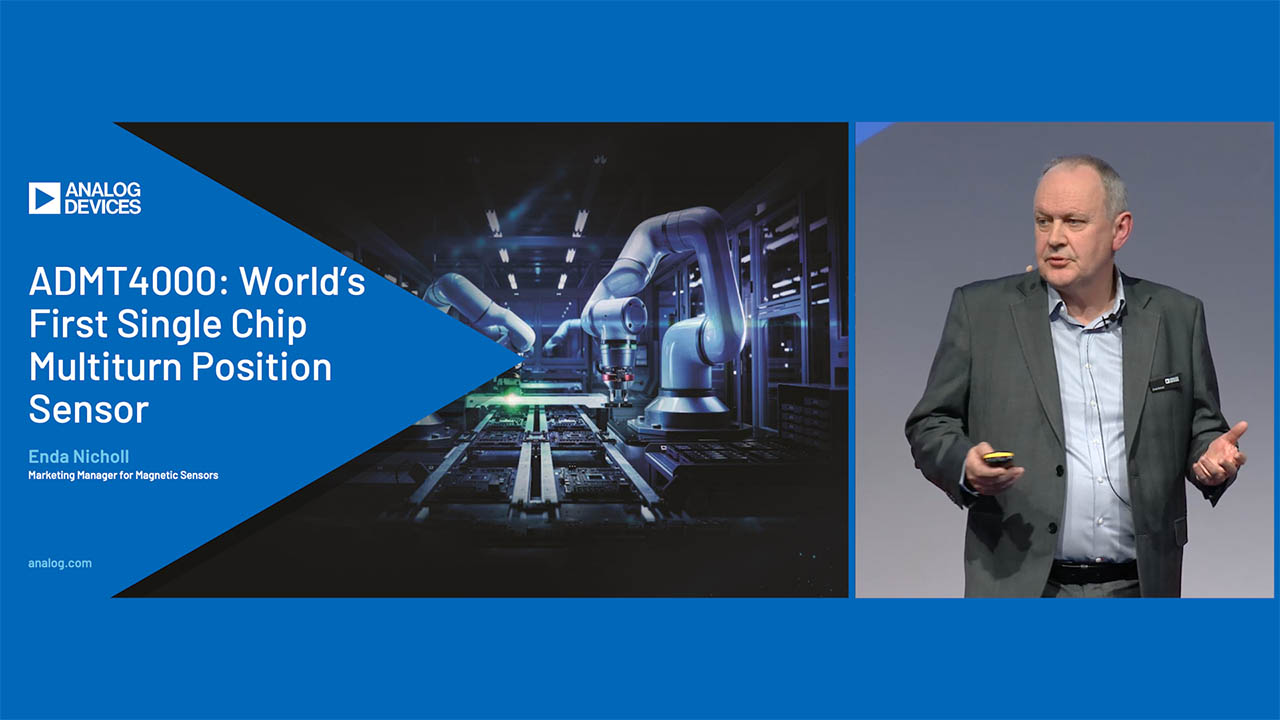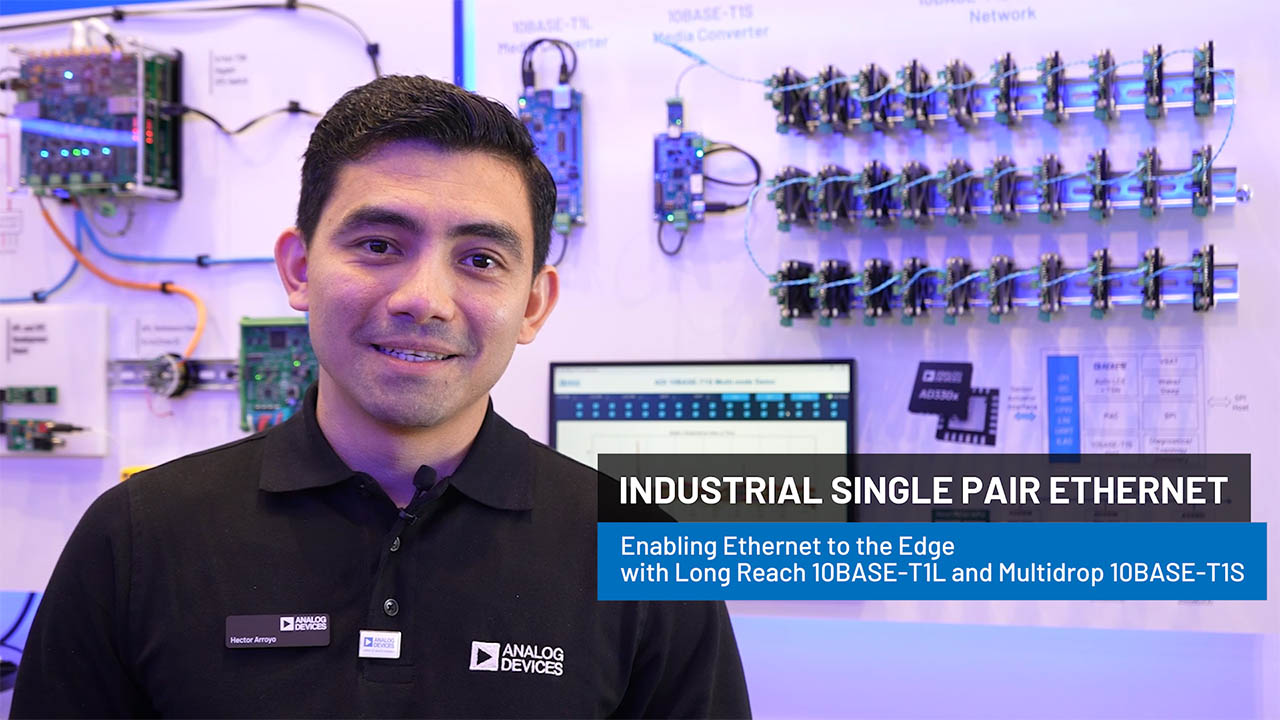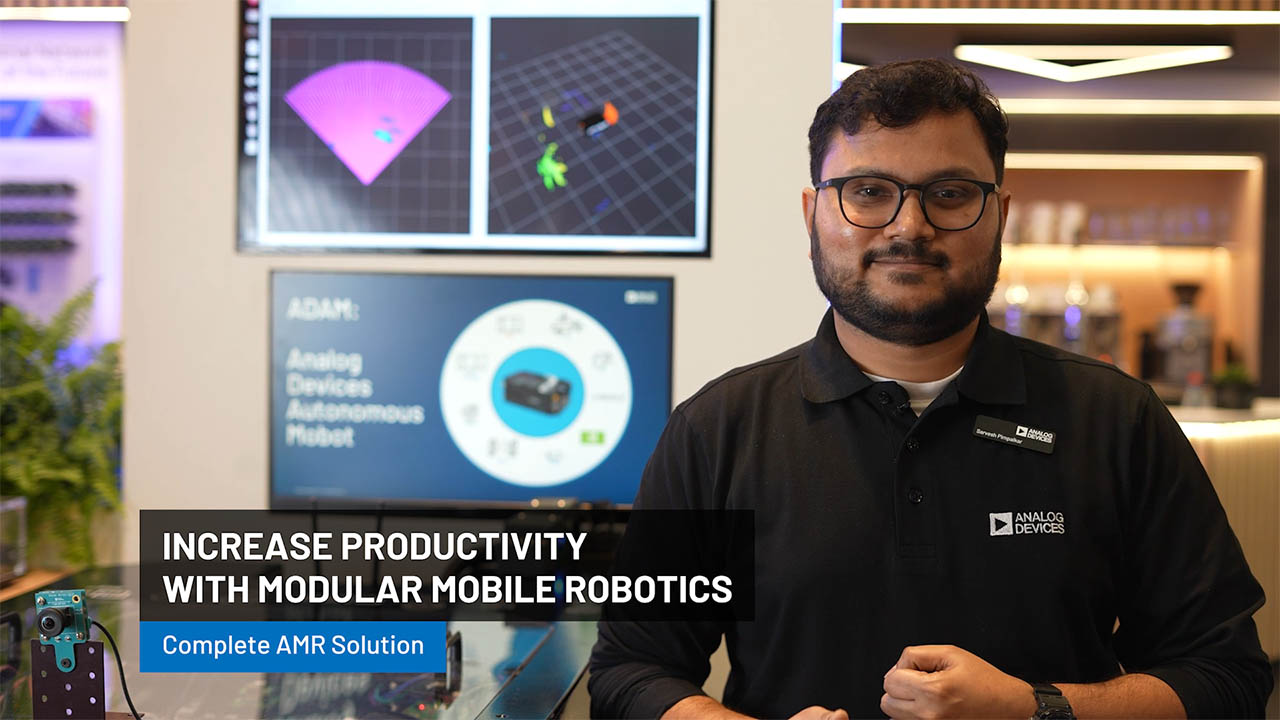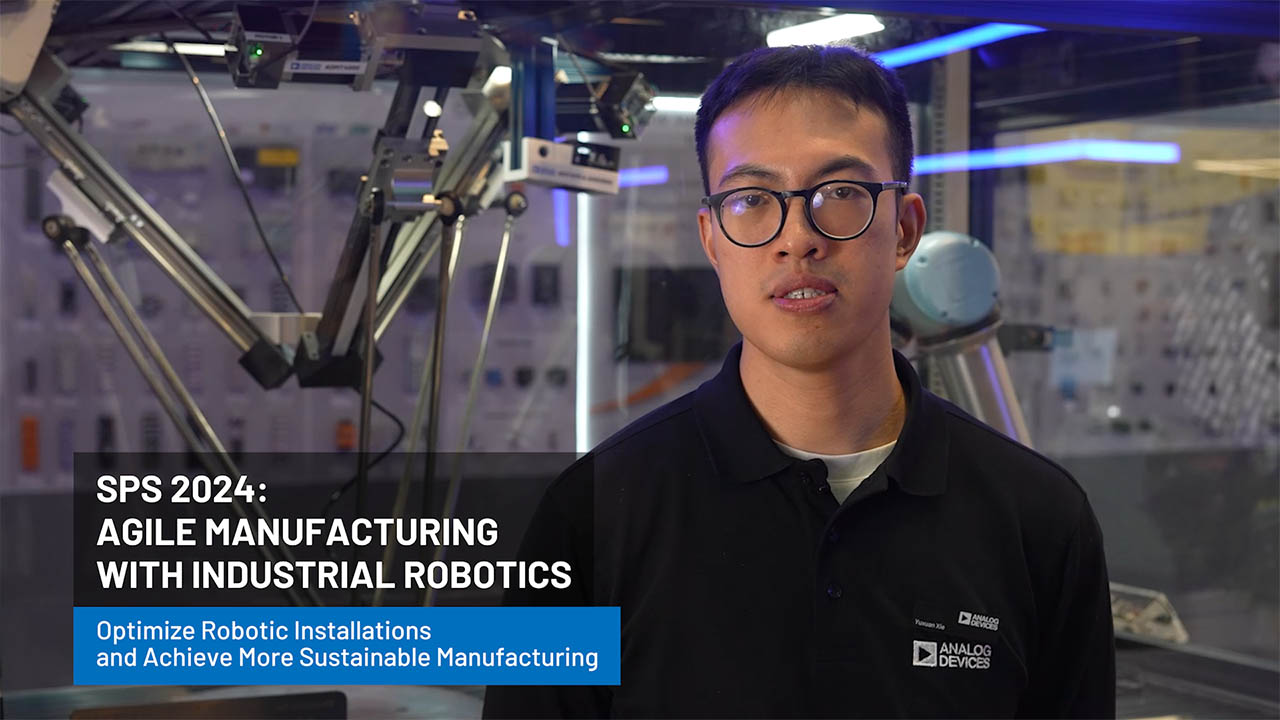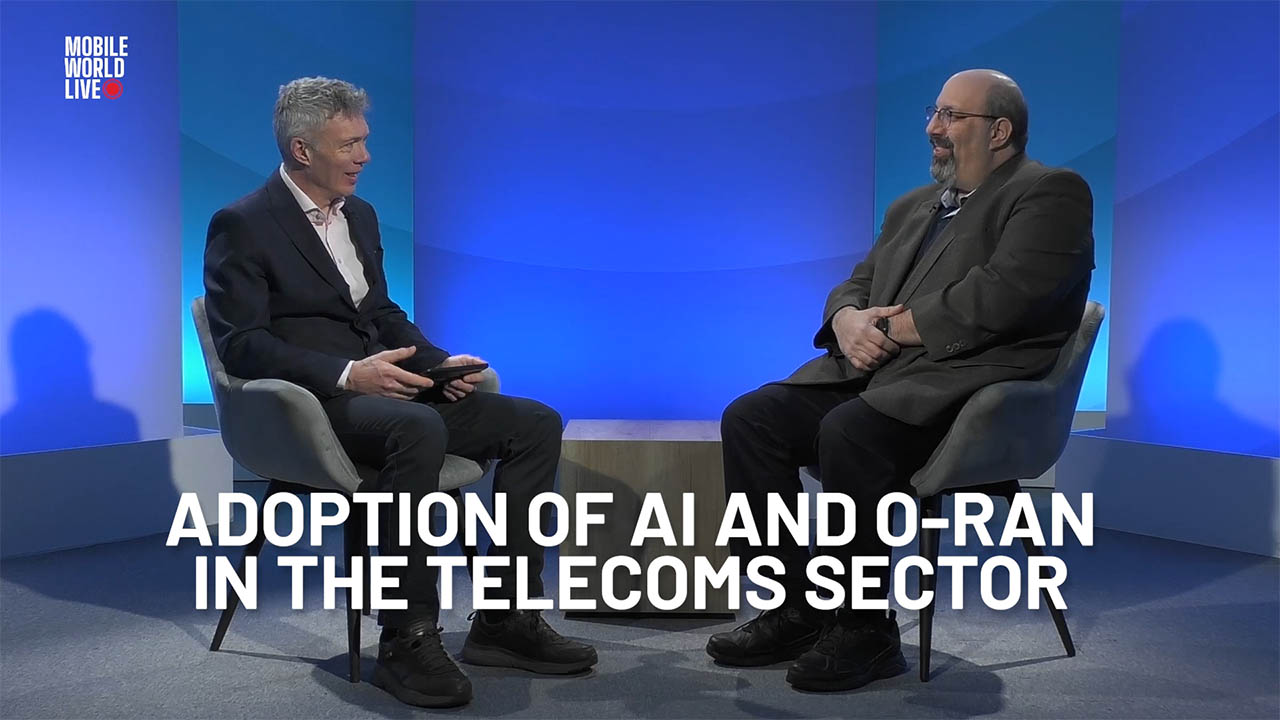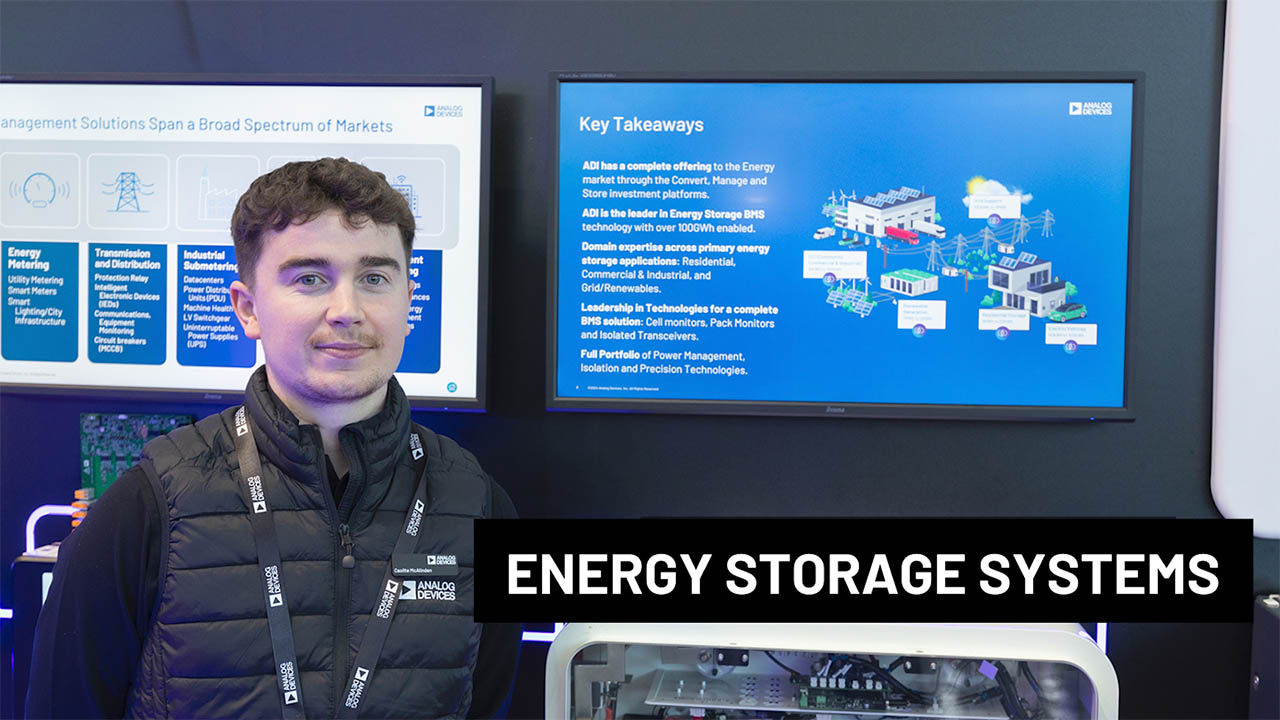加速度センサーの動作が不安定で困っています。何が問題なのか見当もつきません
質問
現在、加速度センサー「ADXL001」を使って測定を行おうとしています。ところが、加速度を与えない状態でもノイズのような異常な値が出力されてしまいます。回路設計の経験がほとんどないので、なぜこのような不安定な動作になるのかまったくわかりません。原因と対策について教えていただけないでしょうか?
回答
このような質問を受けてアナログ・デバイセズの技術者が最初に示したアドバイスは、「まずは、データシートに記載されているADXL001自体のノイズ性能と測定値を比較してみてください」というものでした。
同ICを5Vの電源電圧で動作させた場合、10Hz~400Hzにおいて、ノイズの大きさが55mg rms、ノイズ密度が2.15mg/√Hzという仕様になっています。ここでいう「10Hz~400Hz」の意味は、ADXL001の出力を10Hzから400Hzの範囲で帯域制限し、その範囲内におけるノイズのレベルを仕様として規定しているということです。周波数軸で見て、矩形状に帯域を制限することが可能なフィルタがあったとします。その下限、上限の周波数がそれぞれ10Hz、400Hzであるということです。この帯域内でノイズを観測すると、先ほど示したmg rms、mg/√Hzを単位とする値が得られるということになります。
データシートでは、上記のように完全に矩形な応答を示すフィルタを使って帯域制限した場合の数値を示しています。しかし、実際にはそのようなフィルタを構成することはできません。そこで、実際には1次のRCローパス・フィルタで代替して測定が行われます。具体的には、-3dB周波数が255Hz(= 400/1.57)の1次のローパス・フィルタを使用します。ここで1.57というのは、矩形フィルタとRCローパス・フィルタの周波数の関係を考えた場合の補正係数です。つまり、-3dB周波数が255HzとなるRCローパス・フィルタを使用すれば、400Hzの矩形フィルタに相当する帯域幅を実現できるということです。
このローパス・フィルタは、ADXL001の出力に接続します。つまり、f = 1/2πCRに対応する抵抗Rを直列に接続し、コンデンサCを並列に接続します。ここで、ADXL001のデータシートには出力に接続するコンデンサとして1000pFという値が示されています。ただ、これはEMI(電磁妨害)対策のためのものです。また、1000pFというのは出力に直接接続できる容量の最大値でもあります。ローパス・フィルタを構成する場合、抵抗Rによって分離されるため、Cの値を1000pF以上にしても即座に異常な動作を示すというわけではありません。ただ、RとCの値についてはある程度適切な関係で選んでおくべきです。なお、f = 1/2πCRのfが上述した-3dB周波数になりますので、この測定の前提となる等価帯域幅はその1.57倍の値になります。
ここまで400Hzという上限値に注目して説明を行ってきました。厳密に言えば、下限値である10Hzに対応するフィルタ(ハイパス・フィルタ)も必要です。ただ、この低域側については考慮しなくても、現実的なレベルでノイズを観測できるはずです。つまり、上述したローパス・フィルタを付加するだけで、55mg(に相当する電圧のRMS値)が計測されるでしょう。ただし、ノイズの波形はガウス分布的なものになるので、観測されるピーク値はその6倍程度(330mg pk)に達すると考えられます(図1)。
このレベルで収まっていれば、IC自体が発生するノイズが支配的であると考えられます。一方、それを超える値が出力されている場合には、外来ノイズが原因で出力が不安定になっていると推測されます。その場合、例えば電源をよりクリーンなものにしたり、余計な振動が加わっていないか確認して対応を図ったりといった具合に、様々な方向から工夫を施して、どのような変化が見られるか確認していくとよいでしょう。なお、後段に配置するフィルタによって帯域を狭くすれば出力されるノイズも削減されます。つまり、必要な帯域まで帯域制限を施すというのも1つの手です。

以上のように、アナログ・デバイセズの技術者からは、ノイズの正体を突き止める方法といくつかの対処法が示されました。一方で、別の投稿者からは「あるメーカーの加速度センサーを使用したときに同じような問題に悩まされたことがある」という話が寄せられました。その内容は以下のようなものでした。
この投稿者の場合、ハム・ノイズが原因で異常な値が出力されるという問題に直面したそうです。ハム・ノイズの影響とは、商用交流電源である50Hz/60Hzの周波数信号がノイズとして出力に現れるということです。これについては、オシロスコープで観測しただけでも原因を推測できるケースがあるようです。なお、最近ではサンプリング型のデジタル・オシロスコープが主流になっているので、低いレンジで観測していると、高い周波数信号が低い周波数信号に折り返し(エイリアス)として現れてしまうので、その点には注意が必要です。
以上のようなアドバイスを受けた質問者は、実際にローパス・フィルタを構成/付加してセンサーの出力を観測してみました。その結果、ハム・ノイズの影響が非常に疑わしいということがわかりました。このハム・ノイズの影響を回避するための方法として、先の投稿者からは次のようなアドバイスが送られました。
多くの場合、ハム・ノイズは周辺から静電誘導(電界)の形で混入します。例えば、回路が鉄製の机の上に置かれているなら、そこから混入することが少なくありません。静電シールドを施してみてノイズが小さくなるようであれば、そこに原因があると考えられます。具体的な処置としては、回路全体の下に金属板を敷き、それを回路のグラウンドにつなぎます。可能であれば、グラウンドに接続された金属の箱の中に回路全体を入れるとさらによいでしょう(箱の上側は開いていても構いません)。それによってノイズが小さくなるようであれば、恒久的な対策を考えます。例えば、センサーの下に広めのグラウンド・パターンを設けるといった具合です。実験室の机は鉄製であることが少なくありません。そのため、この種のトラブルは頻発する可能性があります。実際、この投稿者の場合、静電シールドを設けることでハム・ノイズによるトラブルを10件ほど解決したことがあるそうです。
なお、本稿で取り上げたADXL001は、第5世代のiMEMS®技術を適用した製品です。高性能、広帯域幅、低消費電力、小型、堅牢といった特徴を備えており、産業用機器や医療用機器などに適したものでした。この品種自体はすでに製造中止となっていますが、アナログ・デバイセズはその流れをくむ加速度センサーを続々と製品化しています。それらの製品を使用する際にも、本稿で紹介した内容は必ず役に立つはずです。ぜひ参考にしてください。
アナログ電子回路コミュニティとは
アナログ電子回路コミュニティは、アナログ・デバイセズが技術者同士の交流のために提供していた掲示板サイトで、2018年3月に諸般の事情からサービスを終了しました。
アナログ電子回路コミュニティには日々の回路設計活動での課題や疑問などが多く寄せられ、アナログ・デバイセズのエンジニアのみならず、業界で活躍する経験豊富なエンジニアの皆様からも、その解決案や意見などが活発に寄せられました。
ここでは、そのアナログ電子回路コミュニティに寄せられた多くのスレッドの中から、反響の大きかったスレッドを編集し、技術記事という形で公開しています。アナログ電子回路コミュニティへのユーザ投稿に関するライセンスは、アナログ電子回路コミュニティの会員登録時に同意いただいておりました、アナログ・デバイセズの「利用規約」ならびに「ADIのコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約」に則って取り扱われます。
また、英語版ではございますが、アナログ・デバイセズではEngineerZoneというコミュニティサービスを運用しています。こちらのコミュニティでは、アナログ・デバイセズの技術に精通した技術者と交流することで、設計上の困難な課題に関する質問をしたり、豊富な技術情報を参照したりすることが出来ます。こちらも併せてご活用ください。
この記事に関して
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}