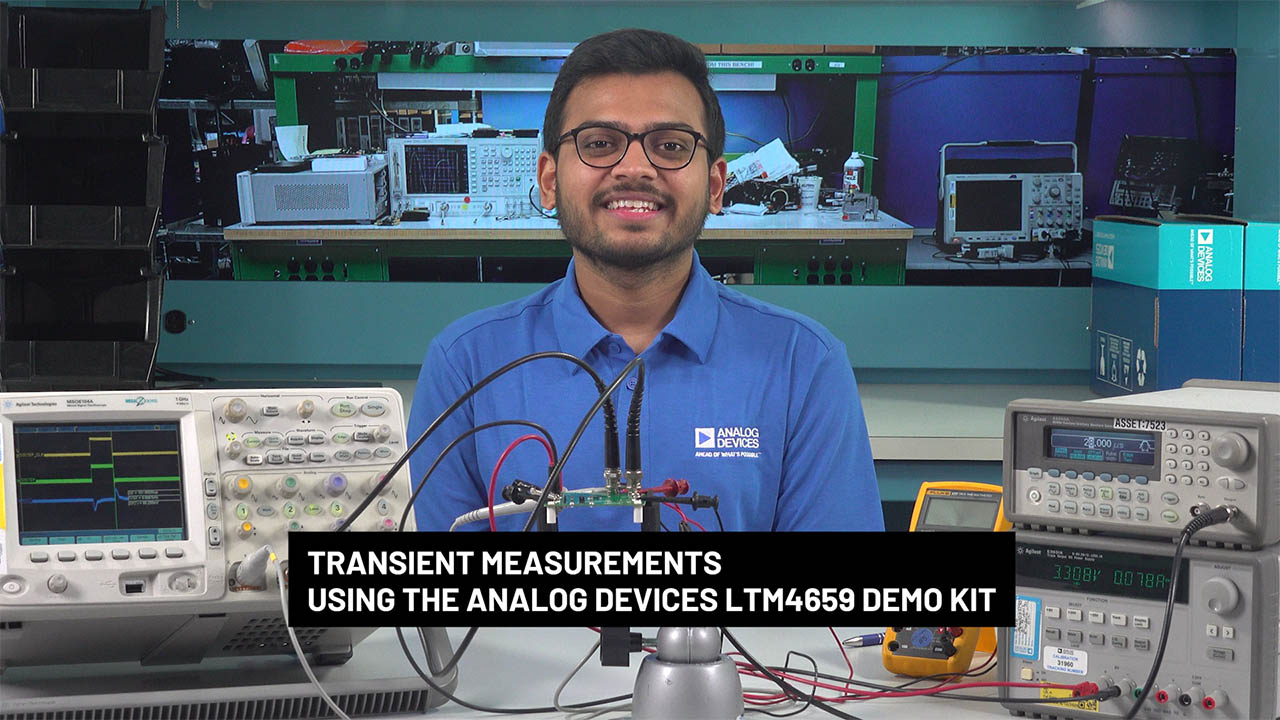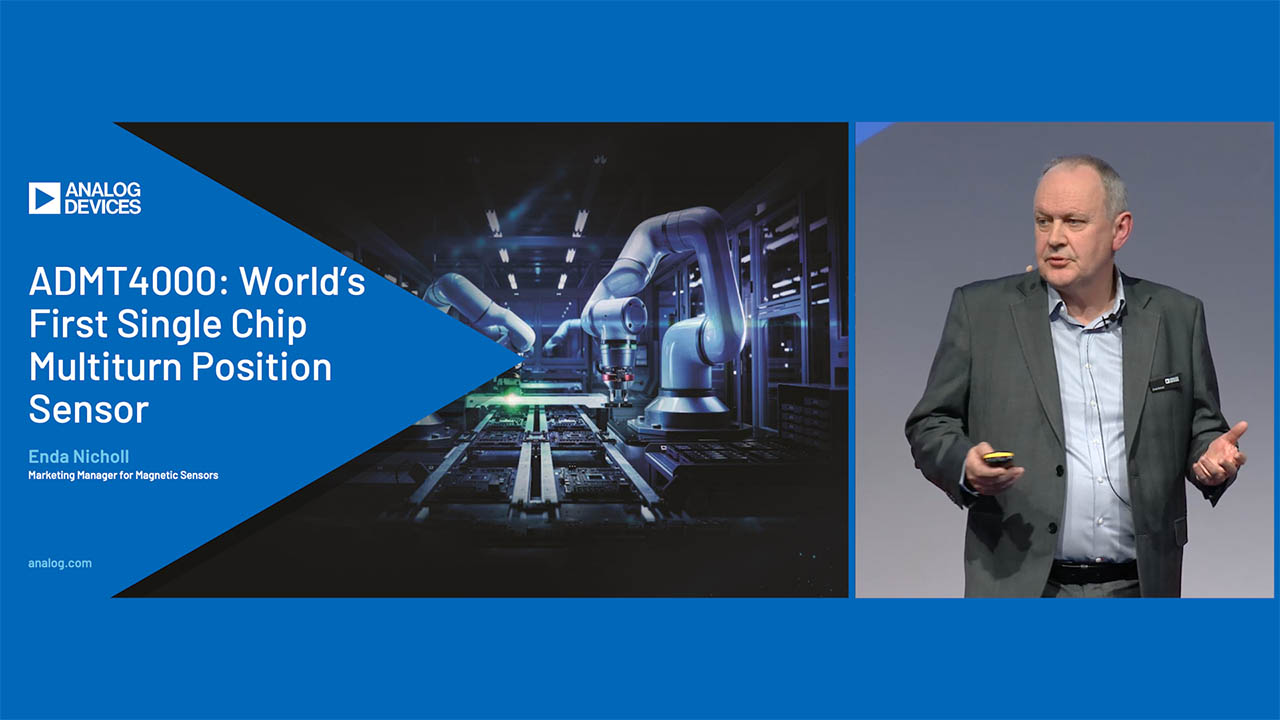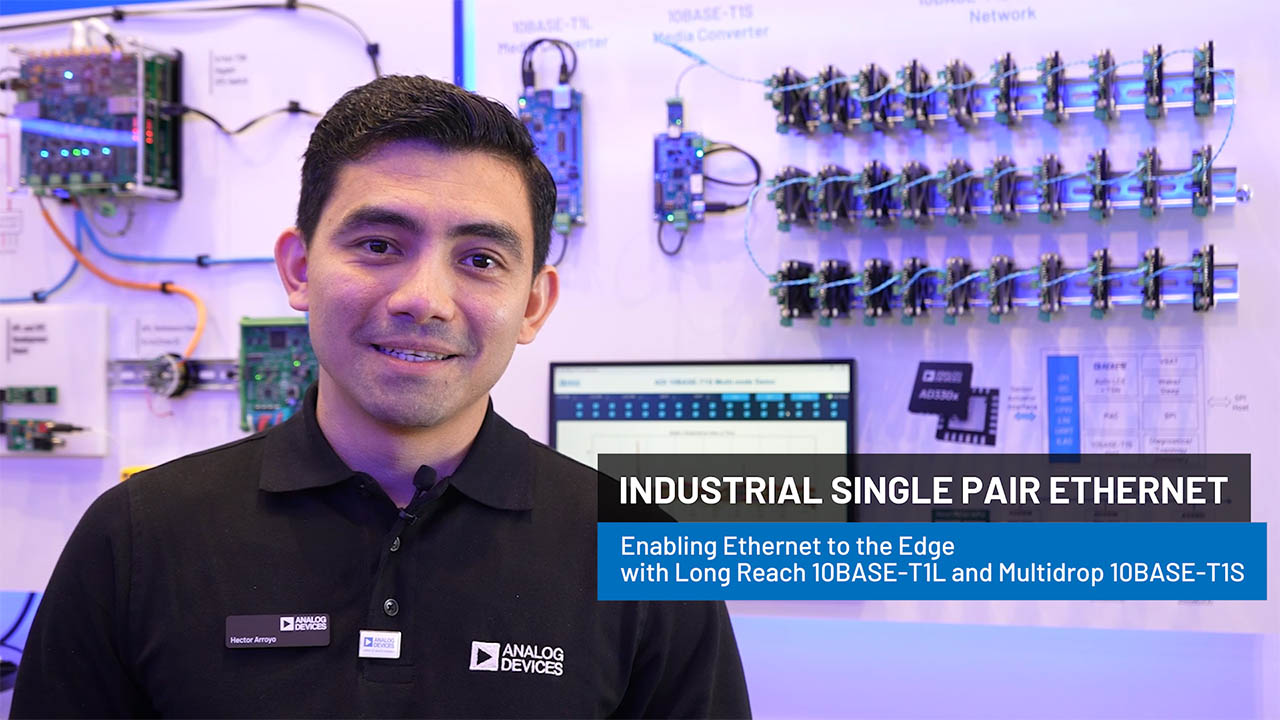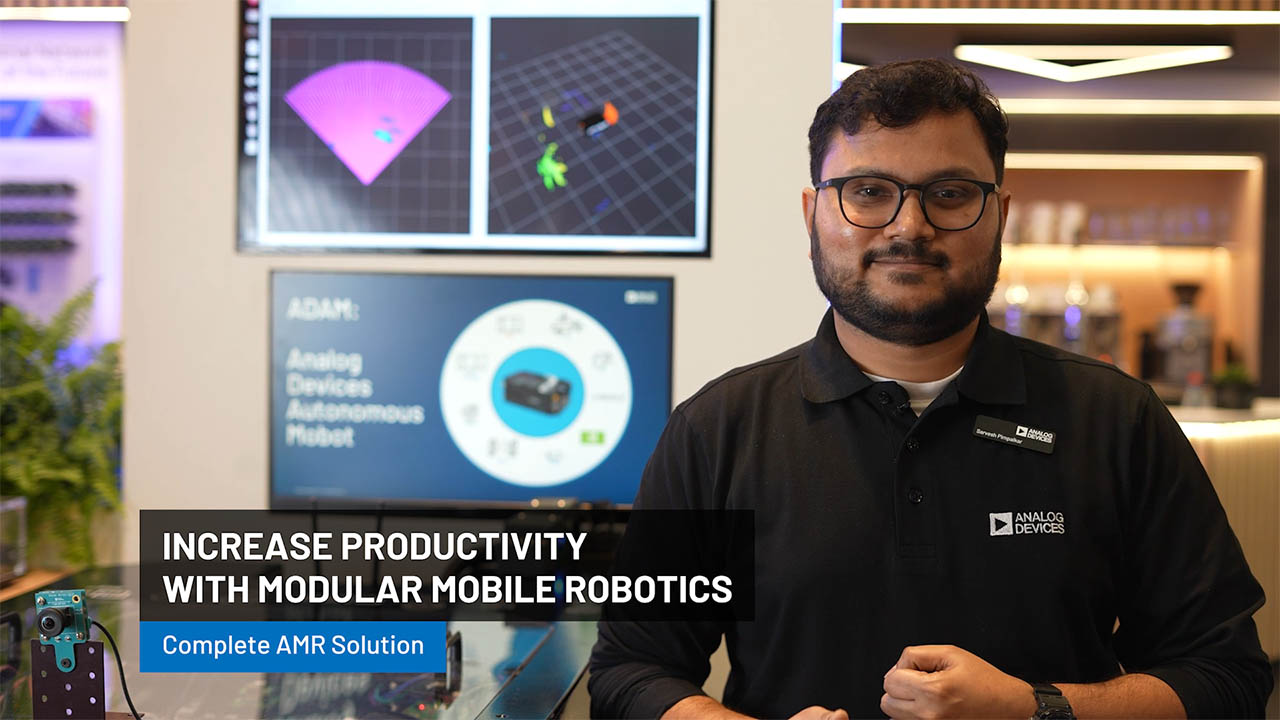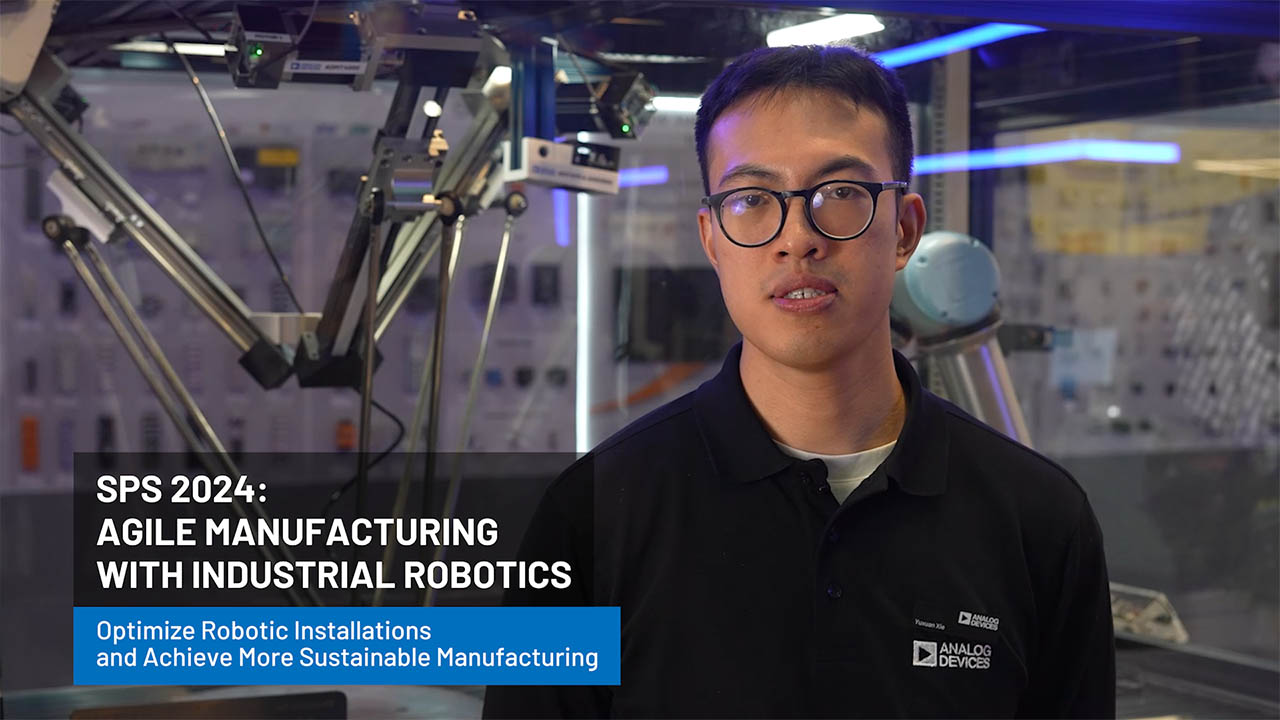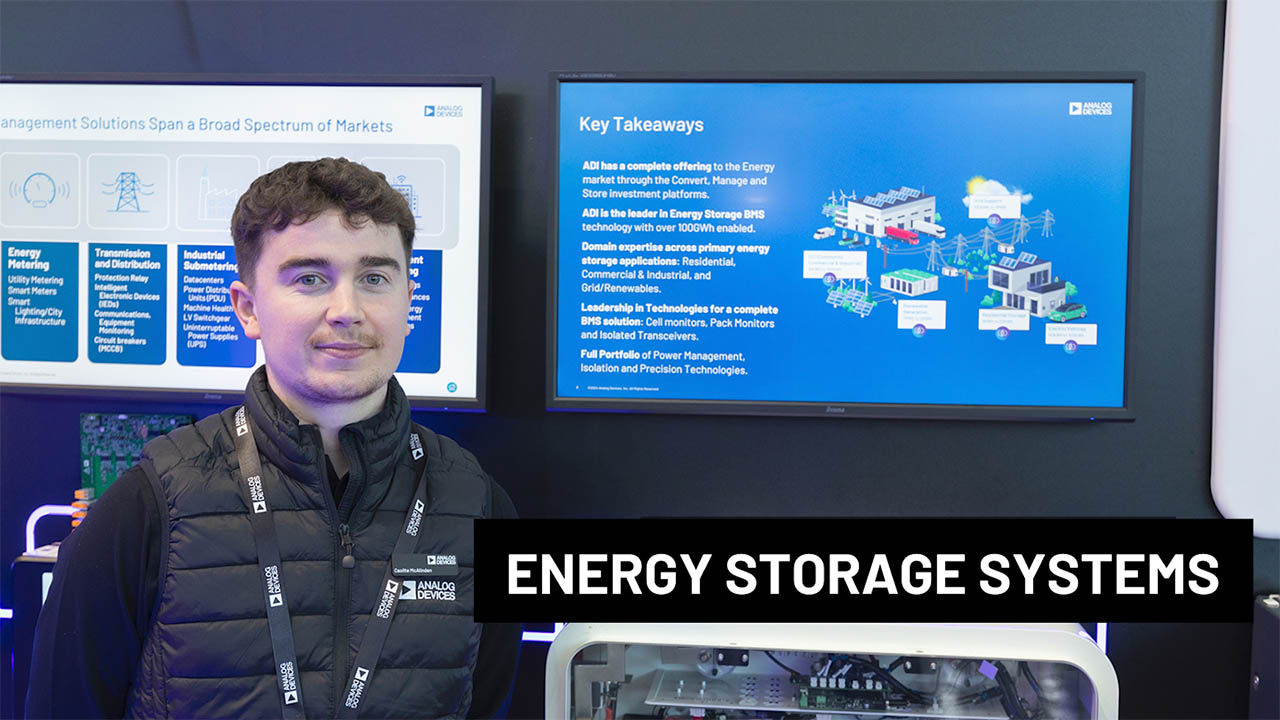デジタル・ポテンショメータは、アナログ方式のものと何が違うの?
質問
デジタル・ポテンショメータについて教えてください。アナログ方式のものと比較すると、どのような違いがあるのでしょうか? また、使用上の注意点などがあれば、それについても教えてください。
回答
アナログ・ポテンショメータ(機械式のポテンショメータ)とデジタル・ポテンショメータ(以下、digiPOT)を比較すると、値の変化の仕方や、値の決定方法に違いがあると言えます。まず、アナログ・ポテンショメータでは連続的に値が変化します。例えば、旧式のオーディオ機器などでは、円形のボリュームつまみを回すことで音量を設定していました。つまり、人手による操作で連続的にアナログ量を変化させていき、つまみを回すのを止めることで、最終的な値を決定するということです。
このつまみの部分に使われているのがアナログ・ポテンショメータです。なお、これは使い方の一例であって、アナログ・ポテンショメータは必ず人手で操作するということではありません。また、この例の場合、アナログ・ポテンショメータは回転角を抵抗値に変換しているのですが、ポテンショメータという言葉については、可変抵抗器といった広い意味で捉えるべきかもしれません。特に、digiPOTについてはそのような理解の方が適切だと考えられます。
digiPOTでは、あらかじめ用意されている値のうちいずれかを、デジタル制御によって選択します。オーディオ機器のボリュームの例で言うと、例えば最大音量から最小音量までの間を256ステップで設定できるように回路を構成しておき、いずれかの値をデジタル制御で決定するといった具合です。デジタル制御を行うということから、digiPOTを動作させるには電源が必要だということもご理解いただけるでしょう。なお、アナログ・ポテンショメータも完全に連続的に値が変化するわけではなく、ある程度のステップで値を変化させる製品も少なくないようです。
アナログ方式の問題点
ある投稿者からは、「digiPOTは使ったことがないのだが、アナログ・ポテンショメータには嫌気がさしている」という意見が寄せられました。その理由は、機械式のポテンショメータの場合、軽く振動を与えるだけで設定値が少しずれてしまうからだと言います。実際、新品を使ってきちんと調整を行っているのに、時間の経過に伴い、大きなズレが生じてしまうということが起こり得ます。この点については、単回転型のものでも多回転型のものでも違いはありません。
また、別の投稿者は「アナログ・ポテンショメータのバックラッシュは大きすぎる」と指摘しています。これについても単回転型のものでも多回転型のものでも同様です。
設定精度を高めようとして多回転型の製品を採用しても、無意味に近い結果に終わることがよくあります。加えて、バックラッシュに生じるドリフトにも注意が必要です。バックラッシュの大きさは、メーカーごとに差があります。そのため、価格だけに注目して製品を選択してしまうと、トラブルに遭遇することになるかもしれません。さらに、巻き線型のポテンショメータでは温度係数は一定ですが、サーメット型のポテンショメータの場合、低温では負の温度係数になり、高温では正の温度係数になる(40℃付近でゼロになる)という複雑な性質を持ちます。
もちろん、機械式のポテンショメータの場合、埃や汚れ、酸化の影響を受けるという欠点もあります。こうした理由から、アナログ・ポテンショメータは必ずしも信頼性が高く、使いやすいものだとは言えません。実際、回路に何らかの工夫を盛り込んで欠点に対処しなければならないケースが少なくないようです。
digiPOTの基本と注意点
digiPOTの主要な構成要素は、ステップの数だけ直列に抵抗を接続した抵抗ストリングです。各抵抗の間にはタップが設けられており、CMOSスイッチが接続されています。例えば、8ビットのdigiPOTであれば、255個の抵抗に256個のCMOSスイッチが付加されています。そして、外部からの設定に応じてどれか1つのタップだけを選択するために、1つのCMOSスイッチをオンにするということが行われます。
このような制御により分圧比が決まり、所望の電圧値が得られます。ただ、CMOSスイッチは半導体素子なのでオン抵抗が存在します。スイッチのサイズを大きくすればオン抵抗の値は小さくなりますが、そうすると接合容量が大きくなってAC特性が低下してしまいます。つまり、サイズを大きくするにも限界があるということです。このような理由から、オン抵抗がそれなりの大きさであることを前提にしつつ、それが大きな誤差要因にならないようにトータルの抵抗値(8ビット品であれば、255個の抵抗の値の総和)が決定されます。
結果として、digiPOTのトータルの抵抗値としては比較的大きな値が選ばれます。特殊な製品であれば1kΩ程度の場合もありますが、通常は10kΩ以上の抵抗値が使われます。
また、digiPOTでは1つのICチップ上に抵抗素子を形成するため、抵抗ストリングを使用するD/Aコンバータと同様の高い相対精度が得られます。したがって、digiPOTを分圧器として使用すれば、高精度で使いやすい回路を構成することが可能です。
ただし、抵抗値の絶対精度は必ずしも高くありません。つまり、抵抗の絶対値が重要になる用途ではdigiPOTは最適な選択肢にはなりません。例えば、digiPOTによって分流した電流の絶対値が重要な意味を持ち、それによって何かをトリムしたいといったケースには向いていないということです。ただ、設定を行った後のドリフトについては規定値内に収まることが保証されます。加えて、ワイパーの設定位置のヒステリシスがなく、高い再現性が得られるということもdigiPOTの長所として挙げられます。
基本的な機能の面から言えば、digiPOTとアナログ・ポテンショメータの間に大きな違いはありません。では、digiPOTはアナログ・ポテンショメータをそのまま置き換えることが可能なものだと言えるのでしょうか。
確かに、digiPOTとアナログ・ポテンショメータを比較すると、内部回路にも似ている部分がありますが、両者は完全な互換性を持つデバイスではありません。例えば、digiPOTには、電源電圧よりも大きい信号は扱えないという基本的な制約があります。このことから、高電圧を扱うアッテネータとしての使用には適していません。また、回路図には描かれませんが、digiPOTのすべての端子にはESD保護用の素子が付加されています。これは、他の半導体製品と同様に、過度なチャージが印加されるとダメージを受ける可能性があるということを意味しています。
例えば、機器の外部に引き出される端子に直接接続するような場合には、digiPOTの外部に何らかの保護機構を設ける必要があるでしょう。また、digiPOTを使う場合には過電圧や周波数特性にも注意を払う必要があります。
簡単に言えば、機械部品ではなく、電子部品であるということを念頭に置いて扱わなければならないということです。
digiPOTの用途
では、digiPOTが適した用途としてはどのようなものがあるのでしょうか。digiPOTはプログラマブルなデバイスであり、デジタル制御によって高速に設定を変更できます。したがって、動的にワイパーの位置を切り替えたい用途などに適しています。また、AC特性に優れることから、フィルタなどのように比較的帯域の広い用途でも有効に活用することができます。
さらに、抵抗の相対精度が高いという点も活かすべき特徴の1つです。そうした長所を踏まえると、例えば、産業用制御システムや、医療用の計測機器などにおいて、カットオフ周波数が可変のローパス・フィルタ、プログラマブル・ゲイン・アンプ、プログラマブルな発振器、電圧‐電流コンバータ、立上がり/立下がり時間をプログラムできるコントローラなどを実現するためにdigiPOTを使用するということが想定できます。
また、最近では、設計/製造の効率や利便性の面から、製造ラインで機器製品の自動調整を行うという例が増えています。その自動調整に向けて、製造ラインで補正用のパラメータを抽出し、それらのデータをdigiPOTが内蔵するEEPROMやフラッシュ・メモリに書き込んでおき、機器を使用する際(電源を投入する際)にそれらのデータをdigiPOTにロードするといったことが行われています。
つまり、製品を工場から出荷する際、校正用の設定や各種パラメータの設定といった作業を動的に実施できるということです。加えて、不揮発性メモリを備えるdigiPOT製品を使えば、電源がオフした際にもワイパーの設定を保持することができます。さらに、ヒューズ・リンクを備える製品では、ワンタイム・プログラム・トリマー機能を利用可能です。
先述したように、アナログ・ポテンショメータを使用する場合、振動などが原因で値に大きなズレが生じてしまう可能性があります。digiPOTであれば、そのようなことは発生しないので安心して使用できます。ただし、設定/調整を行うにはA/Dコンバータを備えるマイクロコントローラなどが必要になるでしょう。その意味で、digiPOTの設定は、アナログ・ポテンショメータと比べて少し面倒だと言えるのかもしれません。
ただ、なかにはコントローラがなくても設定できる便利な製品もあります。例えば「AD5228」では、2つのプッシュ・ボタンをつなぐことで、設定値のアップ/ダウンの機能を実現できます(下図)。

それにより、手作業で抵抗値を変えられるようになっています。また、プッシュ・ボタンのチャタリング防止機能も備えています。ただ、この製品は不揮発性メモリは内蔵していないので、電源をオフにするとワイパーの位置はリセットされます。ご興味のある方は、同ICの AD5228のデータシートをご覧ください。
それ以外にも、アナログ・デバイセズは、数多くのdigiPOT製品やそれに関連する技術資料を提供しています。詳しくはデジタル・ポテンショメータのページをご覧ください。
アナログ電子回路コミュニティとは
アナログ電子回路コミュニティは、アナログ・デバイセズが技術者同士の交流のために提供していた掲示板サイトで、2018年3月に諸般の事情からサービスを終了しました。
アナログ電子回路コミュニティには日々の回路設計活動での課題や疑問などが多く寄せられ、アナログ・デバイセズのエンジニアのみならず、業界で活躍する経験豊富なエンジニアの皆様からも、その解決案や意見などが活発に寄せられました。
ここでは、そのアナログ電子回路コミュニティに寄せられた多くのスレッドの中から、反響の大きかったスレッドを編集し、技術記事という形で公開しています。アナログ電子回路コミュニティへのユーザ投稿に関するライセンスは、アナログ電子回路コミュニティの会員登録時に同意いただいておりました、アナログ・デバイセズの「利用規約」ならびに「ADIのコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約」に則って取り扱われます。
また、英語版ではございますが、アナログ・デバイセズではEngineerZoneというコミュニティサービスを運用しています。こちらのコミュニティでは、アナログ・デバイセズの技術に精通した技術者と交流することで、設計上の困難な課題に関する質問をしたり、豊富な技術情報を参照したりすることが出来ます。こちらも併せてご活用ください。
この記事に関して
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}