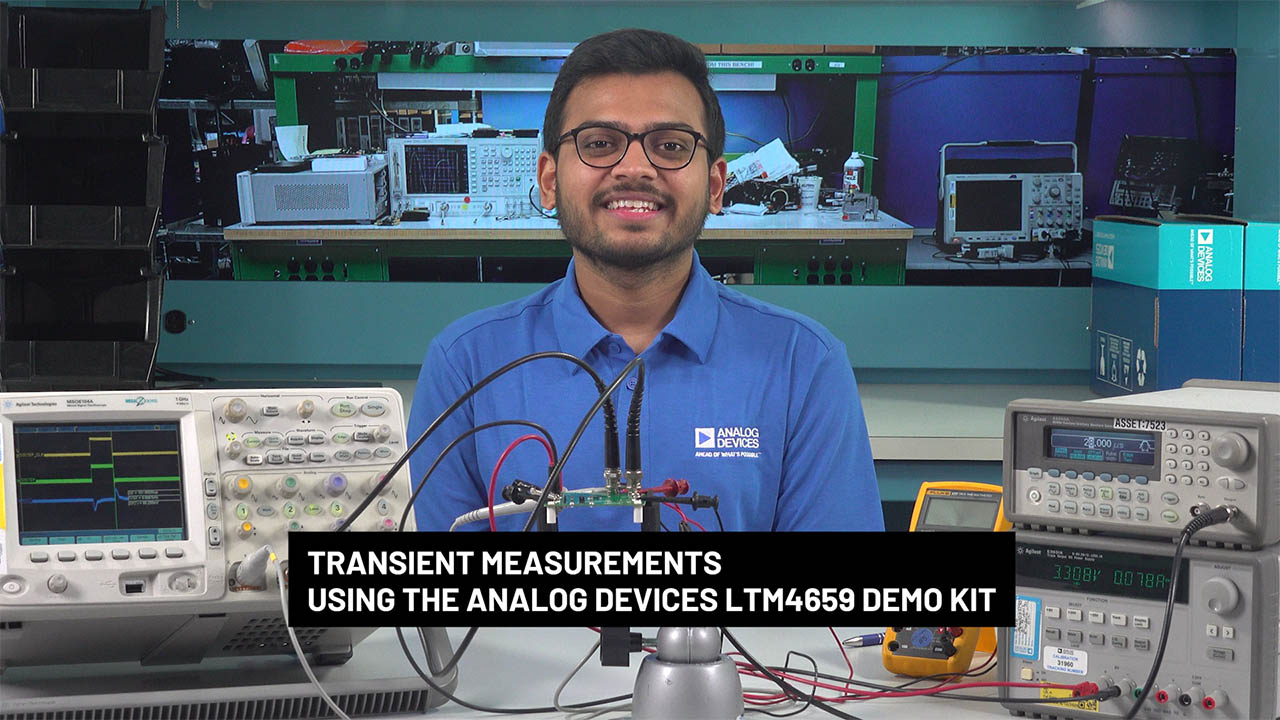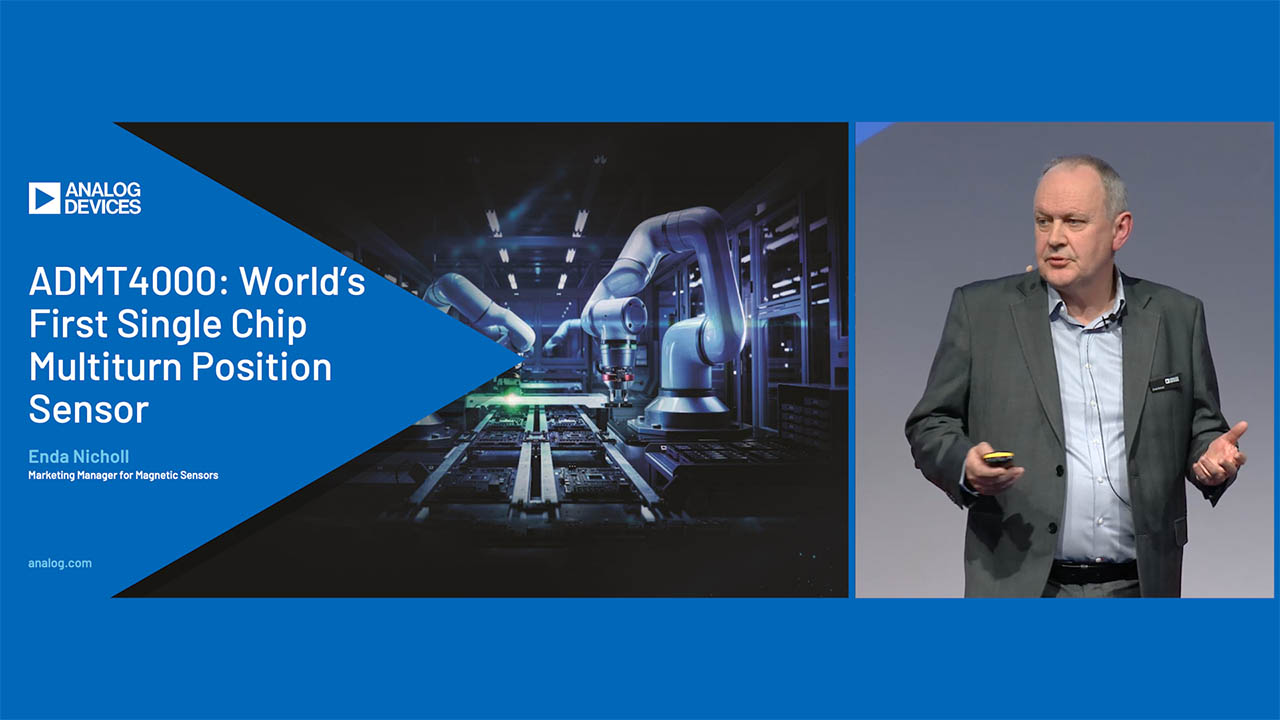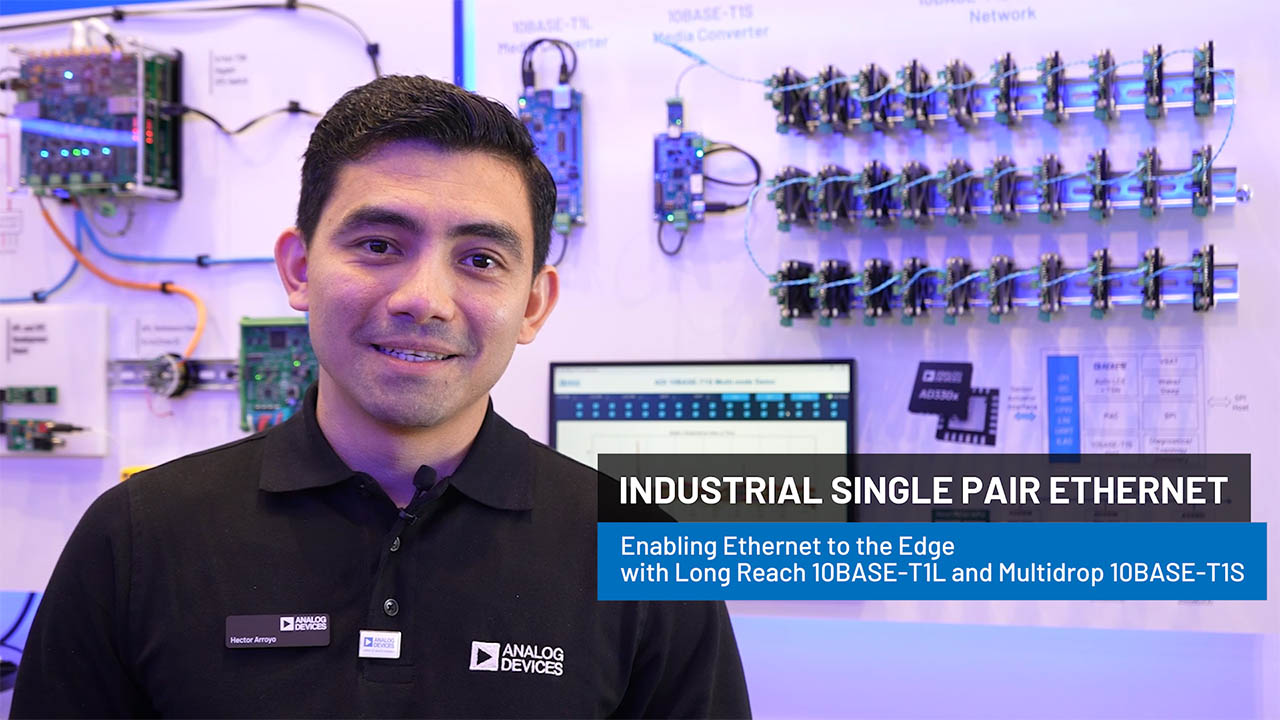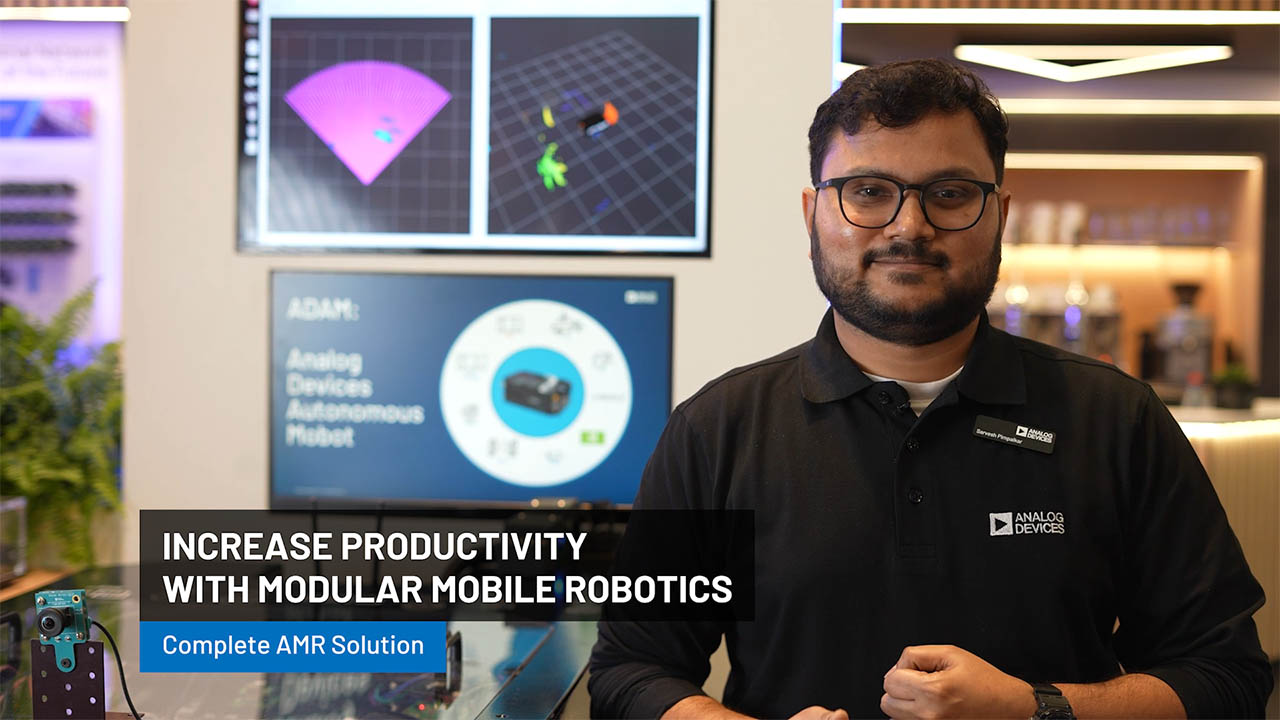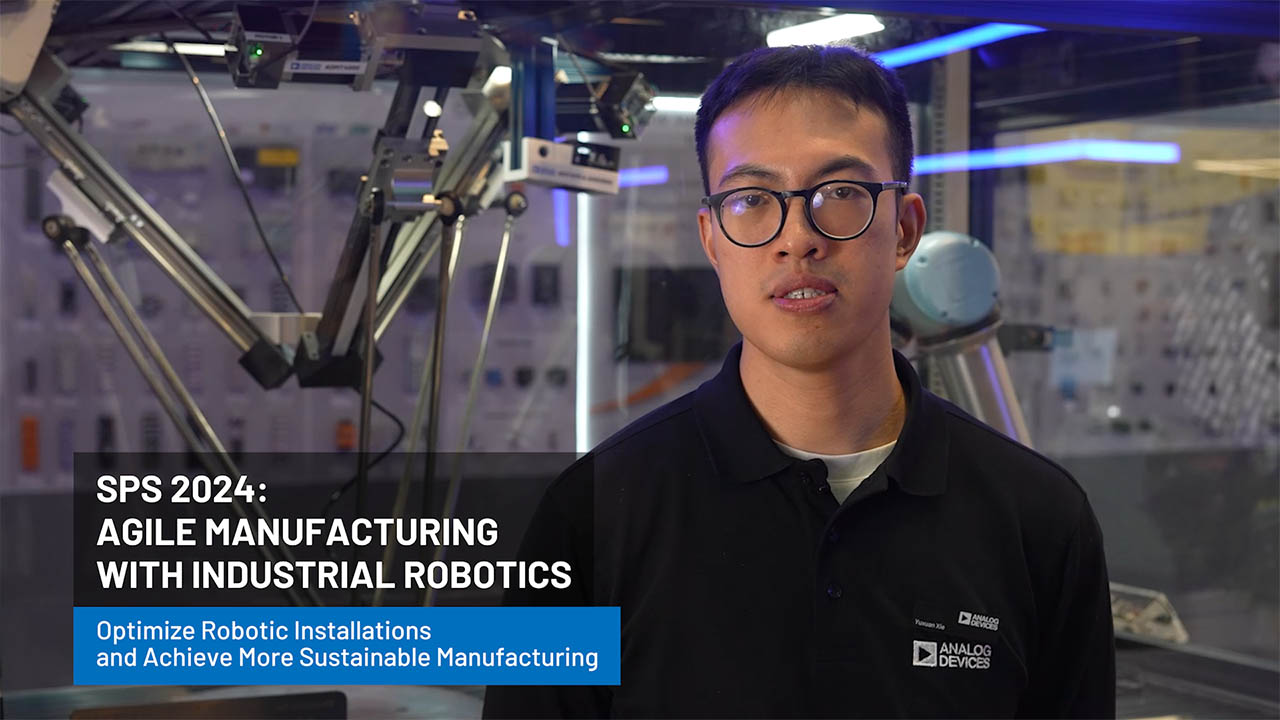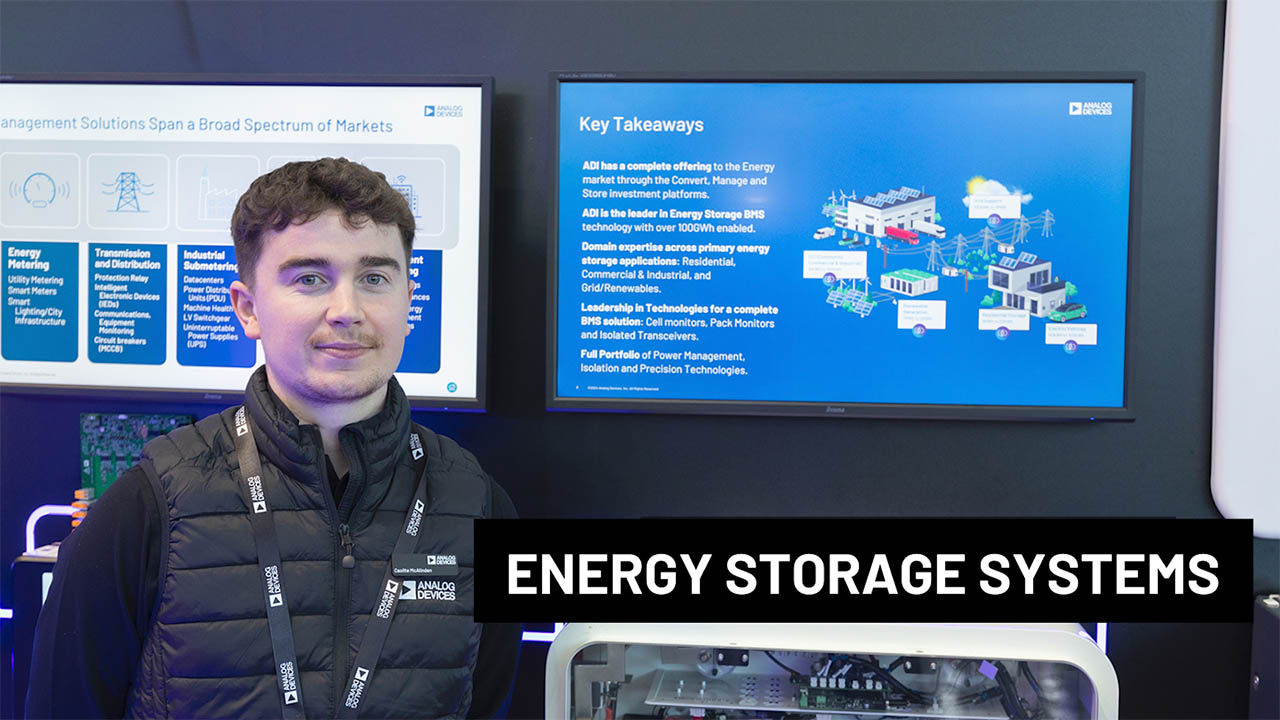基板にハンダ付けされた表面実装型ICの取り外し方
アナログ電子回路コミュニティのスレッドから
質問
基板にハンダ付けされた表面実装型のICをうまく取り外す方法はありませんか?
回答
表面実装型のICは、プリント基板に一度ハンダ付けしてしまうと、容易に取り外すことはできません。
例えば、抵抗やコンデンサといった2ピンの部品であれば、ハンダごてを2本使い、2つのピンを一度に加熱することで取り外すことができるでしょう。あるいは小型の部品であれば、ハンダをたっぷりと盛り、両方のピンをブリッジした状態にして加熱することで取り外すことが可能です。
問題なのは、IC に代表されるようなピン数が多いものです。その種の部品を取り外すのは容易ではありません。以下、IC のように何本ものピンを備える部品を取り外す方法を紹介します。
SOP品の取り外し
用意するものは、ハンダごて、ハンダ、ピンセット、銅線、ハンダ吸い取り線などです。これらは、ハンダ付けの作業が行われる場所には間違いなく存在するでしょう。まず、写真1のように「コ」の字の形に銅線を折り曲げて、ICのピンの外側にぴったりはまるようにします。
銅線は単線でもかまいませんが、太いものだと加工が難しいかもしれません。恐らく、0.5mm径くらいの銅線を3~4本撚り合わせたものが使いやすいはずです。ICのピン数が多い場合には、熱が伝わりやすいように太めの銅線を用意します。

写真1. 銅線の取り付け
次に、銅線部分にハンダをたっぷりと盛ります(写真2)。
ICのすべてのピンに、十分にハンダが流れ込むようにしてください。低温ハンダの方が好ましいと言えますが、共晶ハンダでも大差はないかもしれません。鉛フリーのハンダは固まりやすく、少し扱いにくいと言えます。ただ、鉛フリーでなければならない場合には他に選択肢がありませんし、それでは役に立たないというわけでもありません。
いずれにせよ、ダメージを少なくするためには融点の低いハンダが適しています。サンハヤトなどは、取り外し専用品としてフラックスとハンダを組み合わせたキットを販売しています。続いてハンダを盛った銅線全体を加熱します。ハンダごてとしては少し容量が大きいものが適しています。コテ先を交換できる場合には、写真2のように、太く、短く、熱抵抗が小さいものを選ぶとよいでしょう。30ピンのSOPくらいまでなら1本のハンダごてで2ヵ所ほど交互に加熱すれば取り外せるはずです。

写真2. ハンダの加熱
もっとピン数が多い場合には、2本のハンダごてで加熱します。ただ、この作業を1人でこなすには少し慣れが必要かもしれません。ハンダが溶けたらコテ先で銅線を軽く押してみてください。ICが動く(ハンダ付けされた元の位置から少し移動する)ようであれば準備は完了です。
1ピンでもハンダが溶けていないと、ICを外したときに基板のパッドがはがれてしまうことがあるので注意しましょう。ハンダごてで加熱したまま、ピンセットで素早く銅線ごとICを取り外します(写真3)。ここでうっかりICを基板に落としてしまうと、変な状態でハンダが固まってしまい困った事態に陥ってしまうことがあります。手前に紙などを敷いて、取り外したICを即座に置けるようにしておくとよいでしょう。

写真3. ピンセットによる取り外し
最後に、基板のパターン上に残った余計なハンダをハンダ吸い取り線で取り除き、フラックスをアルコールなどで拭き取れば作業は完了です。廃棄しても構わないような基板を使って、2~3回練習してみてください。すぐにできるようになるはずです。使用後の銅線は、ハンダごてで加熱してICから取り外せば何度でも再利用できます。なお、ICが接着剤で固定されている場合や、コーティングされている場合には、上記の方法では取り外せないことがあります。
これ以外にも、リードにハンダをたくさん盛って、ドライヤであぶりながらハンダごてで一方ずつハンダを浮かせて取り外すという方法があります。ただ、この方法には、ドライヤによる熱の影響が周辺の部品に及ぶという欠点があります。これまでドライヤを使っていた方は、ぜひ、今回紹介した方法を試してみてください。
QFP品の取り外し
より難易度の高いものとして、続いてはピン数の多いQFP品の取り外し方を紹介します。用意するものは、小型のICの場合と同じく、ハンダごて、ハンダ、ピンセット、銅線、ハンダ吸い取り線などです。ただ、QFP品の場合には、それらに加えて細い銅線が必要になります。太さが0.15~0.3mm程度であれば、エナメル線でも、撚り線をほぐしたものでも構いません。
ハンダごてについては、70W程度の大きな出力に対応するものを使用します。また、できれば2本は使用したいところです。ここでは、白光のハンダごて「FX-951」を使用することにしました。70Wの出力に対応し、自動温度調整機能も備えた製品です。こて先としては高熱容量のものを選択しています。
まず、ICの対辺のピンの下に細い銅線を通し、写真4のように銅線の頂点を撚り合わせてピラミッド状にします。この作業がQFP品に対応する上でのポイントです。多少のたるみなどがあっても問題はありません。
続いて、太い銅線をQFPのピンのまわりにぴったりと適合するよう丁寧に折り曲げてはめ込みます。単線でも構いませんが、0.5mmくらいの銅線を撚り合わせたものが使いやすいでしょう。大型のICの場合には、熱が伝わりやすいように太い線を選択します。この例では、インターホンの配線に使う0.5mmのビニール単線の被覆を剥がし、7本を撚り合わせて使用しました。

写真4. 銅線のセットアップ
続いてハンダをたっぷりと盛ります。ICのすべてのピンに確実にハンダが付いている状態にしなければなりません。銅線の合わせ目もハンダでつないでおきます。作業中に銅線が浮き上がらないように気を付けましょう。
次に、2本のハンダごてを使い、ハンダを盛った銅線を加熱します。対向した2辺ずつを交互に加熱し、4辺とも均等にハンダが溶けるようにします(写真5)。ハンダが溶けたら、ハンダごての先で軽く銅線を押してみてICが動くことを確認します。完全にハンダが溶けていないピンがあると、基板のパッドをはがしてしまうのでくれぐれも注意してください。
ICが動くことを確認したら、ハンダごての先をピラミッド上の細い銅線に差し込んでICを持ち上げます。この作業がQFPに対応する上での肝になります。
ハンダごてを2本使っているので、1人だとピンセットなどが使えません。2人で作業するとしても、QFPというのは意外にピンセットではつまみにくいものです。うっかり、ICを基板に落としてしまうと、変な状態でハンダが固まってしまうことになります。くれぐれも、気を付けてください。後は、ハンダ吸い取り線などを使って基板をきれいにすれば作業は完了です。銅線は何度でも使えますし、ハンダも回収しておけば再利用することが可能です。

写真5. ハンダの加熱
以上、本稿では基板にハンダ付けされたSOPやQFPのICを取り外す方法を紹介しました。この種の作業は自力でも不可能ではありません。ただ、そうしたサービスを提供している企業も存在します。例えば、トモエレクトロのような企業に依頼すればBGA品なども取り外してくれます。また、パターンの傷みの修正などにも対応してくれます。必要に応じて、作業の委託も検討してみてください。
注釈:記事中の画像は、HN:tamanyan さんより、アナログ電子回路コミュニティへ投稿されたものです。
アナログ電子回路コミュニティとは
アナログ電子回路コミュニティは、アナログ・デバイセズが技術者同士の交流のために提供していた掲示板サイトで、2018年3月に諸般の事情からサービスを終了しました。
アナログ電子回路コミュニティには日々の回路設計活動での課題や疑問などが多く寄せられ、アナログ・デバイセズのエンジニアのみならず、業界で活躍する経験豊富なエンジニアの皆様からも、その解決案や意見などが活発に寄せられました。
ここでは、そのアナログ電子回路コミュニティに寄せられた多くのスレッドの中から、反響の大きかったスレッドを編集し、技術記事という形で公開しています。アナログ電子回路コミュニティへのユーザ投稿に関するライセンスは、アナログ電子回路コミュニティの会員登録時に同意いただいておりました、アナログ・デバイセズの「利用規約」ならびに「ADIのコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約」に則って取り扱われます。
また、英語版ではございますが、アナログ・デバイセズではEngineerZoneというコミュニティサービスを運用しています。こちらのコミュニティでは、アナログ・デバイセズの技術に精通した技術者と交流することで、設計上の困難な課題に関する質問をしたり、豊富な技術情報を参照したりすることが出来ます。こちらも併せてご活用ください。
この記事に関して
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}