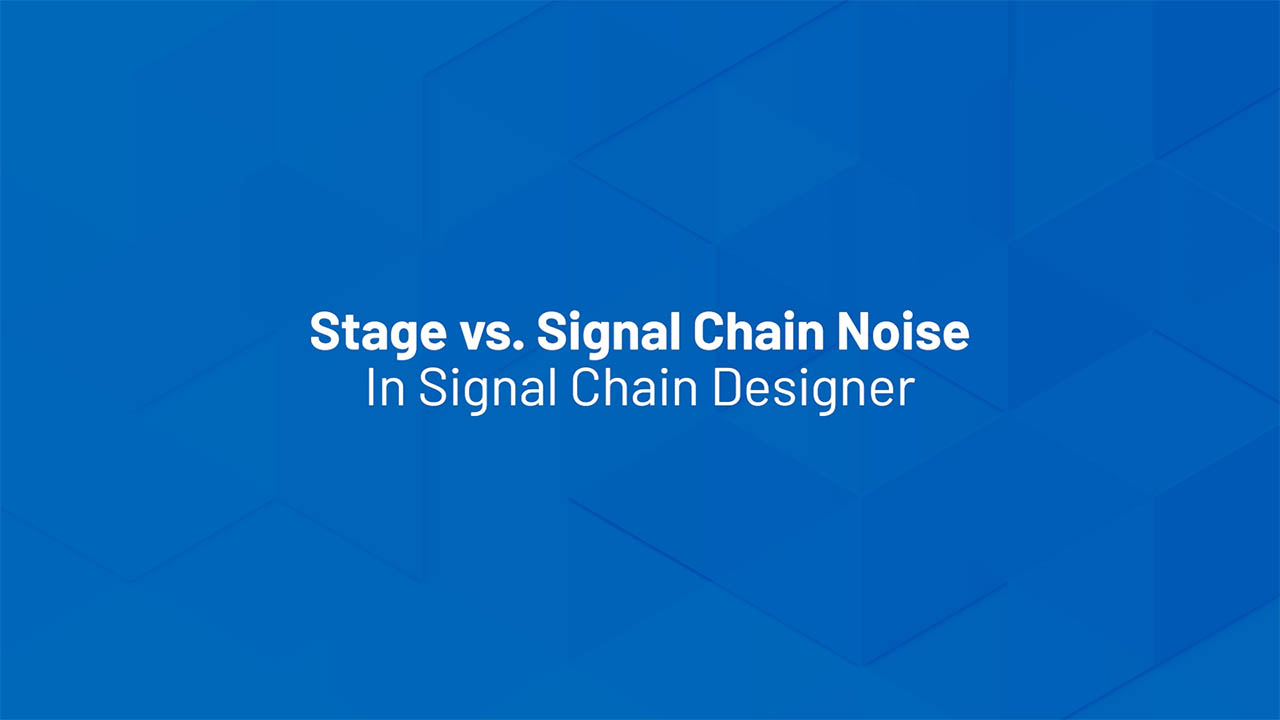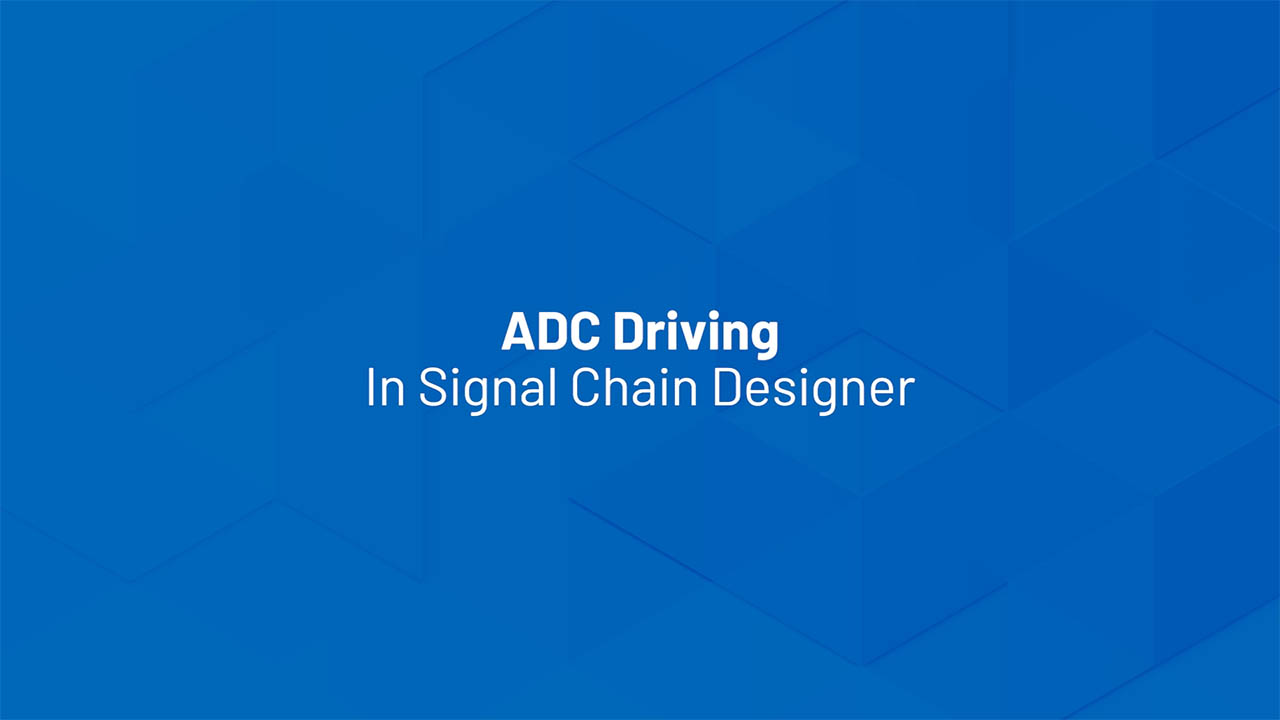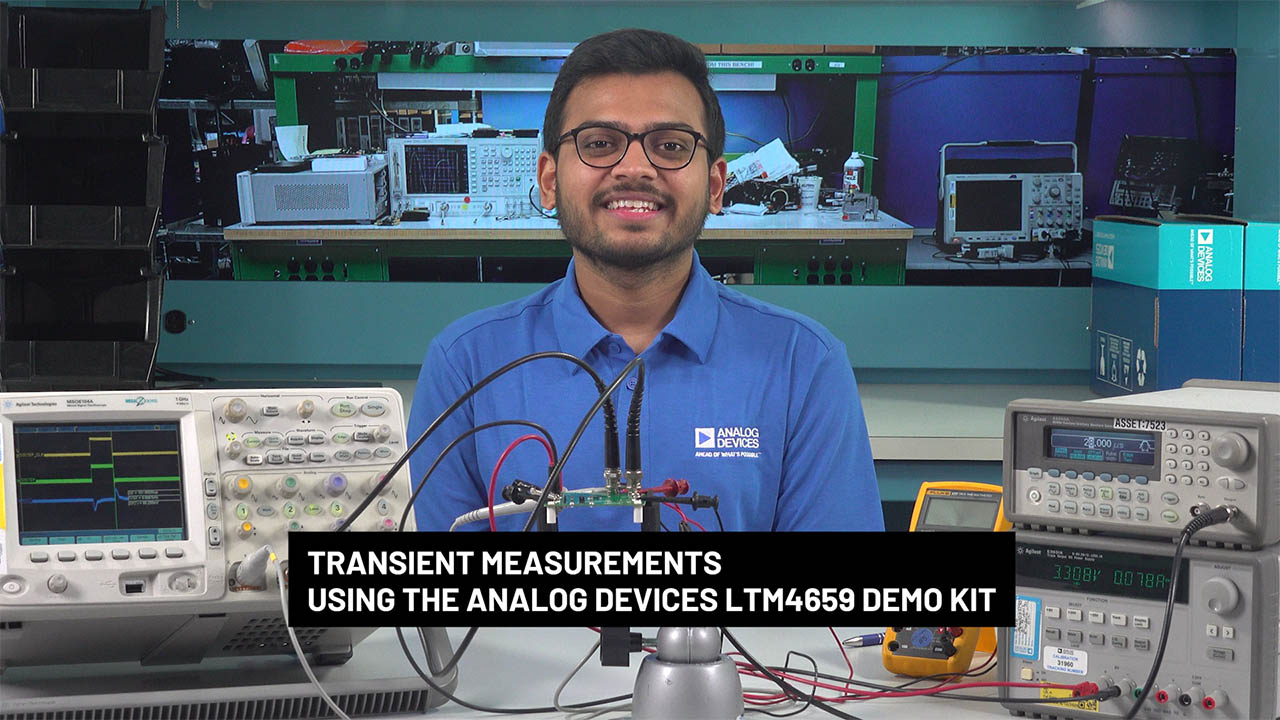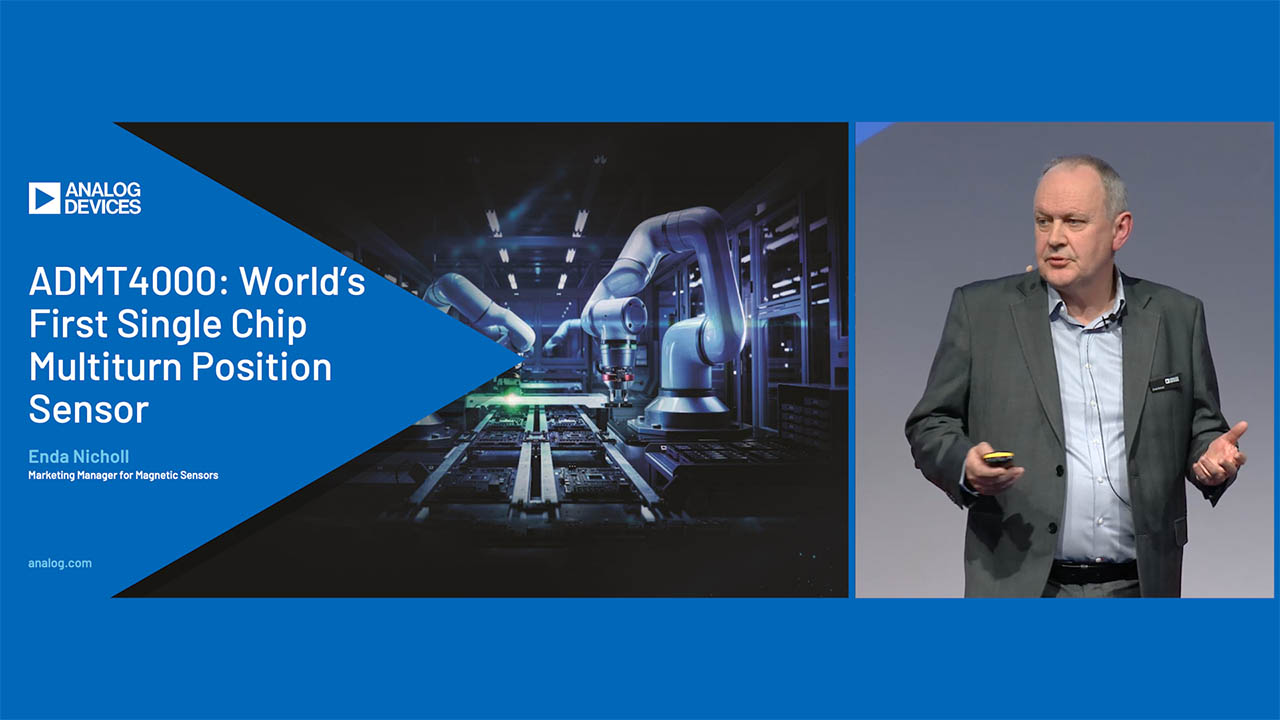要約
本稿では、アナログ・ビデオに関する基礎的な事柄について説明します。具体的には、次の4つのセクションによって解説を進めていきます。まず「映像の基礎」では、ビデオ映像がどのように生成されるのかを明らかにします。続く「解像度 - 視覚とフォーマット」では、様々な解像度のフォーマットと、解像度を規定/測定する方法について説明します。そして「フォーマットとインターフェース」では、様々な種類のビデオ信号、波形、インターフェースについて解説します。稿末に設けた「用語集」では、ビデオに関連する特有の用語について説明します。
はじめに
本稿では、アナログ・ビデオの中でも、「動画」に限定して解説を進めます。つまり、デジタル・スチル・カメラやスキャナなどで扱われる静止画の話題は取り上げません。静止画に関する要件には、動画に関する要件と多くの共通点があります。ただ、それ以外の部分の違いは大きく、別の分野として扱う必要があります。
本稿は、4つのセクションから成ります。1つ目の「映像の基礎」では、ビデオの映像がどのように生成されるのかを明らかにします。次の「解像度 - 視覚とフォーマット」では、様々な解像度のフォーマットと、解像度を規定/測定する方法について説明します。続く「フォーマットとインターフェース」では、様々な種類のビデオ信号、波形、インターフェースについて解説します。そして最後の「用語集」では、ビデオの分野に特有の用語について解説します。
映像の基礎
映像は、テレビやコンピュータのディスプレイに映し出されます。その描画を行うためには、電気信号を一度に1ラインずつディスプレイを横切る形で水平に走査するという処理が行われます。検出された信号における時間と振幅の関係によって、ディスプレイ上の物理的な点における瞬間的な輝度が決まります。図1に、信号の振幅とディスプレイ上の輝度の関係を示しました。

図1. 水平走査とディスプレイの輝度の関係
各ラインの最後には、水平ブランキング期間と呼ばれる波形が存在します。これは、ディスプレイの走査回路に対し、ディスプレイの左端まで戻り、次のラインの走査を開始するよう指示するためのものです。このようにして、ディスプレイ上のすべてのラインは、最上部から最下部まで走査されます。走査済みのラインがすべて揃うと1枚の画像が得られます。これをフレームと呼びます。最初の画像が完全に走査された後には、垂直ブランキング期間(不可視)という時間が設けられます。これは、走査回路に対し、ディスプレイの最上部まで戻って次のフレーム(画像)の走査を開始するように指示するためのものです。ここまでに説明したシーケンスは、表示された画像が連続して動いているように感じられるほど高速に繰り返されます。これは、「パラパラ漫画」と同じようなものだと言えます。パラパラ漫画では、各ページを素早くパラパラとめくると、各ページに描かれた絵が動いているように見えます。1枚ずつ描かれた絵を順番に素早く表示していくアニメーションと同じようなものだとも言えます。
インターレース・スキャンとプログレッシブ・スキャン
インターレース・スキャンとプログレッシブ・スキャンは、いずれも画面上に画像を描画するための走査方式です。ただ、それぞれ異なる手法を採用しています。通常、テレビ用の信号ならびにそれに対応するディスプレイではインターレース・スキャンが使用されています。一方、コンピュータ用の信号ならびにそれに対応するディスプレイでは、通常はプログレッシブ・スキャン(ノンインターレース)が使われます。これら2つのフォーマットには互換性がありません。そのため、描画のための一般的な処理を行う前に、一方のフォーマットを他方のフォーマットに変換しなければ流用できないことになります。インターレース・スキャンでは、フィールドと呼ばれる2つの異なるサブ画像を組み合わせることによって、フレームと呼ばれる1つの画像を生成します。つまり、2つのフィールドによって1つのフレームが構成されます。もう少し詳しく説明すると、インターレース・スキャンでは、2回に分けて1つの画像を画面に描画します。まず、1つ目のフィールドの各水平ラインを走査していき、画面の最上部まで戻ります。続いて、2つ目のフィールドの各水平ラインを1つ目の各ラインの間に挿入するような形で走査します。フィールド1はライン1からライン262.5(252 1/2)まで、フィールド2はライン262.5からライン525までで構成されます。図2にインターレース・スキャンの原理を示しました。なお、この図には、各フィールドの最上部と最下部の数ラインだけを示してあります。

図2. インターレース・スキャン方式
プログレッシブ・スキャン(またはノンインターレース)では、画像のすべての水平ラインを最上部から最下部まで1回で走査します。それによって画面に1枚の画像を描きます(図3)。

図3. プログレッシブ(ノンインターレース)スキャン方式
解像度 - 視覚とフォーマット
ビデオ信号やディスプレイの視覚解像度は、どれだけ細かく見られるのかを表す指標です。これは、信号やディスプレイのフォーマット解像度とは異なるものです。例えば、コンピュータのアプリケーションの場合、XGA(Extended Graphics Array)信号のフォーマット解像度は水平方向が1024ピクセル、垂直方向が768ピクセル(ライン)です。これが暗黙的な視覚解像度となります。しかし、信号やディスプレイに性能を低下させるような制約が存在する場合、実際にはこのレベルの細かさを完全に表示することはできない可能性があります。
テレビおける視覚解像度
テレビにおける視覚解像度は、「TV本(TV lines)」と呼ばれるパラメータで規定されます。通常、このパラメータは水平方向の解像度を表すために使用されます。ただ、同じ手法を垂直方向の解像度に適用することも可能です。TV本は、黒線と白線が交互に並べられ、徐々に接近するように配置されているテスト・パターンを表示することで決定されます。具体的には、別々の線として識別できる最も間隔が狭い線のペアによって解像度が判定されます。画面の高さに等しい幅に並べることができる識別可能な垂直の線の数が解像度のTV本です。図4に示したのは、解像度を決めるための代表的な画像の例です。

図4. 視覚解像度を判定するための代表的なテスト・パターン.
コンピュータにおける視覚解像度
通常、コンピュータのフォーマット解像度は、水平/垂直の範囲内に表示できるピクセル数によって規定します。例えば、VGA(Video Graphics Array)フォーマットの信号では、表示可能なピクセル数は水平方向が640、垂直方向が480です。XGAフォーマットの信号の場合、表示可能なピクセル数は水平方向が1024、垂直方向が768となります。優れた設計のコンピュータ・システムの場合、既定の最大フォーマット解像度を達成できるよう仕様が定められています。つまり、そのようなシステムで実行されるすべての信号処理は、視覚解像度がフォーマット解像度と同等になるように設計されています。シグナル・チェーン内に、要求される性能を満たさない回路が存在すると、視覚解像度はフォーマット解像度よりも低くなります。
フォーマットとインターフェース
ビデオ信号には様々な種類が存在します。それらは、大きくテレビ用とコンピュータ用の2つに分けることができます。テレビ信号のフォーマットは国によって異なります。米国や日本では、NTSCフォーマットが使用されています。NTSCというのは、National Television Systems Committeeの略称であり、この規格を策定した組織の名称を表しています。一方、欧州ではPAL(Phase Alternating Line)フォーマットが一般的に使われています。これはNTSCフォーマットよりも後に策定されたものであり、NTSCフォーマットに対する改良が加えられています。また、フランスでは、SECAM(Sequential Couleur Avec Memoire)フォーマットが使用されています。なお、これら3つの一般的なフォーマットについては、全部で約15種類のサブ・フォーマットが存在します。一般に、各フォーマットには他のフォーマットとの互換性がありません。これらで使用される基本的な走査方式はすべて同じであり、一種の位相変調によって色を表現しています。ただ、各フォーマットでは、固有の走査周波数、走査線数、色変調技術などが使われています。VGA、XGA、UXGA(Ultra XGA)など、コンピュータ用のフォーマットにも様々な種類があります。それぞれに違いがありますが、大きく異なるのは走査周波数です。ただ、そうした違いはそれほど気にする必要はありません。ほとんどのコンピュータ機器は、可変スキャン・レートに対応するように設計されているからです。このような互換性が確保されているのは、コンピュータ用のフォーマットにとって大きなメリットになります。なぜなら、あらゆるコンテンツを全世界に流通させられるからです。
| ビデオ・フォーマット |
NTSC | PAL | HDTV/SDTV | VGA | XGA |
| 説明 | 北米/日本で使用されるテレビ用フォーマット | 欧州と南米のほとんどで使用されるテレビ用フォーマット | 高精細/標準画質のデジタル・テレビのフォーマット | PC用のフォーマット | PC用のフォーマット |
| 垂直解像度フォーマット(1フレーム当たりに表示可能なライン数) | 約480(計525) | 約575(計625) | 1080/720/480。18種類のフォーマット | 480 | 768 |
| 水平解像度フォーマット(1ライン当たりに表示可能なピクセル数) | 320~650の範囲。帯域幅によって決まる | 320~720の範囲。帯域幅によって決まる | 1920/704/640。18種類のフォーマット | 640 | 1024 |
| 水平レート〔kHz〕 | 15.734 | 15.625 | 33.75~45 | 31.5 | 60 |
| 垂直フレーム・レート〔Hz〕 | 29.97 | 25 | 30~60 | 60~80 | 60~80 |
| 最高周波数〔MHz〕 | 4.2 | 5.5 | 25 | 15.3 | 40.7 |
ベースバンド信号のインターフェースには3つの基本的なレベルがあります。映像の品質が高い順に示すと、1対のワイヤを使用するコンポジット(またはCVBS)、2対のワイヤを使用するY/C(またはSビデオ)、3対のワイヤを使用するコンポーネントとなります。各ワイヤのペアは信号とグラウンドで構成されます。これら3つのインターフェースでは、情報の結合(つまりコーディング)のレベルに違いがあります。通常、必要なエンコーディング処理が多くなると品質が劣化しますが、少ないワイヤで信号を伝送できる点は長所になります。エンコーディング処理の量は、コンポーネントが最も少なく、コンポジットが最も多くなります。
コンポジット/CVBSのインターフェース
コンポジットは、最もよく使用されているアナログ・ビデオ・インターフェースです。コンポジット・ビデオはCVBS(Composite Video Baseband Signal)とも呼ばれています。この呼び名は、Color, Video, Blanking and Syncを表しているとも言われています。コンポジットでは、輝度の情報(ルーマ)、色の情報(クロマ)、同期信号がわずか1本のケーブルに統合されます。また、通常はコネクタとしてRCAジャックが使用されます。これは、標準的なレベルのオーディオ用の接続に使用されるのと同じものです。ここで、図5をご覧ください。これは、NTSCで使われるコンポジット・ビデオ信号の代表的な波形を示したものです。この信号により、全画面は白になります。

図5. NTSCで使われるコンポジット・ビデオ信号の波形
この図は、信号の一部を示したものであり、1本の水平走査線を表しています。各走査線は、アクティブ・ビデオの部分と水平ブランキングの部分で構成されています。アクティブ・ビデオの部分には、画像の輝度(ルーマ)と色(クロマ)の情報が含まれます。輝度の情報は、任意の時点における瞬時振幅で表されます。振幅の測定単位としては、任意単位であるIREが使われます。具体的には、1Vp-pが140 IREという関係になります。図5から、この水平走査線では、アクティブ・ビデオの部分の電圧によって明るい白の画像が生成されることがわかります。それに対し、水平ブランキングの部分は黒として表示され、画面上では見えません(前掲の図1も参照)。一部のビデオ・システム(NTSCのみ)では、「セットアップ」と呼ばれるものが使用されています。7.5 IREに等しい点、つまりブランキング・レベルから約54mV上の位置に黒の基準が配置されます。
色の情報は、ルーマの信号の上に追加されます。具体的には、カラー・バーストによる基準位相との間の特定の位相差によって色を識別するための正弦波が追加されます。これについては図6をご覧ください。この図には、カラー・バーの水平走査線を示してあります。

図6. コンポジット・ビデオの信号波形(カラー・バー)
変調信号の振幅は、色の量(または飽和度)に比例します。また、位相の情報は色の色調(または色相)を表します。水平ブランキングの部分には、水平同期パルス(シンク・パルス)とシンク・パルスの立ち上がりエッジの直後(バック・ポーチ)に位置する色の基準(カラー・バースト)が含まれています。信号の水平ブランキングの部分は、ディスプレイの画面に表示されない時間に位置しているということが重要です。
Y/Cインターフェース
Y/C信号は、必要なエンコーディング処理がより少ないビデオ信号です。Y信号である輝度(ルーマ)、C信号である色信号(クロマ)は、2組の個別のワイヤで伝送されます。コネクタとしてはミニDINタイプのものが使用されます。これは、キーボード用コネクタの小型版に似たものです。
【注意】「Sビデオ」という用語は「Separate Video」の略ですが、Y/C信号の呼称として使用されることがあります。また、録画用のフォーマットに関連してSビデオという用語が使用されるケースもあります。その録画用のフォーマットは元々はソニーのベータマックスで使用されていたものであり、ルーマがクロマとは別に記録されていました。また、この用語は、S-VHSの録画フォーマットの呼称としても使用されていました。
コンポーネント・インターフェース
コンポーネント信号のインターフェースでは、エンコーディング処理の量を最も少なく抑えられます。そのため、最高の性能が得られます。この場合の信号は、ネイティブに近いフォーマットで存在します。このインターフェースでは、常に3対のワイヤを使用します。ルーマ(Y)と2つの色差信号から成るフォーマットか、RGB(赤、緑、青)フォーマットが使われます。ほとんどの場合、RGBフォーマットはコンピュータのアプリケーションで使用されます。一方、色差ベースのフォーマットは一般的にはテレビのアプリケーションで使われます。Y信号には輝度(ルーマ)と同期に関する情報が含まれています。色差の信号にはR-Y信号とB-Y信号が含まれています(Rは赤、Bは青)。この組み合わせの背景には1つの理論が存在します。それは、基本となるR、G、Bの各コンポーネントは、これらの色差信号から求められるというものです。以下、各種の信号の一般的なバリエーションについてまとめます。
- Y、B-Y、R-Y:ルーマと色差信号です。
- Y、Pr、Pb:PrとPbは、B-YとR-Yをスケーリングしたバージョンです。ハイエンドの民生用機器でよく使用されます。ルーマと色差信号です。
- Y、Cr、Cb: Y、Pr、Pbに相当するデジタル信号です。Y、Pr、Pbの代わりに誤って使用されているケースがあります。
- Y、U、V:インターフェースの規格で定められているものではありません。ただ、誤ってコンポーネント・インターフェースとして扱われることがあります。これらは、コンポジット信号とY/C信号を形成する際に使用される中間的な直交信号です。
コンピュータ信号のインターフェース
事実上、すべてのコンピュータのインターフェースでは、RGBフォーマットの信号を使用しています。画像の情報は、R、G、Bの3つの基本的なコンポーネントによって個別に伝送されます。通常、同期に関する情報は、個別のH(水平)信号とV(垂直)信号として伝送されることになります。R、G、B、H、Vの5つの信号は、シールド付きのワイヤの束から成る1本のケーブルで伝送されます。ほとんどの場合、15ピンのD型コネクタが使用されます。HとVのシンク情報は、RGB信号の1つ(通常はGのコンポーネント)と統合されるケースもありました。ただ、これはあまり一般的なものではなくなりつつあります。なお、この手法は「シンク・オン・グリーン(sync on green)」と呼ばれています。まれに、シンク情報がRまたはBの信号に重畳される場合もあります。
用語集
ここからは、ビデオの分野でよく使われる用語について説明することにします。
アスペクト比
表示される画像の幅と高さの比。標準的なテレビやコンピュータのアスペクト比は4:3(1.33)です。HDTVのアスペクト比は4:3または16:9(1.78)となっています。映画では、1.85:1や2.35:1といったアスペクト比が使用されます。
バック・ポーチ
コンポジット・ビデオ信号に含まれる1つの期間。カラー・バーストの終了からアクティブ・ビデオの開始までの時間として定義されます。また、シンクの立ち上がりエッジからアクティブ・ビデオの開始までの総時間という意味で使われることもあります。
ブランキング期間
ブランキング期間には、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間があります。水平ブランキング期間は、信号がディスプレイの右端から左端まで戻り、次の走査線に対する処理を開始するために割り当てられています。一方の垂直ブランキング期間は、信号が最下部から最上部まで戻り、新たなフィールドまたはフレームに対する処理を開始するために確保されています。ブランキング期間には、同期信号が設けられます。
ブランキング・レベル
電圧レベル(ブランキング・レベル)を表すために使用されます。ブランキング・レベルは、より大きな負電圧を使用するシンク・チップを除き、水平期間/垂直期間におけるビデオ信号の波形の公称電圧となります。
ブリーズウェイ
コンポジット・ビデオ信号に含まれる1つの期間。シンク・パルスの立ち上がりエッジからカラー・バーストの開始までの時間として定義されます。
クロマ
ビデオ信号の色の部分のことです。「クロミナンス」と誤って呼ばれることがありますが、クロミナンスは実際に表示される色の情報のことです。
クランプ
クランプ回路は、ビデオ信号の特定の部分(バック・ポーチまたはシンク・チップ)を強制的に特定のDC電圧にして、DCレベルを復元します。この処理は「DC再生」と呼ばれることもあります。黒のレベルをグラウンドにクランプする回路では、バック・ポーチの電圧を強制的に0Vに設定します。ピーク・クランプの回路は、シンク・チップの電圧を強制的に規定の電圧に設定します。
カラー・バー
ビデオ・システムのキャリブレーションに関するテストを行うために使用される標準ビデオ波形のことです。標準の振幅とタイミングを備えた原色と2次色(補色)の6色に白を加えた一連の色の配列で構成されています。アクティブ・ローの色の配列は、白、黄、シアン、緑、マゼンタ、赤、青です。振幅についてはいくつかの基準が設けられています。振幅(輝度)が75%で、飽和度(色の濃度)が100%というのが最も一般的です。
カラー・バースト
カラー・バーストは、カラー・サブキャリアとも呼ばれます。これは、カラー基準周波数の8~10周期分に相当します。コンポジット・ビデオ信号では、シンクの立ち上がりエッジからアクティブ・ビデオの開始までの間に配置されます。
色飽和度
標準的なビデオ信号の色変調の振幅。この変調の振幅が大きいほど、色がより飽和している(より濃くなる)ことになります。
カラー・サブキャリア
「カラー・バースト」の項を参照してください。
コンポーネント・ビデオ
3線式のビデオ・インターフェース。ビデオの情報を、基本であるRGBコンポーネント、またはルーマ(輝度)と2つの色差信号によって伝送します。
コンポジット・ビデオ
コンポジット・ビデオでは、ルーマ(輝度)、クロマ(色)、バースト(色基準)、シンク(水平と垂直の同期信号)を組み合わせて1つの波形として結合し、1対のワイヤで伝送します。
微分ゲイン
コンポジット・ビデオ信号を対象として測定される重要なパラメータです。Y/C信号やコンポーネント信号には適用されません。微分ゲインは、低い周波数におけるルーマ(輝度)の振幅の変化に対する色飽和度(色変調の振幅)の変化量として定義されます。DCレベルの変化に対する正弦波の振幅の変化を測定することにより、ほぼ近似することが可能です。
微分位相
コンポジット・ビデオ信号について測定される重要なパラメータです。Y/C信号やコンポーネント信号には適用されません。微分位相は、低い周波数におけるルーマ(輝度)の振幅の変化に対する色相(色変調の位相)の変化量として定義されます。DCレベルの変化に対する正弦波の位相の変化を測定することによって、ほぼ近似することが可能です。
フィールド、フレーム
1枚の画像をすべて走査したものがフレームです。NTSCの場合、フレームは525本の水平走査線によって構成されます。インターレース・スキャン方式では、1フレームの半分を1フィールドとして扱います。つまり、2つのフィールドで1つのフレームが構成されます。
フロント・ポーチ
コンポジット・ビデオ波形において、アクティブ・ビデオの終了からシンクの前縁までの部分がフロント・ポーチです。
水平ブランキング
「ブランキング・レベル」と「ブランキング期間」の項を参照してください。
水平ライン周波数
1本の水平走査ラインに対応する時間(または周期)の逆数。
インターレース・スキャン
各フレームについて、まずラインの半分を走査し、次に残りのラインを走査することによって画像を生成する方式のことです。2回目に走査したラインを1回目に走査したラインの間に挿入することによって画像が完成します。各回に走査された半分の画像をフィールドと呼びます。つまり、2つのフィールドによって1つのフレームが構成されます。
IRE
ビデオの分野で使用される任意単位。ブランキングから、基準になる白のレベルまでの偏位の1/100に等しい値に相当します。NTSCに対応するシステムでは、100 IREは714mV、1Vp-pは140 IREになります。
ルーマ
ビデオ信号のモノクロームまたは白黒の部分。この用語は「ルミナンス」と誤って呼ばれることがありますが、ルミナンスは実際に表示される輝度のことを指します。
モノクローム
色情報を除いたビデオ信号のルーマ(輝度)の部分。現在のカラー・テレビが登場する前に、モノクロームは一般に白黒という意味で用いられていました。
NTSC
NTSCは、National Television System Committeeという組織の略称です。この組織は、1941年に米国で白黒テレビの規格を策定しました。また1953年には、カラー・テレビの規格も策定しています。NTSCという言葉は、その特定のカラー変調方式に準拠したシステムや信号のことを指すために使用されています。NTSCの信号は、カラー・サブキャリアを基準として、直交変調による色差信号をルーマに追加する形で構成されます。通常、カラー・サブキャリアの周波数は、水平ライン・レートが15.75kHzの場合、その455/2倍の3.579545MHzになります。一般に、525本の走査線、59.94Hzの走査方式で使用されます。
PAL
PALは、Phase Alternating Lineの略です。この用語は、この特定の変調方式に準拠したシステムや信号を指すために使用されます。NTSCに似ていますが、サブキャリアの位相反転を使用することにより、カラー・エラーとして表示される位相エラーに対する感度を低下させる点が異なります。一般に、4.43362MHzのサブキャリア周波数、626本の走査線、50Hzの走査方式で使用されます。
ピクセル
「画素」とも呼ばれます。ピクセルは、表示の細かさを表す最小単位であり、固有の輝度と色を備えています。デジタル画像の場合、ピクセルは画像内の個々の点であり、一定の数のビットによって輝度を表します。
プログレッシブ・スキャン
プログレッシブ・スキャンでは、フレームのすべてのラインを1回で走査することによって画像を生成します。「インターレース・スキャン」の項も参照してください。なお、インターレース・スキャンからプログレッシブ・スキャンへの変換プロセスを「ライン・ダブリング」と呼びます。
ラスタ
ディスプレイ上で画像を構成する水平走査線の集合をラスタと呼びます。通常、ラスタについて言及する場合、信号の同期に関する要素が含まれていることを前提とします。
リフレッシュ・レート
「垂直フレーム・レート」の項を参照してください。
RGB
Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の略。RGBは、コンピュータ・グラフィック・システムで一般的に使用されるコンポーネント・インターフェースです。
セットアップ
NTSCのアナログ・システムにおいて、ブランキング・レベルより7.5%(7.5 IRE)上に位置する基準用の黒のレベルのことです。PALやデジタルのシステム、HDTVシステムでは使用されません。これらのシステムでは、基準になる黒はブランキングと同じレベルになります。
サブキャリア
「カラー・バースト」の項を参照してください。
Sビデオ
本来は、磁気テープの変調フォーマットのことを指します。ただ、誤ってY/Cと同じ意味で使用されることがよくあります。「Y/C」の項も参照してください。
シンク信号/シンク・パルス
シンク信号は、シンク・パルスとも呼ばれます。これは、ビデオ信号に含まれる負の方向のタイミング・パルスのことです。ディスプレイの水平部分と垂直部分の同期をとるために、ビデオ処理機器やディスプレイ機器で使用されます。
垂直ブランキング
「ブランキング・レベル」と「ブランキング期間」の項を参照してください。
垂直フィールド周波数
ビデオの1フィールド(1フレームの半分)を生成するために必要な時間(または期間)の逆数。NTSCでは59.94Hzとなります。
垂直フレーム・レート
ビデオの1フレームを生成するために必要な時間(または期間)の逆数。「リフレッシュ・レート」または「垂直リフレッシュ・レート」とも呼ばれます。
ビデオ帯域幅、最小ビデオ帯域幅
ビデオ信号に含まれる最小の細かさを再現するために必要な最小アナログ帯域幅。
Y Cr Cb
デジタルのコンポーネント・ビデオ・インターフェース。Yは信号のルーマ(輝度)の部分、CrとCbは信号の色差の部分を表します。
Y Pr Pb
アナログのコンポーネント・ビデオ・インターフェース。Yは信号のルーマ(輝度)の部分、PrとPbは信号の色差の部分を表します。通常、このインターフェースはハイエンドの民生用ビデオ機器で使用されます。
Y/C
クロマ(色)の情報がルーマ(輝度)/シンクの情報とは別に伝送されるアナログ・ビデオ・インターフェース。2対のワイヤが使用されます。表記としては、YおよびCまたはY/Cが使用されます。誤って「Sビデオ」と呼ばれることがよくあります。
VIDEO DESIGNERS: アナログ・ビデオ設計者向けのメール・ベースのディスカッション・グループにぜひご参加ください。
この記事に関して
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}